お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0038 校種 中高一貫校 教科・領域等 国語 単元 エッセー 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供とブックトーク 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 教科書で椎名誠のエッセーを勉強するので、それにあわせて多様な分野のエッセー読ませたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 今回は厳密にエッセイの分野に限定をするのではなく、自然科学系、時事的問題、同世代のエッセイなど、多様な分野の本をそろえて欲しい。4月の図書館オリエンテーションの流れをくんで、本を読むことの楽しさを感じてもらうことを優先したい。
提示資料 多様な分野のエッセイを用意したなかから、個人エッセイ、スポーツ分野のエッセイ、生物分野のエッセイからそれぞれブックトークをしながら紹介。4クラスごとに少しずつ本も変えながら紹介したなかの1例。 
『はい、泳げません』高橋秀実 著.新潮社 2007年
小学校のときに水恐怖症になって以来、泳ぐことを一切避けて過ごしてきた著者。しかし40代になって意を決して泳ぐことに再挑戦する。泳げない人にとってどれほど水が怖いものなのか、また指導をするの言葉と、それを受け取る側の人との思いの違い違いなども書かれており、両者の真剣さがかえって滑稽で笑わずにはいられないエッセ-。スポーツの分野とはいえ、出来ない人の思いがよく伝わってくる1冊。 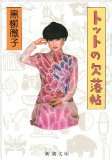
『トットの欠落帖』黒柳徹子 著.新潮社 1993年
何か1つくらい、自分に特有の才能があるに違いないと、著者の黒柳さんはさまざまなことにチャレンジします。クラシックバレエ、犬の調教師、九官鳥の言葉の先生など、とにかくすさまじいばかりの行動力とともに、どんな場所でも何かしらヘマをしてしまう黒柳さん。そんな彼女の失敗談を集めた1冊。 
『ありがとう大五郎』大谷英之(写真)大谷淳子(文)新潮社 1993年
奇形の猿を撮影していた写真家が、ある日一匹の手足がほとんどない子猿を自宅に連れて帰ります。「おみやげだよ」と。しかしその日から奥さんと子どもたちにとっては子猿との大変な日々が始まります。大五郎と名づけられた子猿はやがて家族の一員として欠かせない存在となりますが、その矢先悲しい別れが・・・・。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 中1エッセイリスト.xlsx
キーワード1 エッセー キーワード2 キーワード3 授業計画・指導案等 エッセーを読み味わう 単元計画.doc 児童・生徒の作品 授業者 荻野聡 授業者コメント 授業後に子どもたちから「楽しかった」「またメディアセンターで授業したい」という声がちらほら聞こえてきて、授業者としても大変嬉しい限りでした。
司書・司書教諭コメント 公共図書館から約200冊、自館の本約150冊の合計350冊を提供。本は大きくは7つの分野に分けた。1.私の歩んできた道(個人的エッセー)2.不思議の世界へようこそ(自然科学分野)3.スポーツってすばらしい(運動分野)4.動物とのふれあい(生物分野)5.私たちの住む国(日本の時事問題)6.世界は今(世界の時事問題)7.同世代の思い、考えを知ろう(中学生の作文、論文)。メディアセンターでの最初の授業の冒頭で、各分野のエッセーを紹介し、その分野のなかからいくつかブックトークをおこなった。4月のオリエンテーション直後におこなわれた授業だったため、1年生にはメディアセンターに親しむ良い機会ともなり、例年よりも1年生と良好な関係でスタートをきることができたと感じている。
今回は公共図書館が全面的に協力をしてくれたおかげで、「同世代のエッセー」という教員の要望にたいし、中学生の作文集やコンテストのエッセー集を提供してくれたのでとてもありがたかった。 情報提供校 東京学芸大学附属国際中等教育学校 事例作成日 2010年6月10日 事例作成者氏名 荻野聡(東京学芸大学附属国際中等教育学校)
記入者:渡辺(主担)
カウンタ
3863480 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0038 校種 中高一貫校 教科・領域等 国語 単元 エッセー 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供とブックトーク 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 教科書で椎名誠のエッセーを勉強するので、それにあわせて多様な分野のエッセー読ませたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 今回は厳密にエッセイの分野に限定をするのではなく、自然科学系、時事的問題、同世代のエッセイなど、多様な分野の本をそろえて欲しい。4月の図書館オリエンテーションの流れをくんで、本を読むことの楽しさを感じてもらうことを優先したい。
提示資料 多様な分野のエッセイを用意したなかから、個人エッセイ、スポーツ分野のエッセイ、生物分野のエッセイからそれぞれブックトークをしながら紹介。4クラスごとに少しずつ本も変えながら紹介したなかの1例。 
『はい、泳げません』高橋秀実 著.新潮社 2007年
小学校のときに水恐怖症になって以来、泳ぐことを一切避けて過ごしてきた著者。しかし40代になって意を決して泳ぐことに再挑戦する。泳げない人にとってどれほど水が怖いものなのか、また指導をするの言葉と、それを受け取る側の人との思いの違い違いなども書かれており、両者の真剣さがかえって滑稽で笑わずにはいられないエッセ-。スポーツの分野とはいえ、出来ない人の思いがよく伝わってくる1冊。 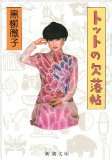
『トットの欠落帖』黒柳徹子 著.新潮社 1993年
何か1つくらい、自分に特有の才能があるに違いないと、著者の黒柳さんはさまざまなことにチャレンジします。クラシックバレエ、犬の調教師、九官鳥の言葉の先生など、とにかくすさまじいばかりの行動力とともに、どんな場所でも何かしらヘマをしてしまう黒柳さん。そんな彼女の失敗談を集めた1冊。 
『ありがとう大五郎』大谷英之(写真)大谷淳子(文)新潮社 1993年
奇形の猿を撮影していた写真家が、ある日一匹の手足がほとんどない子猿を自宅に連れて帰ります。「おみやげだよ」と。しかしその日から奥さんと子どもたちにとっては子猿との大変な日々が始まります。大五郎と名づけられた子猿はやがて家族の一員として欠かせない存在となりますが、その矢先悲しい別れが・・・・。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 中1エッセイリスト.xlsx
キーワード1 エッセー キーワード2 キーワード3 授業計画・指導案等 エッセーを読み味わう 単元計画.doc 児童・生徒の作品 授業者 荻野聡 授業者コメント 授業後に子どもたちから「楽しかった」「またメディアセンターで授業したい」という声がちらほら聞こえてきて、授業者としても大変嬉しい限りでした。
司書・司書教諭コメント 公共図書館から約200冊、自館の本約150冊の合計350冊を提供。本は大きくは7つの分野に分けた。1.私の歩んできた道(個人的エッセー)2.不思議の世界へようこそ(自然科学分野)3.スポーツってすばらしい(運動分野)4.動物とのふれあい(生物分野)5.私たちの住む国(日本の時事問題)6.世界は今(世界の時事問題)7.同世代の思い、考えを知ろう(中学生の作文、論文)。メディアセンターでの最初の授業の冒頭で、各分野のエッセーを紹介し、その分野のなかからいくつかブックトークをおこなった。4月のオリエンテーション直後におこなわれた授業だったため、1年生にはメディアセンターに親しむ良い機会ともなり、例年よりも1年生と良好な関係でスタートをきることができたと感じている。
今回は公共図書館が全面的に協力をしてくれたおかげで、「同世代のエッセー」という教員の要望にたいし、中学生の作文集やコンテストのエッセー集を提供してくれたのでとてもありがたかった。 情報提供校 東京学芸大学附属国際中等教育学校 事例作成日 2010年6月10日 事例作成者氏名 荻野聡(東京学芸大学附属国際中等教育学校)
記入者:渡辺(主担)
カウンタ
3863480 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0038 |
|---|---|
| 校種 | 中高一貫校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | エッセー |
| 対象学年 | 中1 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供とブックトーク |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 教科書で椎名誠のエッセーを勉強するので、それにあわせて多様な分野のエッセー読ませたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 今回は厳密にエッセイの分野に限定をするのではなく、自然科学系、時事的問題、同世代のエッセイなど、多様な分野の本をそろえて欲しい。4月の図書館オリエンテーションの流れをくんで、本を読むことの楽しさを感じてもらうことを優先したい。 |
| 提示資料 | 多様な分野のエッセイを用意したなかから、個人エッセイ、スポーツ分野のエッセイ、生物分野のエッセイからそれぞれブックトークをしながら紹介。4クラスごとに少しずつ本も変えながら紹介したなかの1例。 |
 | 『はい、泳げません』高橋秀実 著.新潮社 2007年 小学校のときに水恐怖症になって以来、泳ぐことを一切避けて過ごしてきた著者。しかし40代になって意を決して泳ぐことに再挑戦する。泳げない人にとってどれほど水が怖いものなのか、また指導をするの言葉と、それを受け取る側の人との思いの違い違いなども書かれており、両者の真剣さがかえって滑稽で笑わずにはいられないエッセ-。スポーツの分野とはいえ、出来ない人の思いがよく伝わってくる1冊。 |
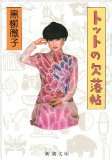 | 『トットの欠落帖』黒柳徹子 著.新潮社 1993年 何か1つくらい、自分に特有の才能があるに違いないと、著者の黒柳さんはさまざまなことにチャレンジします。クラシックバレエ、犬の調教師、九官鳥の言葉の先生など、とにかくすさまじいばかりの行動力とともに、どんな場所でも何かしらヘマをしてしまう黒柳さん。そんな彼女の失敗談を集めた1冊。 |
 | 『ありがとう大五郎』大谷英之(写真)大谷淳子(文)新潮社 1993年 奇形の猿を撮影していた写真家が、ある日一匹の手足がほとんどない子猿を自宅に連れて帰ります。「おみやげだよ」と。しかしその日から奥さんと子どもたちにとっては子猿との大変な日々が始まります。大五郎と名づけられた子猿はやがて家族の一員として欠かせない存在となりますが、その矢先悲しい別れが・・・・。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 中1エッセイリスト.xlsx |
| キーワード1 | エッセー |
| キーワード2 | |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | エッセーを読み味わう 単元計画.doc |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 荻野聡 |
| 授業者コメント | 授業後に子どもたちから「楽しかった」「またメディアセンターで授業したい」という声がちらほら聞こえてきて、授業者としても大変嬉しい限りでした。 |
| 司書・司書教諭コメント | 公共図書館から約200冊、自館の本約150冊の合計350冊を提供。本は大きくは7つの分野に分けた。1.私の歩んできた道(個人的エッセー)2.不思議の世界へようこそ(自然科学分野)3.スポーツってすばらしい(運動分野)4.動物とのふれあい(生物分野)5.私たちの住む国(日本の時事問題)6.世界は今(世界の時事問題)7.同世代の思い、考えを知ろう(中学生の作文、論文)。メディアセンターでの最初の授業の冒頭で、各分野のエッセーを紹介し、その分野のなかからいくつかブックトークをおこなった。4月のオリエンテーション直後におこなわれた授業だったため、1年生にはメディアセンターに親しむ良い機会ともなり、例年よりも1年生と良好な関係でスタートをきることができたと感じている。 今回は公共図書館が全面的に協力をしてくれたおかげで、「同世代のエッセー」という教員の要望にたいし、中学生の作文集やコンテストのエッセー集を提供してくれたのでとてもありがたかった。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 |
| 事例作成日 | 2010年6月10日 |
| 事例作成者氏名 | 荻野聡(東京学芸大学附属国際中等教育学校) |
記入者:渡辺(主担)

























