お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0042 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 ものづくりの知恵 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 小関智弘「ものづくりの知恵」を学習した後の発展読書として、製造業・職人仕事の工夫
が書かれた本を読み、内容を読み取らせたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 教育実習生が、教科書を使って授業をした後の発展学習として、1時間図書館資料を使って調べさせたい。ワークシートに工夫されていることを書き込ませる形式。基本的には授業時間内に終わるようにし、終わらなかった生徒のみ、全クラス終了後、資料を貸し出させる。
提示資料 1冊の本をじっくり読み込むというよりも、授業時間内にいくつかの工夫を読み取らせたいということだったので、図鑑的なものや、家電製品のパンフレット等も用意した。 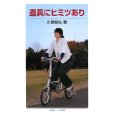
『道具にヒミツあり』 小関 智弘 岩波ジュニア新書 2007.12
ボールペンや消しゴム、ケータイなどの身近な道具をつくった人の工夫がわかりやすく書かれている。1項目も数ページと短く手軽なため、今回の学習にはふさわしく、手に取った生徒が多かった。 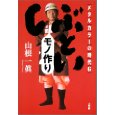
『メタルカラーの時代(6)しぶといモノ作り』 山根 一眞 小学館 2003.7
ノーベル賞受賞科学者から職人まで、ニッポンのモノ作りにこだわる人々へのインタヴューで構成されている。 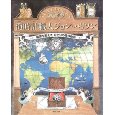
『海時計職人 ジョン・ハリソンー船旅を変えたひとりの男の物語』 ルイーズ・ボーデン、エリック・ブレグバッド あすなろ書房 2005.2
現在地を知らずに航海していた時代に、経度のわかる時計を発明した人の話。絵本ではあるが、ほとんど誤差のない時計を長い年月をかけて改良していく姿が詳しく語られている。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト ものづくりの知恵ブックリスト.xls
キーワード1 ものづくり キーワード2 説明文 キーワード3 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 松原洋子 授業者コメント 教科書教材としての『ものづくりの知恵』には、主に「和釘」「プルトップ缶」「人工衛星まいど1号」という3つの「ものづくり」が描かれている。しかも「和釘」については小学校においても説明文で学んできている生徒が多く、当初から「またか。」といった失望感があった。ゆえに日本が誇る様々な「ものづくり」の技術と精神に気づかせ、視野を広げさせるためにも、何としても教材以外の幅広い「ものづくり」の読み物が必要であった。
諸般の事情により、①1時間以内に読み終わる程度の文量 ②中学1年生にもわかる程度の内容や表現法 ③単なる技術的な説明に終わるのではなく、工夫や苦労についても語られているものが好ましい ④できれば身近な品・システムを扱っていたほうがよい という制約があった。今回、「ものづくり」の「もの」には幅広い解釈を行い、資料を集めていただいた。電化製品のカタログなども立派な資料になった。
司書・司書教諭コメント 早い段階から、どのような資料を集めてほしいのか、明確なイメージが伝えられていたので、他の附属校の協力を得、資料を集めることができた。
生徒のワークシートもあとで拝見したが、まんべんなくどの資料にも目を通していたようだった。 情報提供校 附属小金井中学校 事例作成日 2010.10.15 事例作成者氏名 井谷由紀
記入者:井谷
カウンタ
3863398 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0042 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 ものづくりの知恵 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 小関智弘「ものづくりの知恵」を学習した後の発展読書として、製造業・職人仕事の工夫
が書かれた本を読み、内容を読み取らせたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 教育実習生が、教科書を使って授業をした後の発展学習として、1時間図書館資料を使って調べさせたい。ワークシートに工夫されていることを書き込ませる形式。基本的には授業時間内に終わるようにし、終わらなかった生徒のみ、全クラス終了後、資料を貸し出させる。
提示資料 1冊の本をじっくり読み込むというよりも、授業時間内にいくつかの工夫を読み取らせたいということだったので、図鑑的なものや、家電製品のパンフレット等も用意した。 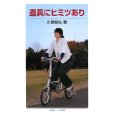
『道具にヒミツあり』 小関 智弘 岩波ジュニア新書 2007.12
ボールペンや消しゴム、ケータイなどの身近な道具をつくった人の工夫がわかりやすく書かれている。1項目も数ページと短く手軽なため、今回の学習にはふさわしく、手に取った生徒が多かった。 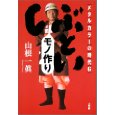
『メタルカラーの時代(6)しぶといモノ作り』 山根 一眞 小学館 2003.7
ノーベル賞受賞科学者から職人まで、ニッポンのモノ作りにこだわる人々へのインタヴューで構成されている。 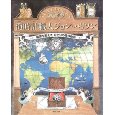
『海時計職人 ジョン・ハリソンー船旅を変えたひとりの男の物語』 ルイーズ・ボーデン、エリック・ブレグバッド あすなろ書房 2005.2
現在地を知らずに航海していた時代に、経度のわかる時計を発明した人の話。絵本ではあるが、ほとんど誤差のない時計を長い年月をかけて改良していく姿が詳しく語られている。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト ものづくりの知恵ブックリスト.xls
キーワード1 ものづくり キーワード2 説明文 キーワード3 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 松原洋子 授業者コメント 教科書教材としての『ものづくりの知恵』には、主に「和釘」「プルトップ缶」「人工衛星まいど1号」という3つの「ものづくり」が描かれている。しかも「和釘」については小学校においても説明文で学んできている生徒が多く、当初から「またか。」といった失望感があった。ゆえに日本が誇る様々な「ものづくり」の技術と精神に気づかせ、視野を広げさせるためにも、何としても教材以外の幅広い「ものづくり」の読み物が必要であった。
諸般の事情により、①1時間以内に読み終わる程度の文量 ②中学1年生にもわかる程度の内容や表現法 ③単なる技術的な説明に終わるのではなく、工夫や苦労についても語られているものが好ましい ④できれば身近な品・システムを扱っていたほうがよい という制約があった。今回、「ものづくり」の「もの」には幅広い解釈を行い、資料を集めていただいた。電化製品のカタログなども立派な資料になった。
司書・司書教諭コメント 早い段階から、どのような資料を集めてほしいのか、明確なイメージが伝えられていたので、他の附属校の協力を得、資料を集めることができた。
生徒のワークシートもあとで拝見したが、まんべんなくどの資料にも目を通していたようだった。 情報提供校 附属小金井中学校 事例作成日 2010.10.15 事例作成者氏名 井谷由紀
記入者:井谷
カウンタ
3863398 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0042 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | ものづくりの知恵 |
| 対象学年 | 中1 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 小関智弘「ものづくりの知恵」を学習した後の発展読書として、製造業・職人仕事の工夫 が書かれた本を読み、内容を読み取らせたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 教育実習生が、教科書を使って授業をした後の発展学習として、1時間図書館資料を使って調べさせたい。ワークシートに工夫されていることを書き込ませる形式。基本的には授業時間内に終わるようにし、終わらなかった生徒のみ、全クラス終了後、資料を貸し出させる。 |
| 提示資料 | 1冊の本をじっくり読み込むというよりも、授業時間内にいくつかの工夫を読み取らせたいということだったので、図鑑的なものや、家電製品のパンフレット等も用意した。 |
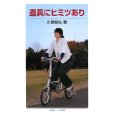 | 『道具にヒミツあり』 小関 智弘 岩波ジュニア新書 2007.12 ボールペンや消しゴム、ケータイなどの身近な道具をつくった人の工夫がわかりやすく書かれている。1項目も数ページと短く手軽なため、今回の学習にはふさわしく、手に取った生徒が多かった。 |
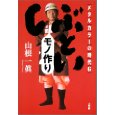 | 『メタルカラーの時代(6)しぶといモノ作り』 山根 一眞 小学館 2003.7 ノーベル賞受賞科学者から職人まで、ニッポンのモノ作りにこだわる人々へのインタヴューで構成されている。 |
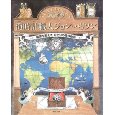 | 『海時計職人 ジョン・ハリソンー船旅を変えたひとりの男の物語』 ルイーズ・ボーデン、エリック・ブレグバッド あすなろ書房 2005.2 現在地を知らずに航海していた時代に、経度のわかる時計を発明した人の話。絵本ではあるが、ほとんど誤差のない時計を長い年月をかけて改良していく姿が詳しく語られている。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | ものづくりの知恵ブックリスト.xls |
| キーワード1 | ものづくり |
| キーワード2 | 説明文 |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 松原洋子 |
| 授業者コメント | 教科書教材としての『ものづくりの知恵』には、主に「和釘」「プルトップ缶」「人工衛星まいど1号」という3つの「ものづくり」が描かれている。しかも「和釘」については小学校においても説明文で学んできている生徒が多く、当初から「またか。」といった失望感があった。ゆえに日本が誇る様々な「ものづくり」の技術と精神に気づかせ、視野を広げさせるためにも、何としても教材以外の幅広い「ものづくり」の読み物が必要であった。 諸般の事情により、①1時間以内に読み終わる程度の文量 ②中学1年生にもわかる程度の内容や表現法 ③単なる技術的な説明に終わるのではなく、工夫や苦労についても語られているものが好ましい ④できれば身近な品・システムを扱っていたほうがよい という制約があった。今回、「ものづくり」の「もの」には幅広い解釈を行い、資料を集めていただいた。電化製品のカタログなども立派な資料になった。 |
| 司書・司書教諭コメント | 早い段階から、どのような資料を集めてほしいのか、明確なイメージが伝えられていたので、他の附属校の協力を得、資料を集めることができた。 生徒のワークシートもあとで拝見したが、まんべんなくどの資料にも目を通していたようだった。 |
| 情報提供校 | 附属小金井中学校 |
| 事例作成日 | 2010.10.15 |
| 事例作成者氏名 | 井谷由紀 |
記入者:井谷

























