お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0005 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 メメント・モリ(死を想え) 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供・ブックリスト配布 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 「命」にかかわる書籍を一人1冊読み、レポートを書かせたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 9月から12月にかけ、生徒は「走れメロス」「心のバリアフリー」「五木寛之の随筆」「葉っぱのフレディ」「平家物語」「わすれられないおくりもの」「千の風になって」「アルフォンス・デーケンの死生学」などを学習しており、そのまとめとして、『限られた生をどう生きるか』『残されたものの思い』『死をどう見つめるか』といったテーマで本を1冊選び、読み込んだ後レポートを書く。
提示資料 1学年160名の生徒に対して、他の付属校・公立図書館に協力をいただき、200冊ほどの書籍を用意した。その際、小説のみに偏らず、さまざまな分類から集めるようにした。ダンボールに入れてカウンター内におき、授業時に貸し出した。 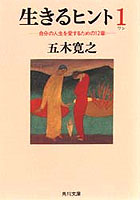
『生きるヒント1』(角川文庫)
五木寛之 著 角川書店 1994年
「自分の人生を愛するための12章」の副題どおり、「歓ぶ」「惑う」「喋る」「知る」など、12のテーマについて書かれたエッセイ集。その中の「想う」が教科書に掲載されていたため、全文を読んでみようという生徒が多かった。人はみな、生まれる場所も、行き着く先も、生きている期間も選ぶことは出来ない。死に向かって進んででいくのだということを若いうちから知って、「死を想って」生きてゆくべきだということを、平易な言葉で書き記した本。 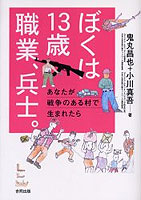
『ぼくは13歳 職業、兵士。』
鬼丸昌也+小川信吾 著 合同出版 2005年
紛争地域で無理やり連れ去られ、武器を持たされて兵士として戦わされる子ども兵が、今現在も世界には存在しています。運良く逃げることができても、心の傷やまわりの無理解などから普通の生活が送れない子どもたちも。親しい人が殺されたり、自分が人を殺したり、日本の子どもたちが想像もできないことが現実に起きていることを知るだけでも、違った目で命について思いをはせられるのではないでしょうか 
『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記 』(幻冬舎文庫)
木藤亜也 著 幻冬舎
15歳の夏に脊髄小脳変性症を発病し、25歳で亡くなるまでの木藤亜也さんの日記を編集したもの。自分たちと年の近いことや、ドラマ化もされたこと、多くの学校から送られて冊数が豊富だったこともあり、この本を取り上げる生徒が多かった。プロの文筆家の手によるものではない、決して上手とも言えない文章が逆に心を打つ。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 2国 命 コメント.xls
キーワード1 命 キーワード2 生き方 キーワード3 死 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 松原洋子 授業者コメント 司書・司書教諭コメント 200冊という冊数に不安があったが、自宅からテーマに沿った本を持参した生徒もおり、一人一人が十分選べたと思う。分類ごとに箱に入れて提示したので、小説の読みたい生徒、それ以外の生徒とスムーズに選書できた。最後に文集に感想をまとめたが、今まで遠い存在だった「死」についてまじめに考えた作品が並んでいた。その後、「おくりびと」などの映画も公開され、蔵書も広がっている。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井中学校 事例作成日 2009年10月13日 事例作成者氏名 井谷由紀
記入者:管理者
カウンタ
3863371 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0005 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 メメント・モリ(死を想え) 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供・ブックリスト配布 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 「命」にかかわる書籍を一人1冊読み、レポートを書かせたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 9月から12月にかけ、生徒は「走れメロス」「心のバリアフリー」「五木寛之の随筆」「葉っぱのフレディ」「平家物語」「わすれられないおくりもの」「千の風になって」「アルフォンス・デーケンの死生学」などを学習しており、そのまとめとして、『限られた生をどう生きるか』『残されたものの思い』『死をどう見つめるか』といったテーマで本を1冊選び、読み込んだ後レポートを書く。
提示資料 1学年160名の生徒に対して、他の付属校・公立図書館に協力をいただき、200冊ほどの書籍を用意した。その際、小説のみに偏らず、さまざまな分類から集めるようにした。ダンボールに入れてカウンター内におき、授業時に貸し出した。 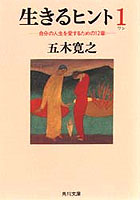
『生きるヒント1』(角川文庫)
五木寛之 著 角川書店 1994年
「自分の人生を愛するための12章」の副題どおり、「歓ぶ」「惑う」「喋る」「知る」など、12のテーマについて書かれたエッセイ集。その中の「想う」が教科書に掲載されていたため、全文を読んでみようという生徒が多かった。人はみな、生まれる場所も、行き着く先も、生きている期間も選ぶことは出来ない。死に向かって進んででいくのだということを若いうちから知って、「死を想って」生きてゆくべきだということを、平易な言葉で書き記した本。 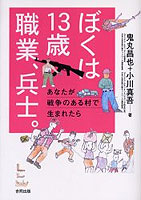
『ぼくは13歳 職業、兵士。』
鬼丸昌也+小川信吾 著 合同出版 2005年
紛争地域で無理やり連れ去られ、武器を持たされて兵士として戦わされる子ども兵が、今現在も世界には存在しています。運良く逃げることができても、心の傷やまわりの無理解などから普通の生活が送れない子どもたちも。親しい人が殺されたり、自分が人を殺したり、日本の子どもたちが想像もできないことが現実に起きていることを知るだけでも、違った目で命について思いをはせられるのではないでしょうか 
『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記 』(幻冬舎文庫)
木藤亜也 著 幻冬舎
15歳の夏に脊髄小脳変性症を発病し、25歳で亡くなるまでの木藤亜也さんの日記を編集したもの。自分たちと年の近いことや、ドラマ化もされたこと、多くの学校から送られて冊数が豊富だったこともあり、この本を取り上げる生徒が多かった。プロの文筆家の手によるものではない、決して上手とも言えない文章が逆に心を打つ。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 2国 命 コメント.xls
キーワード1 命 キーワード2 生き方 キーワード3 死 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 松原洋子 授業者コメント 司書・司書教諭コメント 200冊という冊数に不安があったが、自宅からテーマに沿った本を持参した生徒もおり、一人一人が十分選べたと思う。分類ごとに箱に入れて提示したので、小説の読みたい生徒、それ以外の生徒とスムーズに選書できた。最後に文集に感想をまとめたが、今まで遠い存在だった「死」についてまじめに考えた作品が並んでいた。その後、「おくりびと」などの映画も公開され、蔵書も広がっている。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井中学校 事例作成日 2009年10月13日 事例作成者氏名 井谷由紀
記入者:管理者
カウンタ
3863371 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0005 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | メメント・モリ(死を想え) |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供・ブックリスト配布 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 「命」にかかわる書籍を一人1冊読み、レポートを書かせたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 9月から12月にかけ、生徒は「走れメロス」「心のバリアフリー」「五木寛之の随筆」「葉っぱのフレディ」「平家物語」「わすれられないおくりもの」「千の風になって」「アルフォンス・デーケンの死生学」などを学習しており、そのまとめとして、『限られた生をどう生きるか』『残されたものの思い』『死をどう見つめるか』といったテーマで本を1冊選び、読み込んだ後レポートを書く。 |
| 提示資料 | 1学年160名の生徒に対して、他の付属校・公立図書館に協力をいただき、200冊ほどの書籍を用意した。その際、小説のみに偏らず、さまざまな分類から集めるようにした。ダンボールに入れてカウンター内におき、授業時に貸し出した。 |
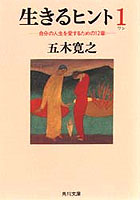 | 『生きるヒント1』(角川文庫) 五木寛之 著 角川書店 1994年 「自分の人生を愛するための12章」の副題どおり、「歓ぶ」「惑う」「喋る」「知る」など、12のテーマについて書かれたエッセイ集。その中の「想う」が教科書に掲載されていたため、全文を読んでみようという生徒が多かった。人はみな、生まれる場所も、行き着く先も、生きている期間も選ぶことは出来ない。死に向かって進んででいくのだということを若いうちから知って、「死を想って」生きてゆくべきだということを、平易な言葉で書き記した本。 |
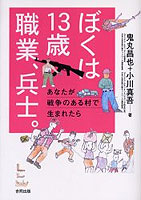 | 『ぼくは13歳 職業、兵士。』 鬼丸昌也+小川信吾 著 合同出版 2005年 紛争地域で無理やり連れ去られ、武器を持たされて兵士として戦わされる子ども兵が、今現在も世界には存在しています。運良く逃げることができても、心の傷やまわりの無理解などから普通の生活が送れない子どもたちも。親しい人が殺されたり、自分が人を殺したり、日本の子どもたちが想像もできないことが現実に起きていることを知るだけでも、違った目で命について思いをはせられるのではないでしょうか |
 | 『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記 』(幻冬舎文庫) 木藤亜也 著 幻冬舎 15歳の夏に脊髄小脳変性症を発病し、25歳で亡くなるまでの木藤亜也さんの日記を編集したもの。自分たちと年の近いことや、ドラマ化もされたこと、多くの学校から送られて冊数が豊富だったこともあり、この本を取り上げる生徒が多かった。プロの文筆家の手によるものではない、決して上手とも言えない文章が逆に心を打つ。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 2国 命 コメント.xls |
| キーワード1 | 命 |
| キーワード2 | 生き方 |
| キーワード3 | 死 |
| 授業計画・指導案等 | |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 松原洋子 |
| 授業者コメント | |
| 司書・司書教諭コメント | 200冊という冊数に不安があったが、自宅からテーマに沿った本を持参した生徒もおり、一人一人が十分選べたと思う。分類ごとに箱に入れて提示したので、小説の読みたい生徒、それ以外の生徒とスムーズに選書できた。最後に文集に感想をまとめたが、今まで遠い存在だった「死」についてまじめに考えた作品が並んでいた。その後、「おくりびと」などの映画も公開され、蔵書も広がっている。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井中学校 |
| 事例作成日 | 2009年10月13日 |
| 事例作成者氏名 | 井谷由紀 |
記入者:管理者

























