お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0007 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 インタビュー(言葉を交わす楽しさを味わう) 対象学年 高2 活用・支援の種類 インタビューを生徒から受ける側として、司書が直接授業に参加をした 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 修学旅行先で現地の人々にインタビューをする前に、生徒にインタビューとはどのようなものか練習をさせたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 生徒からインタビューを受けるにあたり、授業の展開を確認。生徒は事前に1時間、インタビューとは何かを学び、実際に質問内容をグループごとに考える作業をおこなっている。グループは8グループで各4人。生徒には司書の簡単な履歴プリントのみを渡し、それをもとに質問を考えている。50分の授業内で8グループすべての班がインタビューできるように答える。
提示資料 インタビューでの受け答えを通じて、生徒に紹介した本を展示した。(ちなみにブックリストにある本は、インタビューのなかでエピソードとともに司書が紹介した作品です) 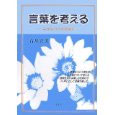
『言葉を考える-中学生の日本語探索-』 石川直美著 渓水社 2007
今回の授業担当教諭の著書。中学生がインタビューをおこなった過去の授業事例や、教科書におけるインタビューの扱いについてわかりやすく解説されている。インタビューとは、何のために聞くのか、何を尋ねたいのか、また質問内容の順番や、会場設営づくりの事例など、インタビューを実践をするうえでの理解と手順が網羅されている。 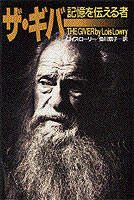
『ザ・ギバー-記憶を伝える者』ロイス・ローリー著 講談社 1995
職業もあらかじめ個々の能力に応じて与えられ、コミュニティには犯罪も飢餓もない理想のユートピア。しかし、自ら選択しながら人生を歩むこととは無縁の生き方や社会は、はたして本当に幸せな社会なのか・・・という問題をなげかける近未来ファンタジー。今回のインタビューの授業で、生徒から「中高生の頃に読んで印象強い作品は?」と尋ねられ、司書が答えた一作。 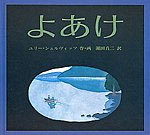
『よあけ』ユリー・シュルヴィッツ作・画 瀬田貞二訳 福音館書店 1977
絵本。唐の詩人、柳宗元の詩「魚翁」をモチーフに、ポーランド出身の画家が描いた作品。時間の流れとともに、静かに夜があけてゆくさまを、見事に描いている。今回の授業では、生徒のインタビューのなかで、「印象に残っている作品は?」と尋ねられ、司書がとりあげた1作。 司書が海外で国際援助の仕事にたずさわっているときにも、現地に持参し”どんなにつらいことがあっても、この作品のように夜は明けるものだからと思った”というエピソードとともに紹介した。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 インタビュー キーワード2 尋ねる キーワード3 聞く 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 石川直美 授業者コメント 一つの質問を通じて、その答えからさらに発展させた質問をするよい機会となった。また新しい図書館ができたばかりであるため、司書とこうした授業をきっかけに知りあい、親しみをもって図書館を利用するいいきっかけにもなるのではないか。予想としては司書の海外での仕事内容に質問が集中するのではないかと思っていたが、なぜ司書という職病を選んだのか、海外から帰国後に日本での仕事に復職することの難しさなど、生徒はむしろ進路選択のことに関心をもったようだ。それはおそらく高校生という自分の進路を考える年齢とも影響しているのだろう。 司書・司書教諭コメント 予測のつかない展開と、意外な質問もあり、初対面の生徒にわかりやすく伝えることに始終した。「どのように図書館の本を選書しているのか」「生徒に薦めない作者はどんな人か」「生徒に期待することは?」「将来自分で図書館をつくりたいと思うか」「また海外援助の仕事をしたいと思っているのか」など、仕事柄本や図書館にかかわる質問が大半を占めた。司書の答えをもとに、発展させた質問もでるなど、修学旅行先でゼロからインタビューをするうえでは多少なりとも事前練習にはなったのではないかと思う。また、話のなかで紹介した作品をすぐに借りてゆく生徒や、休み時間に「追加で質問させてください」と訪れる生徒もあり、授業をきっかけに生徒との距離が近くなったこと感じている。 情報提供校 東京学芸大学附属高校大泉校舎 事例作成日 2009年10月17日 事例作成者氏名 渡辺有理子
記入者:管理者
カウンタ
3863373 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0007 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 インタビュー(言葉を交わす楽しさを味わう) 対象学年 高2 活用・支援の種類 インタビューを生徒から受ける側として、司書が直接授業に参加をした 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 修学旅行先で現地の人々にインタビューをする前に、生徒にインタビューとはどのようなものか練習をさせたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 生徒からインタビューを受けるにあたり、授業の展開を確認。生徒は事前に1時間、インタビューとは何かを学び、実際に質問内容をグループごとに考える作業をおこなっている。グループは8グループで各4人。生徒には司書の簡単な履歴プリントのみを渡し、それをもとに質問を考えている。50分の授業内で8グループすべての班がインタビューできるように答える。
提示資料 インタビューでの受け答えを通じて、生徒に紹介した本を展示した。(ちなみにブックリストにある本は、インタビューのなかでエピソードとともに司書が紹介した作品です) 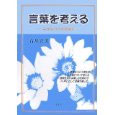
『言葉を考える-中学生の日本語探索-』 石川直美著 渓水社 2007
今回の授業担当教諭の著書。中学生がインタビューをおこなった過去の授業事例や、教科書におけるインタビューの扱いについてわかりやすく解説されている。インタビューとは、何のために聞くのか、何を尋ねたいのか、また質問内容の順番や、会場設営づくりの事例など、インタビューを実践をするうえでの理解と手順が網羅されている。 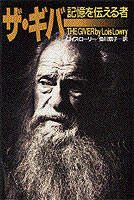
『ザ・ギバー-記憶を伝える者』ロイス・ローリー著 講談社 1995
職業もあらかじめ個々の能力に応じて与えられ、コミュニティには犯罪も飢餓もない理想のユートピア。しかし、自ら選択しながら人生を歩むこととは無縁の生き方や社会は、はたして本当に幸せな社会なのか・・・という問題をなげかける近未来ファンタジー。今回のインタビューの授業で、生徒から「中高生の頃に読んで印象強い作品は?」と尋ねられ、司書が答えた一作。 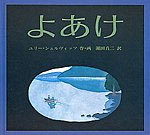
『よあけ』ユリー・シュルヴィッツ作・画 瀬田貞二訳 福音館書店 1977
絵本。唐の詩人、柳宗元の詩「魚翁」をモチーフに、ポーランド出身の画家が描いた作品。時間の流れとともに、静かに夜があけてゆくさまを、見事に描いている。今回の授業では、生徒のインタビューのなかで、「印象に残っている作品は?」と尋ねられ、司書がとりあげた1作。 司書が海外で国際援助の仕事にたずさわっているときにも、現地に持参し”どんなにつらいことがあっても、この作品のように夜は明けるものだからと思った”というエピソードとともに紹介した。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 インタビュー キーワード2 尋ねる キーワード3 聞く 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 石川直美 授業者コメント 一つの質問を通じて、その答えからさらに発展させた質問をするよい機会となった。また新しい図書館ができたばかりであるため、司書とこうした授業をきっかけに知りあい、親しみをもって図書館を利用するいいきっかけにもなるのではないか。予想としては司書の海外での仕事内容に質問が集中するのではないかと思っていたが、なぜ司書という職病を選んだのか、海外から帰国後に日本での仕事に復職することの難しさなど、生徒はむしろ進路選択のことに関心をもったようだ。それはおそらく高校生という自分の進路を考える年齢とも影響しているのだろう。 司書・司書教諭コメント 予測のつかない展開と、意外な質問もあり、初対面の生徒にわかりやすく伝えることに始終した。「どのように図書館の本を選書しているのか」「生徒に薦めない作者はどんな人か」「生徒に期待することは?」「将来自分で図書館をつくりたいと思うか」「また海外援助の仕事をしたいと思っているのか」など、仕事柄本や図書館にかかわる質問が大半を占めた。司書の答えをもとに、発展させた質問もでるなど、修学旅行先でゼロからインタビューをするうえでは多少なりとも事前練習にはなったのではないかと思う。また、話のなかで紹介した作品をすぐに借りてゆく生徒や、休み時間に「追加で質問させてください」と訪れる生徒もあり、授業をきっかけに生徒との距離が近くなったこと感じている。 情報提供校 東京学芸大学附属高校大泉校舎 事例作成日 2009年10月17日 事例作成者氏名 渡辺有理子
記入者:管理者
カウンタ
3863373 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0007 |
|---|---|
| 校種 | 高校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | インタビュー(言葉を交わす楽しさを味わう) |
| 対象学年 | 高2 |
| 活用・支援の種類 | インタビューを生徒から受ける側として、司書が直接授業に参加をした |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 修学旅行先で現地の人々にインタビューをする前に、生徒にインタビューとはどのようなものか練習をさせたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 生徒からインタビューを受けるにあたり、授業の展開を確認。生徒は事前に1時間、インタビューとは何かを学び、実際に質問内容をグループごとに考える作業をおこなっている。グループは8グループで各4人。生徒には司書の簡単な履歴プリントのみを渡し、それをもとに質問を考えている。50分の授業内で8グループすべての班がインタビューできるように答える。 |
| 提示資料 | インタビューでの受け答えを通じて、生徒に紹介した本を展示した。(ちなみにブックリストにある本は、インタビューのなかでエピソードとともに司書が紹介した作品です) |
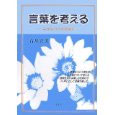 | 『言葉を考える-中学生の日本語探索-』 石川直美著 渓水社 2007 今回の授業担当教諭の著書。中学生がインタビューをおこなった過去の授業事例や、教科書におけるインタビューの扱いについてわかりやすく解説されている。インタビューとは、何のために聞くのか、何を尋ねたいのか、また質問内容の順番や、会場設営づくりの事例など、インタビューを実践をするうえでの理解と手順が網羅されている。 |
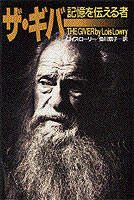 | 『ザ・ギバー-記憶を伝える者』ロイス・ローリー著 講談社 1995 職業もあらかじめ個々の能力に応じて与えられ、コミュニティには犯罪も飢餓もない理想のユートピア。しかし、自ら選択しながら人生を歩むこととは無縁の生き方や社会は、はたして本当に幸せな社会なのか・・・という問題をなげかける近未来ファンタジー。今回のインタビューの授業で、生徒から「中高生の頃に読んで印象強い作品は?」と尋ねられ、司書が答えた一作。 |
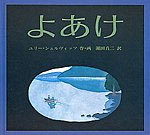 | 『よあけ』ユリー・シュルヴィッツ作・画 瀬田貞二訳 福音館書店 1977 絵本。唐の詩人、柳宗元の詩「魚翁」をモチーフに、ポーランド出身の画家が描いた作品。時間の流れとともに、静かに夜があけてゆくさまを、見事に描いている。今回の授業では、生徒のインタビューのなかで、「印象に残っている作品は?」と尋ねられ、司書がとりあげた1作。 司書が海外で国際援助の仕事にたずさわっているときにも、現地に持参し”どんなにつらいことがあっても、この作品のように夜は明けるものだからと思った”というエピソードとともに紹介した。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | インタビュー |
| キーワード2 | 尋ねる |
| キーワード3 | 聞く |
| 授業計画・指導案等 | |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 石川直美 |
| 授業者コメント | 一つの質問を通じて、その答えからさらに発展させた質問をするよい機会となった。また新しい図書館ができたばかりであるため、司書とこうした授業をきっかけに知りあい、親しみをもって図書館を利用するいいきっかけにもなるのではないか。予想としては司書の海外での仕事内容に質問が集中するのではないかと思っていたが、なぜ司書という職病を選んだのか、海外から帰国後に日本での仕事に復職することの難しさなど、生徒はむしろ進路選択のことに関心をもったようだ。それはおそらく高校生という自分の進路を考える年齢とも影響しているのだろう。 |
| 司書・司書教諭コメント | 予測のつかない展開と、意外な質問もあり、初対面の生徒にわかりやすく伝えることに始終した。「どのように図書館の本を選書しているのか」「生徒に薦めない作者はどんな人か」「生徒に期待することは?」「将来自分で図書館をつくりたいと思うか」「また海外援助の仕事をしたいと思っているのか」など、仕事柄本や図書館にかかわる質問が大半を占めた。司書の答えをもとに、発展させた質問もでるなど、修学旅行先でゼロからインタビューをするうえでは多少なりとも事前練習にはなったのではないかと思う。また、話のなかで紹介した作品をすぐに借りてゆく生徒や、休み時間に「追加で質問させてください」と訪れる生徒もあり、授業をきっかけに生徒との距離が近くなったこと感じている。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属高校大泉校舎 |
| 事例作成日 | 2009年10月17日 |
| 事例作成者氏名 | 渡辺有理子 |
記入者:管理者

























