お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0074 校種 小学校 教科・領域等 総合 単元 対象学年 低学年 活用・支援の種類 本の紹介 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 低学年の総合学習で、織機を使って子どもたちが布を織ります。機織りをしている地域、国の本、布を織るような場面が出ている絵本があったら紹介してください。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 布を織るということが出てくるお話しの絵本でしょうか?
地域のことでは、たくさんのふしぎの『ギョレメ村でじゅうたんを織る』はどうでしょう。
提示資料 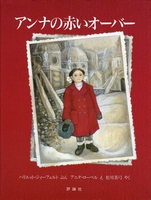
アンナの赤いオーバー
作: ハリエット・ジィーフェルト
絵: アニタ・ローベル
訳: 松川 真弓
出版社: 評論社 1990年
戦争が終わったらオーバーを買ってあげるとアンナはいわれました。戦争が終わったときおじいさんの金時計を売って羊毛を買ってもらい、お母さんとコケモモをつんで、それで赤く染めました。ネックレスを売ってそれで布を織ってもらいました。アンナの赤いオーバーが出来ました。 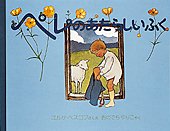
ペレのあたらしいふく
作・絵: エルサ・ベスコフ
訳: 小野寺 百合子
出版社: 福音館書店 1976年
ペレはヒツジをそだてていました。ペレの上着が小さくなったので、羊の毛を刈り、おばあちゃんに毛を梳いてもらい、蒼い染め粉を買ってきて染めという具合にみんなの協力の下に上着が出来ました。 
おひさまいろのきもの
作・絵: 広野 多珂子
出版社: 福音館書店
ふうは目が不自由な女の子です。おかあさんと二人暮らしのふうは、お祭りにおひさま色の着物が欲しいと思いました。お母さんが一生懸命働いて糸を買い、赤く染めて、ふうはおかあさんに教えてもらいながら織りました。お祭りに、ふうはおひさま色の着物を着ました。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 機織りを通して.xlt
キーワード1 織物 キーワード2 児童労働 キーワード3 国際理解 授業計画・指導案等 機織りの実践記録.pdf 児童・生徒の作品 授業者 居城勝彦 授業者コメント 子どもたちは夢中になって布を織り、それをつなげてマフラーを作ったり、ポシェットを作ったりしていた。世界には同じ年頃で、仕事として織物をしていることに気づかせ、児童労働の本を参考に話をした。子どもたちも理解して、自分たちと異なる環境にいる子どもたちがいることに気づいた。絵本を読み聞かせることで、織物のことが理解できたようだ。授業参観で児童労働を取りあげたことで、保護者も関心を持つ機会となり、家庭で子どもと話題としてあがったという報告もあった。 司書・司書教諭コメント 子どもたちが喜々として行っていた織物を行っている時期の図書の時間に、3冊の本を読み聞かせました。子どもたちは「機織りをしているんだ」など、お話しの中で機を織っているシーンを見ながらつぶやいていました。
お話しを自分たちがやっていることにつなげて聞いている姿が見られました。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷小学校 事例作成日 2011/7/21 事例作成者氏名 吉岡裕子
記入者:吉岡
カウンタ
3863370 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0074 校種 小学校 教科・領域等 総合 単元 対象学年 低学年 活用・支援の種類 本の紹介 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 低学年の総合学習で、織機を使って子どもたちが布を織ります。機織りをしている地域、国の本、布を織るような場面が出ている絵本があったら紹介してください。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 布を織るということが出てくるお話しの絵本でしょうか?
地域のことでは、たくさんのふしぎの『ギョレメ村でじゅうたんを織る』はどうでしょう。
提示資料 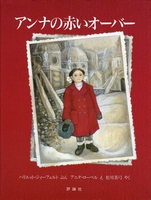
アンナの赤いオーバー
作: ハリエット・ジィーフェルト
絵: アニタ・ローベル
訳: 松川 真弓
出版社: 評論社 1990年
戦争が終わったらオーバーを買ってあげるとアンナはいわれました。戦争が終わったときおじいさんの金時計を売って羊毛を買ってもらい、お母さんとコケモモをつんで、それで赤く染めました。ネックレスを売ってそれで布を織ってもらいました。アンナの赤いオーバーが出来ました。 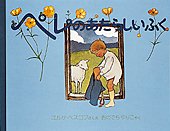
ペレのあたらしいふく
作・絵: エルサ・ベスコフ
訳: 小野寺 百合子
出版社: 福音館書店 1976年
ペレはヒツジをそだてていました。ペレの上着が小さくなったので、羊の毛を刈り、おばあちゃんに毛を梳いてもらい、蒼い染め粉を買ってきて染めという具合にみんなの協力の下に上着が出来ました。 
おひさまいろのきもの
作・絵: 広野 多珂子
出版社: 福音館書店
ふうは目が不自由な女の子です。おかあさんと二人暮らしのふうは、お祭りにおひさま色の着物が欲しいと思いました。お母さんが一生懸命働いて糸を買い、赤く染めて、ふうはおかあさんに教えてもらいながら織りました。お祭りに、ふうはおひさま色の着物を着ました。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 機織りを通して.xlt
キーワード1 織物 キーワード2 児童労働 キーワード3 国際理解 授業計画・指導案等 機織りの実践記録.pdf 児童・生徒の作品 授業者 居城勝彦 授業者コメント 子どもたちは夢中になって布を織り、それをつなげてマフラーを作ったり、ポシェットを作ったりしていた。世界には同じ年頃で、仕事として織物をしていることに気づかせ、児童労働の本を参考に話をした。子どもたちも理解して、自分たちと異なる環境にいる子どもたちがいることに気づいた。絵本を読み聞かせることで、織物のことが理解できたようだ。授業参観で児童労働を取りあげたことで、保護者も関心を持つ機会となり、家庭で子どもと話題としてあがったという報告もあった。 司書・司書教諭コメント 子どもたちが喜々として行っていた織物を行っている時期の図書の時間に、3冊の本を読み聞かせました。子どもたちは「機織りをしているんだ」など、お話しの中で機を織っているシーンを見ながらつぶやいていました。
お話しを自分たちがやっていることにつなげて聞いている姿が見られました。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷小学校 事例作成日 2011/7/21 事例作成者氏名 吉岡裕子
記入者:吉岡
カウンタ
3863370 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0074 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 総合 |
| 単元 | |
| 対象学年 | 低学年 |
| 活用・支援の種類 | 本の紹介 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 低学年の総合学習で、織機を使って子どもたちが布を織ります。機織りをしている地域、国の本、布を織るような場面が出ている絵本があったら紹介してください。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 布を織るということが出てくるお話しの絵本でしょうか? 地域のことでは、たくさんのふしぎの『ギョレメ村でじゅうたんを織る』はどうでしょう。 |
| 提示資料 | |
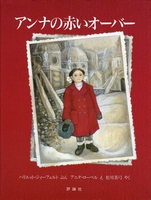 | アンナの赤いオーバー 作: ハリエット・ジィーフェルト 絵: アニタ・ローベル 訳: 松川 真弓 出版社: 評論社 1990年 戦争が終わったらオーバーを買ってあげるとアンナはいわれました。戦争が終わったときおじいさんの金時計を売って羊毛を買ってもらい、お母さんとコケモモをつんで、それで赤く染めました。ネックレスを売ってそれで布を織ってもらいました。アンナの赤いオーバーが出来ました。 |
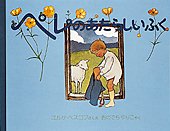 | ペレのあたらしいふく 作・絵: エルサ・ベスコフ 訳: 小野寺 百合子 出版社: 福音館書店 1976年 ペレはヒツジをそだてていました。ペレの上着が小さくなったので、羊の毛を刈り、おばあちゃんに毛を梳いてもらい、蒼い染め粉を買ってきて染めという具合にみんなの協力の下に上着が出来ました。 |
 | おひさまいろのきもの 作・絵: 広野 多珂子 出版社: 福音館書店 ふうは目が不自由な女の子です。おかあさんと二人暮らしのふうは、お祭りにおひさま色の着物が欲しいと思いました。お母さんが一生懸命働いて糸を買い、赤く染めて、ふうはおかあさんに教えてもらいながら織りました。お祭りに、ふうはおひさま色の着物を着ました。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 機織りを通して.xlt |
| キーワード1 | 織物 |
| キーワード2 | 児童労働 |
| キーワード3 | 国際理解 |
| 授業計画・指導案等 | 機織りの実践記録.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 居城勝彦 |
| 授業者コメント | 子どもたちは夢中になって布を織り、それをつなげてマフラーを作ったり、ポシェットを作ったりしていた。世界には同じ年頃で、仕事として織物をしていることに気づかせ、児童労働の本を参考に話をした。子どもたちも理解して、自分たちと異なる環境にいる子どもたちがいることに気づいた。絵本を読み聞かせることで、織物のことが理解できたようだ。授業参観で児童労働を取りあげたことで、保護者も関心を持つ機会となり、家庭で子どもと話題としてあがったという報告もあった。 |
| 司書・司書教諭コメント | 子どもたちが喜々として行っていた織物を行っている時期の図書の時間に、3冊の本を読み聞かせました。子どもたちは「機織りをしているんだ」など、お話しの中で機を織っているシーンを見ながらつぶやいていました。 お話しを自分たちがやっていることにつなげて聞いている姿が見られました。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 |
| 事例作成日 | 2011/7/21 |
| 事例作成者氏名 | 吉岡裕子 |
記入者:吉岡

























