お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0067 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 日本の諸地域 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 日本の諸地域について、グループ学習を予定しているので、県別の資料を含めて、キーワードリストにそった資料の収集と準備をお願いします。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 北陸地方、東京の授業を参考にし、各地域の特色と課題をとらえて調べ発表し、学び会う。
地域は沖縄、北海道、九州、中国・四国、近畿、東北、東海、東山と8グループにわけ、5人のメンバーで、それぞれの地域のテーマを役割分担し、調べた上ですりあわせ、考え話しあう。
その後、自分たちの作った資料や地図を提示しながら発表する。
産業の特色を理解し、作っている側にも目をむけるよう、具体的な地域の事例、人となりのわかる資料を用意する。
また、生徒自身がテーマをみつけるようにする。
提示資料 自館にあるもの、各附属学校と公共図書館から協力を頂き、団体貸し出しで資料を用意し、社会科教諭に委ねた。他、各都道府県のドキュメント資料も収集した。
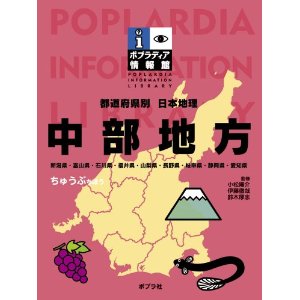
『ポプラディア情報館 都道府県別日本地理』全6巻
県の地理の基本データだけでなく、自然、歴史、産業、文化の特色を豊富な写真やグラフ資料もおおく、わかりやすい基本の本
市町村の一覧で面積、人口また人口の移り変わりや平均寿命、人口過疎化や過密化、産業のようす、食料自給率や農業産出額上位品目、漁業生産量やくらしのデータが記載されている。 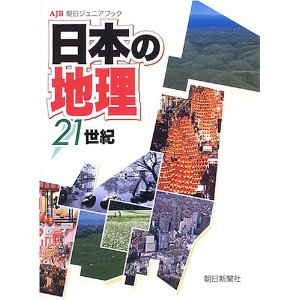
『朝日ジュニアブック 日本の地理21世紀』 高橋伸夫 朝日新聞社 2800円
写真、図版も多く、日本の自然、産業、文化くらしと地域の特色が楽しみながらよくわかる一冊。
目次 地理の目でみる日本・宇宙からみた日本・ぐるっと日本地理の旅他
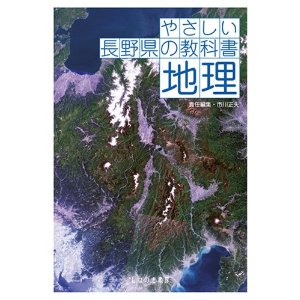
『やさしい長野県の教科書』責任編集 市川正夫 しなのき書房 1600円
長野県の基礎知識がわかるよう、長野県の先生方が3年の月日をかけてつくった本で、地理の学習のみならず、総合学習や校外学習の参考になります。(自然環境・産業と生活・地域から見た長野県)
写真や図版、統計資料・参考文献も多く、コラムも面白いです。
参考資料(含HP) http://www.stat.go.jp/naruhodo/c1s3.htm 参考資料リンク http://www.kodomo.go.jp/promote/school/project.html ブックリスト 竹早中1年日本諸地域調べ_生徒用リスト1.xls
キーワード1 都道府県 キーワード2 各県の産業 キーワード3 各県の特色 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 荒井 正剛 授業者コメント 世界地理の場合は,国別・地方別に書かれた図書は多い。一方,日本地理の場合は,日本全体をテーマに書かれた図書は多いが,地方別をテーマにした図書は少ない。そのため,必要な図書を探す上で苦労した生徒も少なくなかった。また,沖縄や北海道のように比較的多く出版されている地域はともかく,それ以外の地域の場合,図書が少ないのが現状である。
今回,検索機能を利用して,キーワードから適当な図書を探して頂き,助かった。学校にある図書には限りがあるので,区立図書館などからもお借りした。外部の図書館の活用は大切であると思う。
司書・司書教諭コメント 国際こども図書館が、行った授業支援について、詳しいことは、リンクを参照してください。(授業者への聞きどころ・ブックリスト作成の手順、等)
支援の中で、ブックリストを作成して頂き、ブックリストを渡すクラスと渡さないクラスと調べに違いがあるか、比較検討できるようにした。
ブックリストのWeb情報は、生徒が最新のデータを直でしらべる、アドレスを掲載した。
最初の一時間で資料集・地図帳といった身近な資料を使って、地域の基本的な知識を調べ、そこで疑問に思ったことや調べたいことをテーマにした。
グループに分かれ、各々のテーマにもとづき地域の基本的な地理の情報を押さえた上で、自分の興味のあることや疑問、課題点を調べる。次に授業時間に2グループずつ、自分たちの作った資料を配布し、地図や資料を提示しながら発表する。
その後質疑応答をうけたのち、先生から補足説明をうける。ワークシートを埋め、自分たちの発表したことや他のグループの発表を聞くことにより、各々違う地域をを調べているのに、共通すること、繋がっていること、また東京に住んでいる自分たちとの関係を学んでいたようだ。
発表を重ねるうちに、資料の見せ方、プレゼンが上手になっていった。今まで、中学の授業に資料提供のみで、参加していなかったので、先生の授業の構築、子どもたちの調べる様子がわかり、地理の面白さをあらためて知り、実りの多い時間を過ごした。これからは、これを機会に授業支援をしたいと思った。
国際こども図書館の学校支援プロジェクトによる事例で、帝京大学の鎌田先生、国際子ども図書館の企画推進委員会の皆さんのおかげで、感謝しています。 情報提供校 東京学芸大学附属竹早中学校 事例作成日 20110801 事例作成者氏名 岡島玲子
記入者:岡島(主担)
カウンタ
3863432 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0067 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 日本の諸地域 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 日本の諸地域について、グループ学習を予定しているので、県別の資料を含めて、キーワードリストにそった資料の収集と準備をお願いします。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 北陸地方、東京の授業を参考にし、各地域の特色と課題をとらえて調べ発表し、学び会う。
地域は沖縄、北海道、九州、中国・四国、近畿、東北、東海、東山と8グループにわけ、5人のメンバーで、それぞれの地域のテーマを役割分担し、調べた上ですりあわせ、考え話しあう。
その後、自分たちの作った資料や地図を提示しながら発表する。
産業の特色を理解し、作っている側にも目をむけるよう、具体的な地域の事例、人となりのわかる資料を用意する。
また、生徒自身がテーマをみつけるようにする。
提示資料 自館にあるもの、各附属学校と公共図書館から協力を頂き、団体貸し出しで資料を用意し、社会科教諭に委ねた。他、各都道府県のドキュメント資料も収集した。
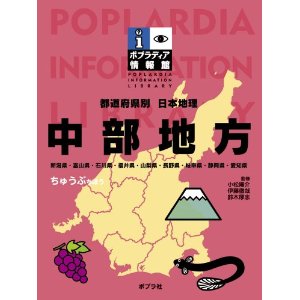
『ポプラディア情報館 都道府県別日本地理』全6巻
県の地理の基本データだけでなく、自然、歴史、産業、文化の特色を豊富な写真やグラフ資料もおおく、わかりやすい基本の本
市町村の一覧で面積、人口また人口の移り変わりや平均寿命、人口過疎化や過密化、産業のようす、食料自給率や農業産出額上位品目、漁業生産量やくらしのデータが記載されている。 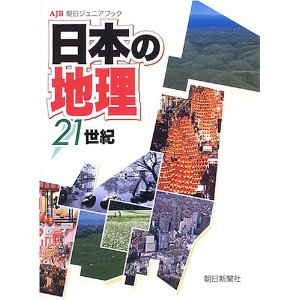
『朝日ジュニアブック 日本の地理21世紀』 高橋伸夫 朝日新聞社 2800円
写真、図版も多く、日本の自然、産業、文化くらしと地域の特色が楽しみながらよくわかる一冊。
目次 地理の目でみる日本・宇宙からみた日本・ぐるっと日本地理の旅他
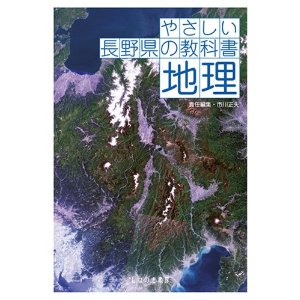
『やさしい長野県の教科書』責任編集 市川正夫 しなのき書房 1600円
長野県の基礎知識がわかるよう、長野県の先生方が3年の月日をかけてつくった本で、地理の学習のみならず、総合学習や校外学習の参考になります。(自然環境・産業と生活・地域から見た長野県)
写真や図版、統計資料・参考文献も多く、コラムも面白いです。
参考資料(含HP) http://www.stat.go.jp/naruhodo/c1s3.htm 参考資料リンク http://www.kodomo.go.jp/promote/school/project.html ブックリスト 竹早中1年日本諸地域調べ_生徒用リスト1.xls
キーワード1 都道府県 キーワード2 各県の産業 キーワード3 各県の特色 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 荒井 正剛 授業者コメント 世界地理の場合は,国別・地方別に書かれた図書は多い。一方,日本地理の場合は,日本全体をテーマに書かれた図書は多いが,地方別をテーマにした図書は少ない。そのため,必要な図書を探す上で苦労した生徒も少なくなかった。また,沖縄や北海道のように比較的多く出版されている地域はともかく,それ以外の地域の場合,図書が少ないのが現状である。
今回,検索機能を利用して,キーワードから適当な図書を探して頂き,助かった。学校にある図書には限りがあるので,区立図書館などからもお借りした。外部の図書館の活用は大切であると思う。
司書・司書教諭コメント 国際こども図書館が、行った授業支援について、詳しいことは、リンクを参照してください。(授業者への聞きどころ・ブックリスト作成の手順、等)
支援の中で、ブックリストを作成して頂き、ブックリストを渡すクラスと渡さないクラスと調べに違いがあるか、比較検討できるようにした。
ブックリストのWeb情報は、生徒が最新のデータを直でしらべる、アドレスを掲載した。
最初の一時間で資料集・地図帳といった身近な資料を使って、地域の基本的な知識を調べ、そこで疑問に思ったことや調べたいことをテーマにした。
グループに分かれ、各々のテーマにもとづき地域の基本的な地理の情報を押さえた上で、自分の興味のあることや疑問、課題点を調べる。次に授業時間に2グループずつ、自分たちの作った資料を配布し、地図や資料を提示しながら発表する。
その後質疑応答をうけたのち、先生から補足説明をうける。ワークシートを埋め、自分たちの発表したことや他のグループの発表を聞くことにより、各々違う地域をを調べているのに、共通すること、繋がっていること、また東京に住んでいる自分たちとの関係を学んでいたようだ。
発表を重ねるうちに、資料の見せ方、プレゼンが上手になっていった。今まで、中学の授業に資料提供のみで、参加していなかったので、先生の授業の構築、子どもたちの調べる様子がわかり、地理の面白さをあらためて知り、実りの多い時間を過ごした。これからは、これを機会に授業支援をしたいと思った。
国際こども図書館の学校支援プロジェクトによる事例で、帝京大学の鎌田先生、国際子ども図書館の企画推進委員会の皆さんのおかげで、感謝しています。 情報提供校 東京学芸大学附属竹早中学校 事例作成日 20110801 事例作成者氏名 岡島玲子
記入者:岡島(主担)
カウンタ
3863432 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0067 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 社会 |
| 単元 | 日本の諸地域 |
| 対象学年 | 中1 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 日本の諸地域について、グループ学習を予定しているので、県別の資料を含めて、キーワードリストにそった資料の収集と準備をお願いします。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 北陸地方、東京の授業を参考にし、各地域の特色と課題をとらえて調べ発表し、学び会う。 地域は沖縄、北海道、九州、中国・四国、近畿、東北、東海、東山と8グループにわけ、5人のメンバーで、それぞれの地域のテーマを役割分担し、調べた上ですりあわせ、考え話しあう。 その後、自分たちの作った資料や地図を提示しながら発表する。 産業の特色を理解し、作っている側にも目をむけるよう、具体的な地域の事例、人となりのわかる資料を用意する。 また、生徒自身がテーマをみつけるようにする。 |
| 提示資料 | 自館にあるもの、各附属学校と公共図書館から協力を頂き、団体貸し出しで資料を用意し、社会科教諭に委ねた。他、各都道府県のドキュメント資料も収集した。 |
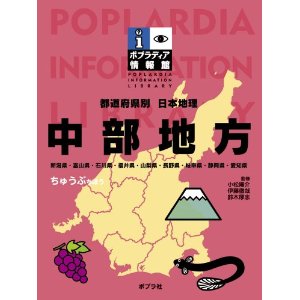 | 『ポプラディア情報館 都道府県別日本地理』全6巻 県の地理の基本データだけでなく、自然、歴史、産業、文化の特色を豊富な写真やグラフ資料もおおく、わかりやすい基本の本 市町村の一覧で面積、人口また人口の移り変わりや平均寿命、人口過疎化や過密化、産業のようす、食料自給率や農業産出額上位品目、漁業生産量やくらしのデータが記載されている。 |
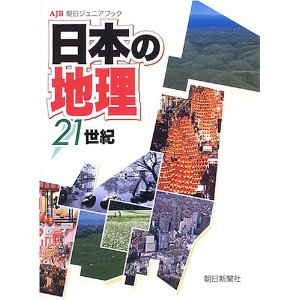 | 『朝日ジュニアブック 日本の地理21世紀』 高橋伸夫 朝日新聞社 2800円 写真、図版も多く、日本の自然、産業、文化くらしと地域の特色が楽しみながらよくわかる一冊。 目次 地理の目でみる日本・宇宙からみた日本・ぐるっと日本地理の旅他 |
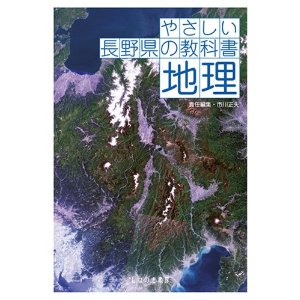 | 『やさしい長野県の教科書』責任編集 市川正夫 しなのき書房 1600円 長野県の基礎知識がわかるよう、長野県の先生方が3年の月日をかけてつくった本で、地理の学習のみならず、総合学習や校外学習の参考になります。(自然環境・産業と生活・地域から見た長野県) 写真や図版、統計資料・参考文献も多く、コラムも面白いです。 |
| 参考資料(含HP) | http://www.stat.go.jp/naruhodo/c1s3.htm |
| 参考資料リンク | http://www.kodomo.go.jp/promote/school/project.html |
| ブックリスト | 竹早中1年日本諸地域調べ_生徒用リスト1.xls |
| キーワード1 | 都道府県 |
| キーワード2 | 各県の産業 |
| キーワード3 | 各県の特色 |
| 授業計画・指導案等 | |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 荒井 正剛 |
| 授業者コメント | 世界地理の場合は,国別・地方別に書かれた図書は多い。一方,日本地理の場合は,日本全体をテーマに書かれた図書は多いが,地方別をテーマにした図書は少ない。そのため,必要な図書を探す上で苦労した生徒も少なくなかった。また,沖縄や北海道のように比較的多く出版されている地域はともかく,それ以外の地域の場合,図書が少ないのが現状である。 今回,検索機能を利用して,キーワードから適当な図書を探して頂き,助かった。学校にある図書には限りがあるので,区立図書館などからもお借りした。外部の図書館の活用は大切であると思う。 |
| 司書・司書教諭コメント | 国際こども図書館が、行った授業支援について、詳しいことは、リンクを参照してください。(授業者への聞きどころ・ブックリスト作成の手順、等) 支援の中で、ブックリストを作成して頂き、ブックリストを渡すクラスと渡さないクラスと調べに違いがあるか、比較検討できるようにした。 ブックリストのWeb情報は、生徒が最新のデータを直でしらべる、アドレスを掲載した。 最初の一時間で資料集・地図帳といった身近な資料を使って、地域の基本的な知識を調べ、そこで疑問に思ったことや調べたいことをテーマにした。 グループに分かれ、各々のテーマにもとづき地域の基本的な地理の情報を押さえた上で、自分の興味のあることや疑問、課題点を調べる。次に授業時間に2グループずつ、自分たちの作った資料を配布し、地図や資料を提示しながら発表する。 その後質疑応答をうけたのち、先生から補足説明をうける。ワークシートを埋め、自分たちの発表したことや他のグループの発表を聞くことにより、各々違う地域をを調べているのに、共通すること、繋がっていること、また東京に住んでいる自分たちとの関係を学んでいたようだ。 発表を重ねるうちに、資料の見せ方、プレゼンが上手になっていった。今まで、中学の授業に資料提供のみで、参加していなかったので、先生の授業の構築、子どもたちの調べる様子がわかり、地理の面白さをあらためて知り、実りの多い時間を過ごした。これからは、これを機会に授業支援をしたいと思った。 国際こども図書館の学校支援プロジェクトによる事例で、帝京大学の鎌田先生、国際子ども図書館の企画推進委員会の皆さんのおかげで、感謝しています。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属竹早中学校 |
| 事例作成日 | 20110801 |
| 事例作成者氏名 | 岡島玲子 |
記入者:岡島(主担)

























