お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0073 校種 中学校 教科・領域等 総合 単元 創作叙事詩を書こう-絵本『父は空 母は大地』を読んで- 対象学年 中2 活用・支援の種類 関連資料の展示 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) テーマ研究 特別授業で紹介した『父は空 母は大地』を図書館で展示してほしい。
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 本校のテーマ研究は、1.2年生を対象に行われている選択制の授業である。特別ゲストとして行った授業の中で寮美千子さんの『父は空 母は大地』をとりあげたので、できれば学校図書館に展示をしてもらいたい。
提示資料 授業後、図書館には『父は空 母は大地』だけでなく、先住民族側からの視点でとらえたアメリカの歴史の本なども一緒に並べて展示しました。 
『父は空 母は大地-インディアンからの手紙-』寮美千子訳(パロル舎)
1854年、アメリカ先住民の首長シアトルが、アメリカ14代大統領フランクリン・ピアスに向けて行ったスピーチを元にしてつくられ絵本。
追記:2016年3月ロクリン社より、文章は加筆修正され、すべての画を新たに書き下ろして、復刊された。 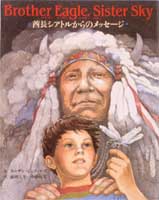
『ブラザーイーグル、シスタースカイ・酋長シアトルからのメッセージ』 絵:スーザン・ジェファーズ 訳:徳岡久生/中西敏夫 JULA出版 1996年
こちらは、同じく酋長シアトルのメッセージを、スーザン・ジェファーソンが描いた絵本。1992年度アメリカ書店業協会賞を受賞し、ヨーロッパ各国で翻訳出版されている。 
『学校では教えてくれない本当のアメリカの歴史 上』 ハワード・ジン著 あすなろ書房 2009年
コロンブスのアメリカ大陸上陸からアメリカ・スペイン戦争まで、教科書には載っていない、恐るべきアメリカの歴史。『民衆のアメリカ史』(TBSブリタニカ)を若い人むけにリライトした本。先住民族であるネイティブアメリカンの視点からコロンブスを見れば、彼は英雄とは呼べない。アメリカ史における真の英雄とは誰か? 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://ryomichico.net/seattle.html ブックリスト 先住民族関連資料.xls
キーワード1 創作叙事詩 キーワード2 解題 キーワード3 想像力 授業計画・指導案等 ●2011授業デザイン曼荼羅(世中実践)改訂版.pdf 児童・生徒の作品 授業者 成田喜一郎(石本貞衡・橋本和顕) 授業者コメント ▼寮美千子訳『父は空 母は大地-インディアンからの手紙-』(パロル舎)は、19世紀と21世紀、アメリカと日本、ネイティブ・アメリカンと白人とわたくしたちという時代や国、人種を超えて、しかもこどもからおとなまで世代を超えて読み解くことのできる不思議な絵本です。▼この絵本からは、アメリカ西部開拓の歴史、アメリカ先住民の暮らしの中の自然観や世界観・人生観、多文化共生への視点と可能性、環境問題への本質的で根源的な問いかけ、挿画の豊かさとイメージなど、読み解いたり感じ取ったりすることできます。▼それに加えて、Post3.11東日本大震災と原発事故で被災・被曝した土地と人々・生き物への思いとつながりかかわることになります。▼この授業は、この「絵本」の読み聞かせに始まり、生徒同士の対話、生徒と教師との対話を通じて絵本の中の「社会的な事実」を探り合い共有したうえで、生徒たちは初めて「創作叙事詩」と「解題」を書きます。▼生徒たちは、「絵本」から読み取った事実に各自の「想像力」を加え掛け、「叙事詩」を「創作」する経験をしました。しかも、さらに「なぜ、この詩を書いたのか」「この詩の背景にある事実とは何か」を自ら解き明かす「解題」まで書きました。いかなる作品ができたのか、今ここでお見せできませんが、いずれご本人たちの許諾を得て別の機会にご紹介したいと考えています。▼今回、ここで紹介した実践は中学校におけるものですが、大学生・大学院生・日米の教員・市民への読み聞かせをしてきました。この絵本に流れる物語の深い「魂」は世代を超えて、人々に考えさせ感じさせるものがあります。▼ある中学校の音楽科の先生は、この絵本の読み聞かせを聴き、混声合唱とオーケストラのためカンタータ「土の歌」第7楽章「大地讃頌」を想起したと言います。絵本の中に潜む様々な事実・事象の物語は、聴き手の思考と想像力を掻き立てます。▼「土の歌」は、第1楽章「農夫と土」、第2楽章「祖国の土」、第3楽章「死の灰」、第4楽章「もぐらもち」、第5章「天地の怒り」、第6楽章「地上の祈り」と続き、最終楽章「大地讃頌」で締めくくられます。▼「絵本の読み聞かせ」という古くて新しい手法、「事実+想像力→創作叙事詩」という学びの化学反応式と自らの学びを省察・メタ認知する「解題」の教育的な意義や可能性を強く感じることができました。(成田喜一郎)
特別授業まで、まず①「創作叙事詩」づくりの目標は【社会事象と「私」がつながっていることを「右脳的な表現(詩)と左脳的な表現(解題)」で発見する試み】にあることを知り、②「解題の書き方」(左脳的な表現)や③「詩を吟味する方法(書き方や読み方)」(右脳的な表現)をトレーニングしました。そして、「附属世田谷中学校」をテーマに叙事詩づくりを行って特別授業を迎えました。まさに日々つながっている世田谷中学校と「私」を再発見することが難しかった生徒が多かった中、この絵本を通して、社会事象と「私」がつながっていることを実感し、詩や解題を「書きたい」という気持ちになった授業でした。(石本貞衛)
絵本を使った図書資料の読み聞かせは、学習者と豊かなイメージを共有することができます。読み終えた感想交流も、お互いの発見を中心にしていました。さらに、感じ取ったことを表現する活動があり、一人一人の考えたことを短歌のリズム形式でまとめていました。特に、短歌の「解題」がおもしろく、お互いの学び合いに、自然環境や人種問題など、様々な思いが表現され、交流することができていました。(橋本和顕)
司書・司書教諭コメント 図書館に展示コーナーをつくり、『父は空 母は大地』の他にも関連本を並べました。この授業を受けた生徒にも感想を聞いたところ、「絵本はちいさい子のものだと思っていたけれど、そうではなくて、絵本でもこんなに深い表現ができるものだと知りました。」「はじめは、世中をテーマにと言われたので、その程度のモノ・・・と思っていたが、成田先生のお話を聞いて、こんなに壮大で深いテーマだったのだとあらためて感じました。」という言葉が返ってきました。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2011.10.13 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3863386 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0073 校種 中学校 教科・領域等 総合 単元 創作叙事詩を書こう-絵本『父は空 母は大地』を読んで- 対象学年 中2 活用・支援の種類 関連資料の展示 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) テーマ研究 特別授業で紹介した『父は空 母は大地』を図書館で展示してほしい。
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 本校のテーマ研究は、1.2年生を対象に行われている選択制の授業である。特別ゲストとして行った授業の中で寮美千子さんの『父は空 母は大地』をとりあげたので、できれば学校図書館に展示をしてもらいたい。
提示資料 授業後、図書館には『父は空 母は大地』だけでなく、先住民族側からの視点でとらえたアメリカの歴史の本なども一緒に並べて展示しました。 
『父は空 母は大地-インディアンからの手紙-』寮美千子訳(パロル舎)
1854年、アメリカ先住民の首長シアトルが、アメリカ14代大統領フランクリン・ピアスに向けて行ったスピーチを元にしてつくられ絵本。
追記:2016年3月ロクリン社より、文章は加筆修正され、すべての画を新たに書き下ろして、復刊された。 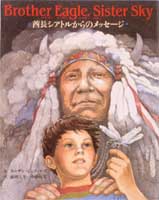
『ブラザーイーグル、シスタースカイ・酋長シアトルからのメッセージ』 絵:スーザン・ジェファーズ 訳:徳岡久生/中西敏夫 JULA出版 1996年
こちらは、同じく酋長シアトルのメッセージを、スーザン・ジェファーソンが描いた絵本。1992年度アメリカ書店業協会賞を受賞し、ヨーロッパ各国で翻訳出版されている。 
『学校では教えてくれない本当のアメリカの歴史 上』 ハワード・ジン著 あすなろ書房 2009年
コロンブスのアメリカ大陸上陸からアメリカ・スペイン戦争まで、教科書には載っていない、恐るべきアメリカの歴史。『民衆のアメリカ史』(TBSブリタニカ)を若い人むけにリライトした本。先住民族であるネイティブアメリカンの視点からコロンブスを見れば、彼は英雄とは呼べない。アメリカ史における真の英雄とは誰か? 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://ryomichico.net/seattle.html ブックリスト 先住民族関連資料.xls
キーワード1 創作叙事詩 キーワード2 解題 キーワード3 想像力 授業計画・指導案等 ●2011授業デザイン曼荼羅(世中実践)改訂版.pdf 児童・生徒の作品 授業者 成田喜一郎(石本貞衡・橋本和顕) 授業者コメント ▼寮美千子訳『父は空 母は大地-インディアンからの手紙-』(パロル舎)は、19世紀と21世紀、アメリカと日本、ネイティブ・アメリカンと白人とわたくしたちという時代や国、人種を超えて、しかもこどもからおとなまで世代を超えて読み解くことのできる不思議な絵本です。▼この絵本からは、アメリカ西部開拓の歴史、アメリカ先住民の暮らしの中の自然観や世界観・人生観、多文化共生への視点と可能性、環境問題への本質的で根源的な問いかけ、挿画の豊かさとイメージなど、読み解いたり感じ取ったりすることできます。▼それに加えて、Post3.11東日本大震災と原発事故で被災・被曝した土地と人々・生き物への思いとつながりかかわることになります。▼この授業は、この「絵本」の読み聞かせに始まり、生徒同士の対話、生徒と教師との対話を通じて絵本の中の「社会的な事実」を探り合い共有したうえで、生徒たちは初めて「創作叙事詩」と「解題」を書きます。▼生徒たちは、「絵本」から読み取った事実に各自の「想像力」を加え掛け、「叙事詩」を「創作」する経験をしました。しかも、さらに「なぜ、この詩を書いたのか」「この詩の背景にある事実とは何か」を自ら解き明かす「解題」まで書きました。いかなる作品ができたのか、今ここでお見せできませんが、いずれご本人たちの許諾を得て別の機会にご紹介したいと考えています。▼今回、ここで紹介した実践は中学校におけるものですが、大学生・大学院生・日米の教員・市民への読み聞かせをしてきました。この絵本に流れる物語の深い「魂」は世代を超えて、人々に考えさせ感じさせるものがあります。▼ある中学校の音楽科の先生は、この絵本の読み聞かせを聴き、混声合唱とオーケストラのためカンタータ「土の歌」第7楽章「大地讃頌」を想起したと言います。絵本の中に潜む様々な事実・事象の物語は、聴き手の思考と想像力を掻き立てます。▼「土の歌」は、第1楽章「農夫と土」、第2楽章「祖国の土」、第3楽章「死の灰」、第4楽章「もぐらもち」、第5章「天地の怒り」、第6楽章「地上の祈り」と続き、最終楽章「大地讃頌」で締めくくられます。▼「絵本の読み聞かせ」という古くて新しい手法、「事実+想像力→創作叙事詩」という学びの化学反応式と自らの学びを省察・メタ認知する「解題」の教育的な意義や可能性を強く感じることができました。(成田喜一郎)
特別授業まで、まず①「創作叙事詩」づくりの目標は【社会事象と「私」がつながっていることを「右脳的な表現(詩)と左脳的な表現(解題)」で発見する試み】にあることを知り、②「解題の書き方」(左脳的な表現)や③「詩を吟味する方法(書き方や読み方)」(右脳的な表現)をトレーニングしました。そして、「附属世田谷中学校」をテーマに叙事詩づくりを行って特別授業を迎えました。まさに日々つながっている世田谷中学校と「私」を再発見することが難しかった生徒が多かった中、この絵本を通して、社会事象と「私」がつながっていることを実感し、詩や解題を「書きたい」という気持ちになった授業でした。(石本貞衛)
絵本を使った図書資料の読み聞かせは、学習者と豊かなイメージを共有することができます。読み終えた感想交流も、お互いの発見を中心にしていました。さらに、感じ取ったことを表現する活動があり、一人一人の考えたことを短歌のリズム形式でまとめていました。特に、短歌の「解題」がおもしろく、お互いの学び合いに、自然環境や人種問題など、様々な思いが表現され、交流することができていました。(橋本和顕)
司書・司書教諭コメント 図書館に展示コーナーをつくり、『父は空 母は大地』の他にも関連本を並べました。この授業を受けた生徒にも感想を聞いたところ、「絵本はちいさい子のものだと思っていたけれど、そうではなくて、絵本でもこんなに深い表現ができるものだと知りました。」「はじめは、世中をテーマにと言われたので、その程度のモノ・・・と思っていたが、成田先生のお話を聞いて、こんなに壮大で深いテーマだったのだとあらためて感じました。」という言葉が返ってきました。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2011.10.13 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3863386 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0073 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 総合 |
| 単元 | 創作叙事詩を書こう-絵本『父は空 母は大地』を読んで- |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 関連資料の展示 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | テーマ研究 特別授業で紹介した『父は空 母は大地』を図書館で展示してほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 本校のテーマ研究は、1.2年生を対象に行われている選択制の授業である。特別ゲストとして行った授業の中で寮美千子さんの『父は空 母は大地』をとりあげたので、できれば学校図書館に展示をしてもらいたい。 |
| 提示資料 | 授業後、図書館には『父は空 母は大地』だけでなく、先住民族側からの視点でとらえたアメリカの歴史の本なども一緒に並べて展示しました。 |
 | 『父は空 母は大地-インディアンからの手紙-』寮美千子訳(パロル舎) 1854年、アメリカ先住民の首長シアトルが、アメリカ14代大統領フランクリン・ピアスに向けて行ったスピーチを元にしてつくられ絵本。 追記:2016年3月ロクリン社より、文章は加筆修正され、すべての画を新たに書き下ろして、復刊された。 |
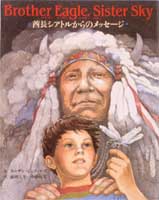 | 『ブラザーイーグル、シスタースカイ・酋長シアトルからのメッセージ』 絵:スーザン・ジェファーズ 訳:徳岡久生/中西敏夫 JULA出版 1996年 こちらは、同じく酋長シアトルのメッセージを、スーザン・ジェファーソンが描いた絵本。1992年度アメリカ書店業協会賞を受賞し、ヨーロッパ各国で翻訳出版されている。 |
 | 『学校では教えてくれない本当のアメリカの歴史 上』 ハワード・ジン著 あすなろ書房 2009年 コロンブスのアメリカ大陸上陸からアメリカ・スペイン戦争まで、教科書には載っていない、恐るべきアメリカの歴史。『民衆のアメリカ史』(TBSブリタニカ)を若い人むけにリライトした本。先住民族であるネイティブアメリカンの視点からコロンブスを見れば、彼は英雄とは呼べない。アメリカ史における真の英雄とは誰か? |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http://ryomichico.net/seattle.html |
| ブックリスト | 先住民族関連資料.xls |
| キーワード1 | 創作叙事詩 |
| キーワード2 | 解題 |
| キーワード3 | 想像力 |
| 授業計画・指導案等 | ●2011授業デザイン曼荼羅(世中実践)改訂版.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 成田喜一郎(石本貞衡・橋本和顕) |
| 授業者コメント | ▼寮美千子訳『父は空 母は大地-インディアンからの手紙-』(パロル舎)は、19世紀と21世紀、アメリカと日本、ネイティブ・アメリカンと白人とわたくしたちという時代や国、人種を超えて、しかもこどもからおとなまで世代を超えて読み解くことのできる不思議な絵本です。▼この絵本からは、アメリカ西部開拓の歴史、アメリカ先住民の暮らしの中の自然観や世界観・人生観、多文化共生への視点と可能性、環境問題への本質的で根源的な問いかけ、挿画の豊かさとイメージなど、読み解いたり感じ取ったりすることできます。▼それに加えて、Post3.11東日本大震災と原発事故で被災・被曝した土地と人々・生き物への思いとつながりかかわることになります。▼この授業は、この「絵本」の読み聞かせに始まり、生徒同士の対話、生徒と教師との対話を通じて絵本の中の「社会的な事実」を探り合い共有したうえで、生徒たちは初めて「創作叙事詩」と「解題」を書きます。▼生徒たちは、「絵本」から読み取った事実に各自の「想像力」を加え掛け、「叙事詩」を「創作」する経験をしました。しかも、さらに「なぜ、この詩を書いたのか」「この詩の背景にある事実とは何か」を自ら解き明かす「解題」まで書きました。いかなる作品ができたのか、今ここでお見せできませんが、いずれご本人たちの許諾を得て別の機会にご紹介したいと考えています。▼今回、ここで紹介した実践は中学校におけるものですが、大学生・大学院生・日米の教員・市民への読み聞かせをしてきました。この絵本に流れる物語の深い「魂」は世代を超えて、人々に考えさせ感じさせるものがあります。▼ある中学校の音楽科の先生は、この絵本の読み聞かせを聴き、混声合唱とオーケストラのためカンタータ「土の歌」第7楽章「大地讃頌」を想起したと言います。絵本の中に潜む様々な事実・事象の物語は、聴き手の思考と想像力を掻き立てます。▼「土の歌」は、第1楽章「農夫と土」、第2楽章「祖国の土」、第3楽章「死の灰」、第4楽章「もぐらもち」、第5章「天地の怒り」、第6楽章「地上の祈り」と続き、最終楽章「大地讃頌」で締めくくられます。▼「絵本の読み聞かせ」という古くて新しい手法、「事実+想像力→創作叙事詩」という学びの化学反応式と自らの学びを省察・メタ認知する「解題」の教育的な意義や可能性を強く感じることができました。(成田喜一郎) 特別授業まで、まず①「創作叙事詩」づくりの目標は【社会事象と「私」がつながっていることを「右脳的な表現(詩)と左脳的な表現(解題)」で発見する試み】にあることを知り、②「解題の書き方」(左脳的な表現)や③「詩を吟味する方法(書き方や読み方)」(右脳的な表現)をトレーニングしました。そして、「附属世田谷中学校」をテーマに叙事詩づくりを行って特別授業を迎えました。まさに日々つながっている世田谷中学校と「私」を再発見することが難しかった生徒が多かった中、この絵本を通して、社会事象と「私」がつながっていることを実感し、詩や解題を「書きたい」という気持ちになった授業でした。(石本貞衛) 絵本を使った図書資料の読み聞かせは、学習者と豊かなイメージを共有することができます。読み終えた感想交流も、お互いの発見を中心にしていました。さらに、感じ取ったことを表現する活動があり、一人一人の考えたことを短歌のリズム形式でまとめていました。特に、短歌の「解題」がおもしろく、お互いの学び合いに、自然環境や人種問題など、様々な思いが表現され、交流することができていました。(橋本和顕) |
| 司書・司書教諭コメント | 図書館に展示コーナーをつくり、『父は空 母は大地』の他にも関連本を並べました。この授業を受けた生徒にも感想を聞いたところ、「絵本はちいさい子のものだと思っていたけれど、そうではなくて、絵本でもこんなに深い表現ができるものだと知りました。」「はじめは、世中をテーマにと言われたので、その程度のモノ・・・と思っていたが、成田先生のお話を聞いて、こんなに壮大で深いテーマだったのだとあらためて感じました。」という言葉が返ってきました。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
| 事例作成日 | 2011.10.13 |
| 事例作成者氏名 | 村上恭子 |
記入者:村上

























