お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0084 校種 小学校 教科・領域等 社会 単元 情報を発信する放送局 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料収集、子どもへの広報 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 東日本大震災に関連した新聞を取り上げて報道の役割について授業を行った。東日本大震災時の報道に関する本をさらに購入してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 東日本大震災時の報道、特に世界でも注目を集めた石巻日日新聞の手書き新聞を取り上げ、報道の役割や責任について考える授業を行っている。関連する本を、子どもの学習環境・読書環境として図書館で収集し、利用できるようにしてほしい。
提示資料 
『6枚の壁新聞 石巻日日新聞・東日本大震災後7日間の記録 角川SSC新書 (角川SSC新書 130) 石巻日日新聞社編 角川マガジンズ(角川グループパブリッシング) 2011.7 ISBN-13: 978-4047315532
「今、伝えなければ、地域の新聞社なんか存在する意味がない」、創業99年の石巻日日新聞社が被災しながら発行した6枚の手書きの壁新聞。「伝える使命」を貫いた記者たちの行動は世界を感動させた。
「大津波警報」のアナウンスが出る前に取材に散っていった6人の記者たち。一晩漂流して救助された記者、渋滞の車から飛び出して走って山に逃げた記者、津波の濁流に課もまれた社屋に残る者…。それぞれの時間を追った体験が、自らも被災し、社員や家族の安否を気遣いながらも、「地元新聞」の「伝える使命」をいかに果たすかと探り、手書き新聞がつくられていったかを語る、迫真のドキュメント。 
『河北新報のいちばん長い日 震災下の地元紙』河北新報社著 文藝春秋 2011.10 ISBN-13: 978-4163744704
河北とは、福島県の「白河以北」を意味し、「一山百文」と明治維新以降軽視された、その名をあえて題字とした独立心を表しているという。1897年創刊の東北を代表するブロック紙である。
被災後の午後4時オープンで、対策会議を開き、社員の安否確認、社の被災状況、そして、新聞の発行に全力を注ぐことの3つを確認した。被災しながら取材を続ける記者たちの苦悩、取材網や販売網が壊滅のさなか、印刷までの製作工程も分断されるが、新潟日報都の相互支援協定による号外をはじめとするその後の発行にこぎつける。被災した人々は河北新報がそのまま、救援物資のごとく力づけられたという。困難のさなか、発行し続けた地方新聞の使命と役割を教えてくれる。2012年3月、ドラマ化決定。2011年度新聞協会賞受賞。 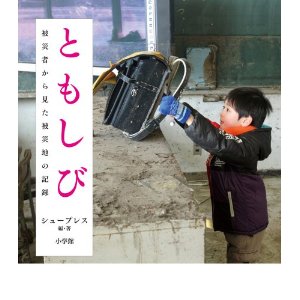
『ともしび』シュ―プレス編著 小学館 2011.8 ISBN-13: 978-4093882033
被災した人々の心をおたためてくれる「ともしび」のような「希望」。
被災した市民に寄り添い、声を聞き、思いを記事にまとめていった地元新聞、東奥日報、岩手日報、三陸新聞、石巻日日新聞、石巻かほく、河北新報、福島民友、いわき日報共同通信社の記事から、「命のともしび」「心のともしび」「勇気のともしび」「希望のともしび」という4章立てでエピソードを拾い、仙台の編集プロダクションが編集した。訪問入浴の最中だった介護士の避難を助けた後に命を落としたいわきの高校生の話、亡くなった弟のために青いこいのぼりを挙げる石巻の高校生の話など。手書き新聞や気仙沼の子どもたちのファイト新聞の記事もある。巻頭の口絵もよい。
「津波てんでんこ」を提唱してきた山下文男氏(87歳)は陸前高田の高田病院の4階で被災し、コメントを寄せている。(p58,59) 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://dl.ndl.go.jp/#newspaper ブックリスト
キーワード1 マスメディア キーワード2 新聞 キーワード3 放送 授業計画・指導案等 小5社会 情報を発信する放送局.tif 児童・生徒の作品 授業者 小倉勝登 授業者コメント 司書・司書教諭コメント 小倉学級の子どもたちのアンテナは高い。写真集やノンフィクションを入れるそばから反応して、借りていく。小学生新聞3紙(朝日小学生新聞、毎日小学生新聞、よみうりKODOMO新聞)、ニュース雑誌2誌(ニュースがわかる、朝日ジュニアアエラ)も購入している図書館環境を、担任も子どもたちもフル活用してくれているといっていい。ブックトークを作成中だが、これらのノンフィクションを組み入れた子たちも多くいる。
これは時事問題の教材化ということで、現地取材、インタビュー、さまざまな活動であつめた情報をもとに授業をデザインする小倉実践を、司書教諭科目を取っている学生にも話をしてもらった。「他人事」ではなく「自分ごと」として社会的事象をとらえてほしいという、教師の願いを実現する丹念な教材研究とそれを生かした授業デザインを学ばせてもらう好機となった。
朝日小学生新聞2012年1月27日1面「震災で変わる教科書」に小倉教諭のコメントが出ている。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2011.12.12. 事例作成者氏名 中山美由紀
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863376 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0084 校種 小学校 教科・領域等 社会 単元 情報を発信する放送局 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料収集、子どもへの広報 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 東日本大震災に関連した新聞を取り上げて報道の役割について授業を行った。東日本大震災時の報道に関する本をさらに購入してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 東日本大震災時の報道、特に世界でも注目を集めた石巻日日新聞の手書き新聞を取り上げ、報道の役割や責任について考える授業を行っている。関連する本を、子どもの学習環境・読書環境として図書館で収集し、利用できるようにしてほしい。
提示資料 
『6枚の壁新聞 石巻日日新聞・東日本大震災後7日間の記録 角川SSC新書 (角川SSC新書 130) 石巻日日新聞社編 角川マガジンズ(角川グループパブリッシング) 2011.7 ISBN-13: 978-4047315532
「今、伝えなければ、地域の新聞社なんか存在する意味がない」、創業99年の石巻日日新聞社が被災しながら発行した6枚の手書きの壁新聞。「伝える使命」を貫いた記者たちの行動は世界を感動させた。
「大津波警報」のアナウンスが出る前に取材に散っていった6人の記者たち。一晩漂流して救助された記者、渋滞の車から飛び出して走って山に逃げた記者、津波の濁流に課もまれた社屋に残る者…。それぞれの時間を追った体験が、自らも被災し、社員や家族の安否を気遣いながらも、「地元新聞」の「伝える使命」をいかに果たすかと探り、手書き新聞がつくられていったかを語る、迫真のドキュメント。 
『河北新報のいちばん長い日 震災下の地元紙』河北新報社著 文藝春秋 2011.10 ISBN-13: 978-4163744704
河北とは、福島県の「白河以北」を意味し、「一山百文」と明治維新以降軽視された、その名をあえて題字とした独立心を表しているという。1897年創刊の東北を代表するブロック紙である。
被災後の午後4時オープンで、対策会議を開き、社員の安否確認、社の被災状況、そして、新聞の発行に全力を注ぐことの3つを確認した。被災しながら取材を続ける記者たちの苦悩、取材網や販売網が壊滅のさなか、印刷までの製作工程も分断されるが、新潟日報都の相互支援協定による号外をはじめとするその後の発行にこぎつける。被災した人々は河北新報がそのまま、救援物資のごとく力づけられたという。困難のさなか、発行し続けた地方新聞の使命と役割を教えてくれる。2012年3月、ドラマ化決定。2011年度新聞協会賞受賞。 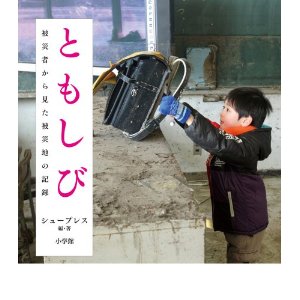
『ともしび』シュ―プレス編著 小学館 2011.8 ISBN-13: 978-4093882033
被災した人々の心をおたためてくれる「ともしび」のような「希望」。
被災した市民に寄り添い、声を聞き、思いを記事にまとめていった地元新聞、東奥日報、岩手日報、三陸新聞、石巻日日新聞、石巻かほく、河北新報、福島民友、いわき日報共同通信社の記事から、「命のともしび」「心のともしび」「勇気のともしび」「希望のともしび」という4章立てでエピソードを拾い、仙台の編集プロダクションが編集した。訪問入浴の最中だった介護士の避難を助けた後に命を落としたいわきの高校生の話、亡くなった弟のために青いこいのぼりを挙げる石巻の高校生の話など。手書き新聞や気仙沼の子どもたちのファイト新聞の記事もある。巻頭の口絵もよい。
「津波てんでんこ」を提唱してきた山下文男氏(87歳)は陸前高田の高田病院の4階で被災し、コメントを寄せている。(p58,59) 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://dl.ndl.go.jp/#newspaper ブックリスト
キーワード1 マスメディア キーワード2 新聞 キーワード3 放送 授業計画・指導案等 小5社会 情報を発信する放送局.tif 児童・生徒の作品 授業者 小倉勝登 授業者コメント 司書・司書教諭コメント 小倉学級の子どもたちのアンテナは高い。写真集やノンフィクションを入れるそばから反応して、借りていく。小学生新聞3紙(朝日小学生新聞、毎日小学生新聞、よみうりKODOMO新聞)、ニュース雑誌2誌(ニュースがわかる、朝日ジュニアアエラ)も購入している図書館環境を、担任も子どもたちもフル活用してくれているといっていい。ブックトークを作成中だが、これらのノンフィクションを組み入れた子たちも多くいる。
これは時事問題の教材化ということで、現地取材、インタビュー、さまざまな活動であつめた情報をもとに授業をデザインする小倉実践を、司書教諭科目を取っている学生にも話をしてもらった。「他人事」ではなく「自分ごと」として社会的事象をとらえてほしいという、教師の願いを実現する丹念な教材研究とそれを生かした授業デザインを学ばせてもらう好機となった。
朝日小学生新聞2012年1月27日1面「震災で変わる教科書」に小倉教諭のコメントが出ている。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2011.12.12. 事例作成者氏名 中山美由紀
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863376 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0084 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 社会 |
| 単元 | 情報を発信する放送局 |
| 対象学年 | 高学年 |
| 活用・支援の種類 | 資料収集、子どもへの広報 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 東日本大震災に関連した新聞を取り上げて報道の役割について授業を行った。東日本大震災時の報道に関する本をさらに購入してほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 東日本大震災時の報道、特に世界でも注目を集めた石巻日日新聞の手書き新聞を取り上げ、報道の役割や責任について考える授業を行っている。関連する本を、子どもの学習環境・読書環境として図書館で収集し、利用できるようにしてほしい。 |
| 提示資料 | |
 | 『6枚の壁新聞 石巻日日新聞・東日本大震災後7日間の記録 角川SSC新書 (角川SSC新書 130) 石巻日日新聞社編 角川マガジンズ(角川グループパブリッシング) 2011.7 ISBN-13: 978-4047315532 「今、伝えなければ、地域の新聞社なんか存在する意味がない」、創業99年の石巻日日新聞社が被災しながら発行した6枚の手書きの壁新聞。「伝える使命」を貫いた記者たちの行動は世界を感動させた。 「大津波警報」のアナウンスが出る前に取材に散っていった6人の記者たち。一晩漂流して救助された記者、渋滞の車から飛び出して走って山に逃げた記者、津波の濁流に課もまれた社屋に残る者…。それぞれの時間を追った体験が、自らも被災し、社員や家族の安否を気遣いながらも、「地元新聞」の「伝える使命」をいかに果たすかと探り、手書き新聞がつくられていったかを語る、迫真のドキュメント。 |
 | 『河北新報のいちばん長い日 震災下の地元紙』河北新報社著 文藝春秋 2011.10 ISBN-13: 978-4163744704 河北とは、福島県の「白河以北」を意味し、「一山百文」と明治維新以降軽視された、その名をあえて題字とした独立心を表しているという。1897年創刊の東北を代表するブロック紙である。 被災後の午後4時オープンで、対策会議を開き、社員の安否確認、社の被災状況、そして、新聞の発行に全力を注ぐことの3つを確認した。被災しながら取材を続ける記者たちの苦悩、取材網や販売網が壊滅のさなか、印刷までの製作工程も分断されるが、新潟日報都の相互支援協定による号外をはじめとするその後の発行にこぎつける。被災した人々は河北新報がそのまま、救援物資のごとく力づけられたという。困難のさなか、発行し続けた地方新聞の使命と役割を教えてくれる。2012年3月、ドラマ化決定。2011年度新聞協会賞受賞。 |
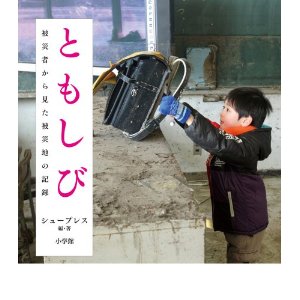 | 『ともしび』シュ―プレス編著 小学館 2011.8 ISBN-13: 978-4093882033 被災した人々の心をおたためてくれる「ともしび」のような「希望」。 被災した市民に寄り添い、声を聞き、思いを記事にまとめていった地元新聞、東奥日報、岩手日報、三陸新聞、石巻日日新聞、石巻かほく、河北新報、福島民友、いわき日報共同通信社の記事から、「命のともしび」「心のともしび」「勇気のともしび」「希望のともしび」という4章立てでエピソードを拾い、仙台の編集プロダクションが編集した。訪問入浴の最中だった介護士の避難を助けた後に命を落としたいわきの高校生の話、亡くなった弟のために青いこいのぼりを挙げる石巻の高校生の話など。手書き新聞や気仙沼の子どもたちのファイト新聞の記事もある。巻頭の口絵もよい。 「津波てんでんこ」を提唱してきた山下文男氏(87歳)は陸前高田の高田病院の4階で被災し、コメントを寄せている。(p58,59) |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http://dl.ndl.go.jp/#newspaper |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | マスメディア |
| キーワード2 | 新聞 |
| キーワード3 | 放送 |
| 授業計画・指導案等 | 小5社会 情報を発信する放送局.tif |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 小倉勝登 |
| 授業者コメント | |
| 司書・司書教諭コメント | 小倉学級の子どもたちのアンテナは高い。写真集やノンフィクションを入れるそばから反応して、借りていく。小学生新聞3紙(朝日小学生新聞、毎日小学生新聞、よみうりKODOMO新聞)、ニュース雑誌2誌(ニュースがわかる、朝日ジュニアアエラ)も購入している図書館環境を、担任も子どもたちもフル活用してくれているといっていい。ブックトークを作成中だが、これらのノンフィクションを組み入れた子たちも多くいる。 これは時事問題の教材化ということで、現地取材、インタビュー、さまざまな活動であつめた情報をもとに授業をデザインする小倉実践を、司書教諭科目を取っている学生にも話をしてもらった。「他人事」ではなく「自分ごと」として社会的事象をとらえてほしいという、教師の願いを実現する丹念な教材研究とそれを生かした授業デザインを学ばせてもらう好機となった。 朝日小学生新聞2012年1月27日1面「震災で変わる教科書」に小倉教諭のコメントが出ている。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |
| 事例作成日 | 2011.12.12. |
| 事例作成者氏名 | 中山美由紀 |
記入者:中山(主担)

























