今だから読んでほしい上橋作品『鹿の王』‼︎
2020-05-15 07:33 | by 村上 |
ブックトーク番外編
COVID-19 で休校が続くなか、今までのように本を手渡せない私たち司書は、ましてや生徒に直接ブックトークを行うこともままなりません。そこで、番外編として、自校の生徒向けに書いた記事を転載します。(今だから子どもたちにぜひ読んでほしい本『鹿の王』を中心に紹介しました。)
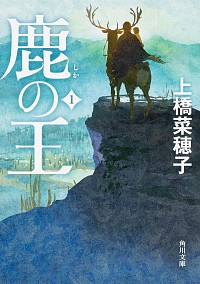 みなさんは、『鹿の王』(上橋菜穂子著 KADOKAWA)を読んだことがありますか?もし、まだであるなら、COVID-19という感染症が全世界に蔓延することを誰もが止めようとしている今だからこそ、ぜひ手にとってほしい物語です。なぜなら、2014年に出版されたこの本は、“黒狼熱(ミツツアル)”という未知の感染症に立ち向かう若き天才医師ホッサルと、かつて愛する妻と子を感染症によって失ったヴァンを中心に描かれ、まさにウィルスと人類がどう対峙するかを描いた作品だからです。
みなさんは、『鹿の王』(上橋菜穂子著 KADOKAWA)を読んだことがありますか?もし、まだであるなら、COVID-19という感染症が全世界に蔓延することを誰もが止めようとしている今だからこそ、ぜひ手にとってほしい物語です。なぜなら、2014年に出版されたこの本は、“黒狼熱(ミツツアル)”という未知の感染症に立ち向かう若き天才医師ホッサルと、かつて愛する妻と子を感染症によって失ったヴァンを中心に描かれ、まさにウィルスと人類がどう対峙するかを描いた作品だからです。
東乎瑠(ツオル)帝国にとらわれ、岩塩鉱で奴隷として働くヴァンを、ある日獰猛な黒犬が襲います。黒犬に噛まれた者たちが皆死に絶えるなか、ひとり生き残ったヴァンは、あらんかぎりの力を振り絞り足かせをはずし、同じく生き延びた幼な子を連れ、岩塩鉱を脱出します。
ヴァンが以前暮らしていたのは、アカファ帝国の辺境の地でした。勢力を拡大する東乎瑠帝国の前に、アカファ帝国は属州となることを選び、アカファの民たちは平民として生きることが許されました。しかしアカファの地で暮らしていた辺境の氏族たちに身の保証はありません。ガンサ氏族の長は、恭順ではなく抵抗する道を選びました。その先鋒となったのが、〈独角〉と呼ばれる戦士たちです。負け戦を承知で少しでも有利な協定を結ぶために戦う独角たちは、何らかの理由で生への執着を失い、死に場所を求めていた者たちの集団でした。そしてヴァンは独角の長だったのです。
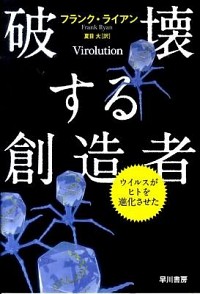 そのきっかけになったのが、『破壊する創造者;ウィルスがヒトを進化させた』(フランク・ライアン著 夏目大訳 ハヤカワ文庫 2014)という本だったと上橋さんは「あとがき」に書いています。副題にもあるように、著者はヒトの進化を、ウィルスの存在と紐付けます。細菌のように単体で増殖はできないウィルスは、必ず寄生するものが必要です。ウィルスはヒトにとって病をもたらす敵のように思われがちですが、ヒトが死んでしまえば、ウィルスも長らえることはできません。ウィルスとヒトとの関係は、実に複雑であり、ヒトを進化させてきたのも実はウィルスだと言うのです。この本を読んだ頃に、自身の体の不調や両親の老いを実感し、自分の体なのにその中で何が起きているかが見えないこと、その体が実は絶えず細菌やウィルスが日々共生したり葛藤する場であること、そしてそれは社会の有り様にとても似ていることに気づいたことが、『鹿の王』につながったというのです。確かに国をもたないオタワル人が、東乎瑠帝国で生きるしか道がないことは、単体では生きられないウィルスが生物に寄生することでしか生きられないことと酷似していることに気づかされます。
そのきっかけになったのが、『破壊する創造者;ウィルスがヒトを進化させた』(フランク・ライアン著 夏目大訳 ハヤカワ文庫 2014)という本だったと上橋さんは「あとがき」に書いています。副題にもあるように、著者はヒトの進化を、ウィルスの存在と紐付けます。細菌のように単体で増殖はできないウィルスは、必ず寄生するものが必要です。ウィルスはヒトにとって病をもたらす敵のように思われがちですが、ヒトが死んでしまえば、ウィルスも長らえることはできません。ウィルスとヒトとの関係は、実に複雑であり、ヒトを進化させてきたのも実はウィルスだと言うのです。この本を読んだ頃に、自身の体の不調や両親の老いを実感し、自分の体なのにその中で何が起きているかが見えないこと、その体が実は絶えず細菌やウィルスが日々共生したり葛藤する場であること、そしてそれは社会の有り様にとても似ていることに気づいたことが、『鹿の王』につながったというのです。確かに国をもたないオタワル人が、東乎瑠帝国で生きるしか道がないことは、単体では生きられないウィルスが生物に寄生することでしか生きられないことと酷似していることに気づかされます。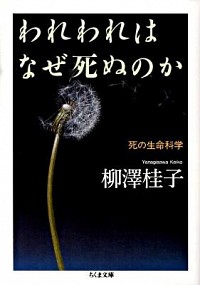 書き始めたものの、壮大なテーマだけに書き続けることの困難さに落ち込むこともあった上橋さんが、次に出会った本が、『われわれはなぜ死ぬのか;死の生命科学』(柳澤桂子著 ちくま書房)だったそうです。この本は、生命科学の視点から「死」を読み解いています。私たちヒトは、死を老いの延長上にあるものとして捉えがちですが、生物の世界では必ずしもそうではないそうです。たとえば、サケは川を遡上すると産卵し、あっという間に死んでいく。メタセコイアは老衰が確認されずに、個体の生命は数千年を超えるとも。死は生を支えるためにあるという新たな視点を得た上橋さんは、ついに物語を完成させます。
書き始めたものの、壮大なテーマだけに書き続けることの困難さに落ち込むこともあった上橋さんが、次に出会った本が、『われわれはなぜ死ぬのか;死の生命科学』(柳澤桂子著 ちくま書房)だったそうです。この本は、生命科学の視点から「死」を読み解いています。私たちヒトは、死を老いの延長上にあるものとして捉えがちですが、生物の世界では必ずしもそうではないそうです。たとえば、サケは川を遡上すると産卵し、あっという間に死んでいく。メタセコイアは老衰が確認されずに、個体の生命は数千年を超えるとも。死は生を支えるためにあるという新たな視点を得た上橋さんは、ついに物語を完成させます。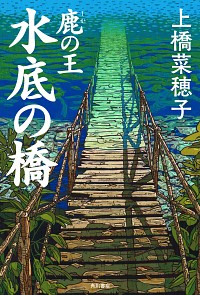 また3巻のあとがきは、西加奈子さんが、先輩作家、上橋菜穂子に魅了されているひとりとして、こんな言葉を書いています。「『鹿の王』はポタラ宮や森のような空間ではなく、寺社や教会に漂う歴史でもなく、一冊の書籍に過ぎないはずだ。ページをめくると「文字」と呼ばれている黒いぶつぶつが並び、色もなくにおいもなく音もなく、景色もない。なのにこれだけわたしの細胞を喚起する。色もにおいも音も景色もないのに、すべてがある。いいや、すべて以上がある。」
また3巻のあとがきは、西加奈子さんが、先輩作家、上橋菜穂子に魅了されているひとりとして、こんな言葉を書いています。「『鹿の王』はポタラ宮や森のような空間ではなく、寺社や教会に漂う歴史でもなく、一冊の書籍に過ぎないはずだ。ページをめくると「文字」と呼ばれている黒いぶつぶつが並び、色もなくにおいもなく音もなく、景色もない。なのにこれだけわたしの細胞を喚起する。色もにおいも音も景色もないのに、すべてがある。いいや、すべて以上がある。」