テーマ設定からレファレンスへつなぐには?
2019-03-14 12:50 | by 村上 |
 3学期は、昨年に引き続き、保健体育の授業で1年生が探究学習はじめの一歩として、「健康新聞」づくりに臨んだ。
3学期は、昨年に引き続き、保健体育の授業で1年生が探究学習はじめの一歩として、「健康新聞」づくりに臨んだ。今年は、昨年の先生とは違う先生が担当をしているが、昨年の様子を先生から伺い、学校司書にも相談をし、ほぼ同じようなタイムスケジュールで行うことになった。テーマ設定に3時間、新聞を書くのに1時間、グループ内発表を2回するために2時間、振り返りに1時間の計7時間。3学期の保健体育の授業は、毎回図書館で行うことになった。
新聞のテーマは、1、2学期に学んだこと=〈テーマ1〉と自分の関心のあること=〈テーマ2〉を結びつけて、できるだけ疑問形の形にするように言われる。テーマを見つける時にも、またテーマが決まってその答えを考えるにも、図書館の本は有効である。
とはいうものの、中学1年生にとって、必要な本を短時間で見つけるのは難しい。そこで、あらかじめ使えそうな本は、分類順に別置した。いよいよテーマが決まって本を探してほしいのだが、実は資料を探す時間は授業内ではあまりとれない。
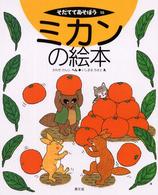 課題のために昼休みや放課後、図書館に資料相談にやってきた生徒には個別に対応する。たとえばテーマ2を大好きな「果物」にしたMさん、困った顔で、「どんな本使ったらいいのかな?」と聞いてきた。そこで、果物の本が並んでいる6類に案内して、農文協の『そだててあそぼう』シリーズを紹介。そこから『ミカンの絵本』(かわせけんじ へん いしまるちさと え 2003)を手に取る。次は料理の本がある5類の棚に案内。最後に栄養と健康に関する4類の棚に案内した。本を手に取り、新聞のイメージがつかめたらしく、3冊本を借りていった。
課題のために昼休みや放課後、図書館に資料相談にやってきた生徒には個別に対応する。たとえばテーマ2を大好きな「果物」にしたMさん、困った顔で、「どんな本使ったらいいのかな?」と聞いてきた。そこで、果物の本が並んでいる6類に案内して、農文協の『そだててあそぼう』シリーズを紹介。そこから『ミカンの絵本』(かわせけんじ へん いしまるちさと え 2003)を手に取る。次は料理の本がある5類の棚に案内。最後に栄養と健康に関する4類の棚に案内した。本を手に取り、新聞のイメージがつかめたらしく、3冊本を借りていった。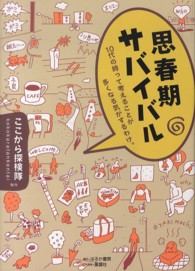 テーマ1が〈性への関心と行動・自己形成〉にして、テーマ2を〈思春期の恋ごころ〉にしたKくん、なかなか「ピンとくる本がないらしい。いろいろ紹介したが、『思春期サバイバル』(ここから探検隊編 はるか書房 2013)を手にして、書けそう!と帰って行った。
テーマ1が〈性への関心と行動・自己形成〉にして、テーマ2を〈思春期の恋ごころ〉にしたKくん、なかなか「ピンとくる本がないらしい。いろいろ紹介したが、『思春期サバイバル』(ここから探検隊編 はるか書房 2013)を手にして、書けそう!と帰って行った。同じく〈テーマ1〉が自己形成だったYくん、「自己形成に関する本はありますか?」と聞かれ、「自己形成って言葉は難しいけれど、たとえば、赤ちゃんがどんなふうに成長していくかが書いてある本は役に立たないかな?」と保育に関する本を示してみたら、『子どもの生活・遊びのせかい』(婦人の友社編集部編 婦人の友社 1996)と、『中学生になったら』(宮下聡著 岩波ジュニア新書 2017)を借りていった。テーマは決まったものの、必要な資料や進め方がぼんやりとしている場合、こうして本を見ながら司書とあれこれ話すことで、見えてくるものがあるのだと思う。しかし、このように授業時間外に図書館にやってきて、レファレンスを求める生徒はそれほど多くはない。
先生には、振り返りシートと、新聞は成績処理が終わったら見せてもらうことにしている。どんな本が使われたのか、このテーマならこの本が使えたのではないか…など来年に活かせるのではと思っている。司書に聞かなくても、自分で資料が探せることが理想だが、そもそも探せているのか、どのぐらい探そうとしたのかは、今のままでは司書はわからない。テーマ設定の次の段階、資料の探索についても、来年度は少し時間をもらって話ができるといいかなと思っている。
(附属世田谷中学校司書 村上恭子)