お知らせ
令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
新着案内
「今月の学校図書館」は 石川県白山市立北星中学校です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0228 校種 高校 教科・領域等 理科 単元 探究活動の進め方 対象学年 高1 活用・支援の種類 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 生物とヒトに関する社会問題について、疑問を持って調べてまとめる活動を行いたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 生物基礎の集大成として探究活動を行った。1,2学期で身につけた基礎・基本的な生物の知識をもとに、個別レポートの作成、班での発表を行いたい、と先生から依頼を受けた。
図書館からは、テーマについて発想を広げたり、問いを深めるようなワークシート(マンダラートや5W1Hマップなど)の提供を先生に行った。調べる段階では、生徒の幅広い興味関心に応えられるよう、テーマに合わせた資料の準備、新聞記事データベースやインターネット検索用のタブレットPCの準備、レファレンスを行った。
提示資料 雑誌や白書、『現代用語の基礎知識』など、情報の新しい資料がよく利用された。また、テーマを深めていく段階、資料を探す段階の初めには児童書がよく利用された。 
『現代用語の基礎知識2015』自由国民社 2014年
生徒の興味関心の中には時事的なものも多かった。これらの基礎的な言葉の定義、最近の動向を押さえておくことのできる資料はよく使われていた。 
「Newton」ニュートンプレス
上記と同様に、最近のことがわかるNewtonはよく使われた。各年12月号は記事索引があるので、関連記事を探すことができる。本校図書館では過去10年分のバックナンバーを保存している。 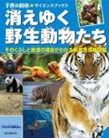
『消えゆく野生動物たち 子供の科学 サイエンスブックス』子供の科学編集部/編 誠文堂新光社 2014年
テーマについて調べ始める時に便利なのが児童書。この本は、振り仮名がついていて、図版も多いが、解説が詳しく索引もきちんとあり、高校生でも使いやすかった。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 生物探究活動 生徒配布プリント.pdf
キーワード1 探究 キーワード2 生物基礎 キーワード3 授業計画・指導案等 生物探究活動指導案.pdf 児童・生徒の作品 授業者 益田健 授業者コメント 図書館で探究活動を行っている生徒は、活発かつ熱心に取り組んでいた。このような、生徒が主体的に学び、自ら知識を獲得してみなで共有するよちうものが、本来の「学習」のあるべき形だと感じた。この学習方法を体験しておくことが、生徒の今後の成長につながる。
反省点としては、図書館を全5時間利用させていただいたが、あと2時間程度確保できれば、ゆとりを持った授業ができたと考える。学校の授業時間数の関係でできなかった。
司書の先生には、資料集めから指導方法まで幅広くご支援いただき、感謝しております。 司書・司書教諭コメント 探究的な学習を授業で行うのは高校では初めてとなる生徒たちだったので、資料の探し方などを時間をいただいて説明した。
レファレンスの利用も多く、多様な興味関心にこ応えるため狛江市立図書館から団体貸出で本をお借りした。
前年度に同じような授業を受けた生徒たちは、2年生になり他の授業の探究的な学習をそれまでよりスムーズに行っている。こういった経験を積み重ねていくことが大事なのだと思った。 情報提供校 都立狛江高等学校 事例作成日 事例作成日 2015年3月 授業実践日 2015年1月 事例作成者氏名 千田つばさ
記入者:千田
カウンタ
3146140 : 2010年9月14日より
令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「今月の学校図書館」は 石川県白山市立北星中学校です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0228 校種 高校 教科・領域等 理科 単元 探究活動の進め方 対象学年 高1 活用・支援の種類 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 生物とヒトに関する社会問題について、疑問を持って調べてまとめる活動を行いたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 生物基礎の集大成として探究活動を行った。1,2学期で身につけた基礎・基本的な生物の知識をもとに、個別レポートの作成、班での発表を行いたい、と先生から依頼を受けた。
図書館からは、テーマについて発想を広げたり、問いを深めるようなワークシート(マンダラートや5W1Hマップなど)の提供を先生に行った。調べる段階では、生徒の幅広い興味関心に応えられるよう、テーマに合わせた資料の準備、新聞記事データベースやインターネット検索用のタブレットPCの準備、レファレンスを行った。
提示資料 雑誌や白書、『現代用語の基礎知識』など、情報の新しい資料がよく利用された。また、テーマを深めていく段階、資料を探す段階の初めには児童書がよく利用された。 
『現代用語の基礎知識2015』自由国民社 2014年
生徒の興味関心の中には時事的なものも多かった。これらの基礎的な言葉の定義、最近の動向を押さえておくことのできる資料はよく使われていた。 
「Newton」ニュートンプレス
上記と同様に、最近のことがわかるNewtonはよく使われた。各年12月号は記事索引があるので、関連記事を探すことができる。本校図書館では過去10年分のバックナンバーを保存している。 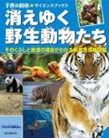
『消えゆく野生動物たち 子供の科学 サイエンスブックス』子供の科学編集部/編 誠文堂新光社 2014年
テーマについて調べ始める時に便利なのが児童書。この本は、振り仮名がついていて、図版も多いが、解説が詳しく索引もきちんとあり、高校生でも使いやすかった。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 生物探究活動 生徒配布プリント.pdf
キーワード1 探究 キーワード2 生物基礎 キーワード3 授業計画・指導案等 生物探究活動指導案.pdf 児童・生徒の作品 授業者 益田健 授業者コメント 図書館で探究活動を行っている生徒は、活発かつ熱心に取り組んでいた。このような、生徒が主体的に学び、自ら知識を獲得してみなで共有するよちうものが、本来の「学習」のあるべき形だと感じた。この学習方法を体験しておくことが、生徒の今後の成長につながる。
反省点としては、図書館を全5時間利用させていただいたが、あと2時間程度確保できれば、ゆとりを持った授業ができたと考える。学校の授業時間数の関係でできなかった。
司書の先生には、資料集めから指導方法まで幅広くご支援いただき、感謝しております。 司書・司書教諭コメント 探究的な学習を授業で行うのは高校では初めてとなる生徒たちだったので、資料の探し方などを時間をいただいて説明した。
レファレンスの利用も多く、多様な興味関心にこ応えるため狛江市立図書館から団体貸出で本をお借りした。
前年度に同じような授業を受けた生徒たちは、2年生になり他の授業の探究的な学習をそれまでよりスムーズに行っている。こういった経験を積み重ねていくことが大事なのだと思った。 情報提供校 都立狛江高等学校 事例作成日 事例作成日 2015年3月 授業実践日 2015年1月 事例作成者氏名 千田つばさ
記入者:千田
カウンタ
3146140 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0228 |
|---|---|
| 校種 | 高校 |
| 教科・領域等 | 理科 |
| 単元 | 探究活動の進め方 |
| 対象学年 | 高1 |
| 活用・支援の種類 | |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 生物とヒトに関する社会問題について、疑問を持って調べてまとめる活動を行いたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 生物基礎の集大成として探究活動を行った。1,2学期で身につけた基礎・基本的な生物の知識をもとに、個別レポートの作成、班での発表を行いたい、と先生から依頼を受けた。 図書館からは、テーマについて発想を広げたり、問いを深めるようなワークシート(マンダラートや5W1Hマップなど)の提供を先生に行った。調べる段階では、生徒の幅広い興味関心に応えられるよう、テーマに合わせた資料の準備、新聞記事データベースやインターネット検索用のタブレットPCの準備、レファレンスを行った。 |
| 提示資料 | 雑誌や白書、『現代用語の基礎知識』など、情報の新しい資料がよく利用された。また、テーマを深めていく段階、資料を探す段階の初めには児童書がよく利用された。 |
 | 『現代用語の基礎知識2015』自由国民社 2014年 生徒の興味関心の中には時事的なものも多かった。これらの基礎的な言葉の定義、最近の動向を押さえておくことのできる資料はよく使われていた。 |
 | 「Newton」ニュートンプレス 上記と同様に、最近のことがわかるNewtonはよく使われた。各年12月号は記事索引があるので、関連記事を探すことができる。本校図書館では過去10年分のバックナンバーを保存している。 |
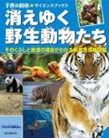 | 『消えゆく野生動物たち 子供の科学 サイエンスブックス』子供の科学編集部/編 誠文堂新光社 2014年 テーマについて調べ始める時に便利なのが児童書。この本は、振り仮名がついていて、図版も多いが、解説が詳しく索引もきちんとあり、高校生でも使いやすかった。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 生物探究活動 生徒配布プリント.pdf |
| キーワード1 | 探究 |
| キーワード2 | 生物基礎 |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | 生物探究活動指導案.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 益田健 |
| 授業者コメント | 図書館で探究活動を行っている生徒は、活発かつ熱心に取り組んでいた。このような、生徒が主体的に学び、自ら知識を獲得してみなで共有するよちうものが、本来の「学習」のあるべき形だと感じた。この学習方法を体験しておくことが、生徒の今後の成長につながる。 反省点としては、図書館を全5時間利用させていただいたが、あと2時間程度確保できれば、ゆとりを持った授業ができたと考える。学校の授業時間数の関係でできなかった。 司書の先生には、資料集めから指導方法まで幅広くご支援いただき、感謝しております。 |
| 司書・司書教諭コメント | 探究的な学習を授業で行うのは高校では初めてとなる生徒たちだったので、資料の探し方などを時間をいただいて説明した。 レファレンスの利用も多く、多様な興味関心にこ応えるため狛江市立図書館から団体貸出で本をお借りした。 前年度に同じような授業を受けた生徒たちは、2年生になり他の授業の探究的な学習をそれまでよりスムーズに行っている。こういった経験を積み重ねていくことが大事なのだと思った。 |
| 情報提供校 | 都立狛江高等学校 |
| 事例作成日 | 事例作成日 2015年3月 授業実践日 2015年1月 |
| 事例作成者氏名 | 千田つばさ |
記入者:千田

























