お知らせ
今年度も、「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vo.17」をオンラインで開催します。日程は12月13日(土)、13:00〜17:00です。プログラムはこちらです。 後日録画配信も予定しています。ぜひ事前に申し込みください。申し込みフォーム
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は東京都立八丈高等学校です。
「授業と学校図書館」は、「はじまりは1冊の本から:光太郎と智恵子の愛のカタチ」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0452 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 民主政治と日本の政治:日本の将来を考える 対象学年 中3 活用・支援の種類 資料提供・ブックリスト提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 「よりよい民主主義・民主政治のために改善すべき問題は何か?」についてパネルディスカッション方式で学習するので、図書資料を用意してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 全体で8時間の授業の3時間をリサーチ学習にあてたい。最初の1時間は図書と、「ジャパンナレッジスクール」のみ使用。後の2時間はネットも使って調べる。グループ学習を重視とのこと。
提示資料 パネルディスカッションに役立った3冊を選んでみました。 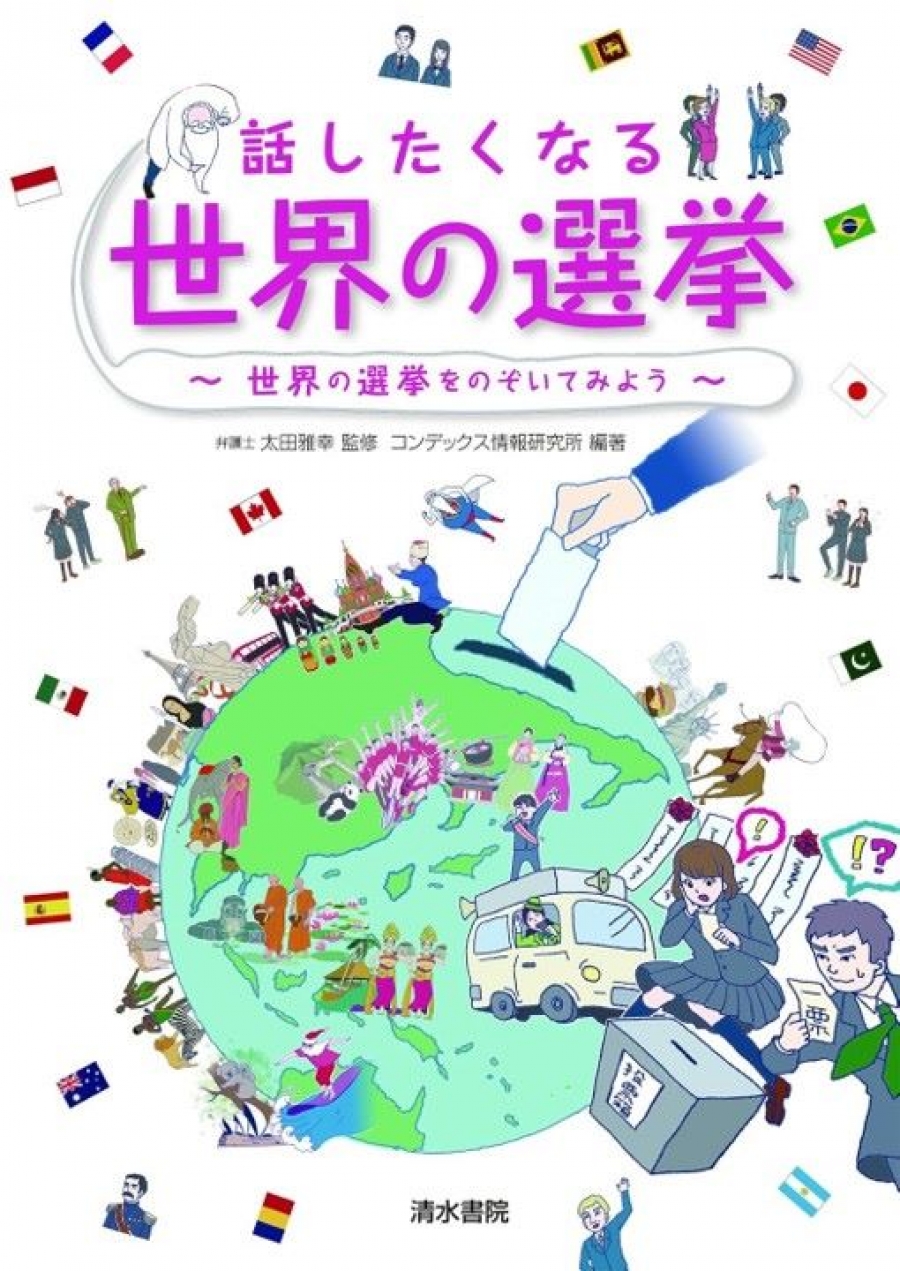
『話したくなる世界の選挙
~世界の選挙をのぞいてみよう~』
太田 雅幸/コンデックス情報研究所
清水書院 2016
ISBN 978-4-389-50051-1
今回生徒の関心が高かった課題が「選挙」だった。他の国ではどのような選挙制度なのかが、興味深く書かれた1冊。常に投票率が90%を超えているオーストラリアには、罰則規定が!低い投票率が続く日本の若者層への課題解決のヒントは? 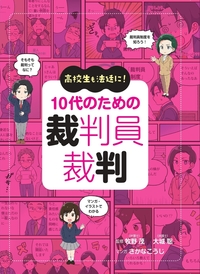
『高校生も法廷に! 10 代のための裁判員裁判』
牧野 茂 大城 聡 監修
さかなこうじ 絵
出版年月日 2023/08/29
ISBN 9784845118380
裁判員に選ばれた高校生ユウトが主人公。漫画とコラムで、裁判員制度が一から学べる。 
『政治分野におけるジェンダー平等の推進:フランスと日本の女性議員の実情と意識』
冨士谷あつ子(編著) 新川達郎(編著)
発行:明石書店 2024
ISBN978-4-7503-5800-0
中学生対象の本ではないので、公共図書館から借りた一冊。フランスは2000年に罰則規定を含むパリテ法を制定した。立候補者届け出には男女同数とし、違反する政党にペナルティを課した。ジェンダーギャップを縮めるフランスから日本は何を学べるのかを問う1冊 参考資料(含HP) 参考資料リンク https:// ブックリスト 76回生公民「よりよい日本の政治を目指して」関連資料ブックリスト(生徒配布用).xlsx
キーワード1 民主主義 キーワード2 政治 キーワード3 パネルディスカッション 授業計画・指導案等 公民日本の将来を考える.pdf 児童・生徒の作品 https:// 授業者 金城和秀 授業者コメント 一般的な政治単元の授業では、国会・内閣・裁判所・選挙・地方自治などを個別に仕組みやその課題などを学習すると思いますが、それぞれの課題は、「民主主義や民主政治の課題」ととらえることもできると思います。この授業では、マクロな視点で政治単元を捉え直し、よりよい社会の実現に向けて、民主主義や民主政治、国民主権や主権者としての在り方を考えることとしました。パネルディスカッション形式にして、それぞれの立場から主張や発表をしてもらい、その後それぞれのグループを解体して、それぞれのパネリストがいるような新たな班を作って振り返りを行いました。単元のまとめでは、民主主義や民主政治の発展についてミニレポートを書いてもらいました。「有権者になることが待ち遠しい」「両親や親せきに投票に行くように呼びかける」「一人の国民として自覚を持った」「民主主義として国民に主権がある以上、国民が主体的に国を動かす意識を持たなければ国家は腐っていってしまう」などの記述がみられました。恐らく、これらは座学による教師から生徒への一方通行の授業では、出てこなかった内容だと考えています。しかし、まだまだ改善の余地はあるので、これからも生徒の主権者意識が高められるような授業を実践していきたいと思います。 司書・司書教諭コメント 社会科の授業は、調べることがスタート地点であることが多い。今回も、6つのテーマで各グループがパネルディスカッションを行ったが、いずれもはたして日本が民主主義国家と言えるのかという問題をはらんでいる。用意した資料はいつもNDC順に並べて、自分達の課題を解決するためには、どの本が使えるのかは生徒に考えてもらっている。ピンポイントの情報を得るには、ネットの検索は便利だし時短にもなる。が、あえて、書籍を見ることで、書籍の特徴を理解したり、意識していなかった事柄に目が行くという利点がある。今回は信頼できる情報として、ジャパンナレッジスクールも1時間目は可とした。最終的に生徒がまとめた資料は、ネットからの情報が多かったがが、そこに行きつく手前で書籍が役立つのではないかと感じた。教室で行われたパネルディスカッションや、最終的にどの課題から解決すべきかなどの話し合いの様子も見学させてもらった。どのクラスも、3年後自分たちが当事者となる選挙への関心が最も高かったが、話し合いをしていたグループの生徒に「みんなは、18歳になったら選挙には行くの?」と尋ねると、「もちろん行きます!」と力強い返事が全員から返ってきた。彼らがそう思えるのは、やはりこのような授業を受けているからこそだと感じた。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2024.12.10 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3600644 : 2010年9月14日より
今年度も、「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vo.17」をオンラインで開催します。日程は12月13日(土)、13:00〜17:00です。プログラムはこちらです。 後日録画配信も予定しています。ぜひ事前に申し込みください。申し込みフォーム
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は東京都立八丈高等学校です。
「授業と学校図書館」は、「はじまりは1冊の本から:光太郎と智恵子の愛のカタチ」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0452 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 民主政治と日本の政治:日本の将来を考える 対象学年 中3 活用・支援の種類 資料提供・ブックリスト提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 「よりよい民主主義・民主政治のために改善すべき問題は何か?」についてパネルディスカッション方式で学習するので、図書資料を用意してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 全体で8時間の授業の3時間をリサーチ学習にあてたい。最初の1時間は図書と、「ジャパンナレッジスクール」のみ使用。後の2時間はネットも使って調べる。グループ学習を重視とのこと。
提示資料 パネルディスカッションに役立った3冊を選んでみました。 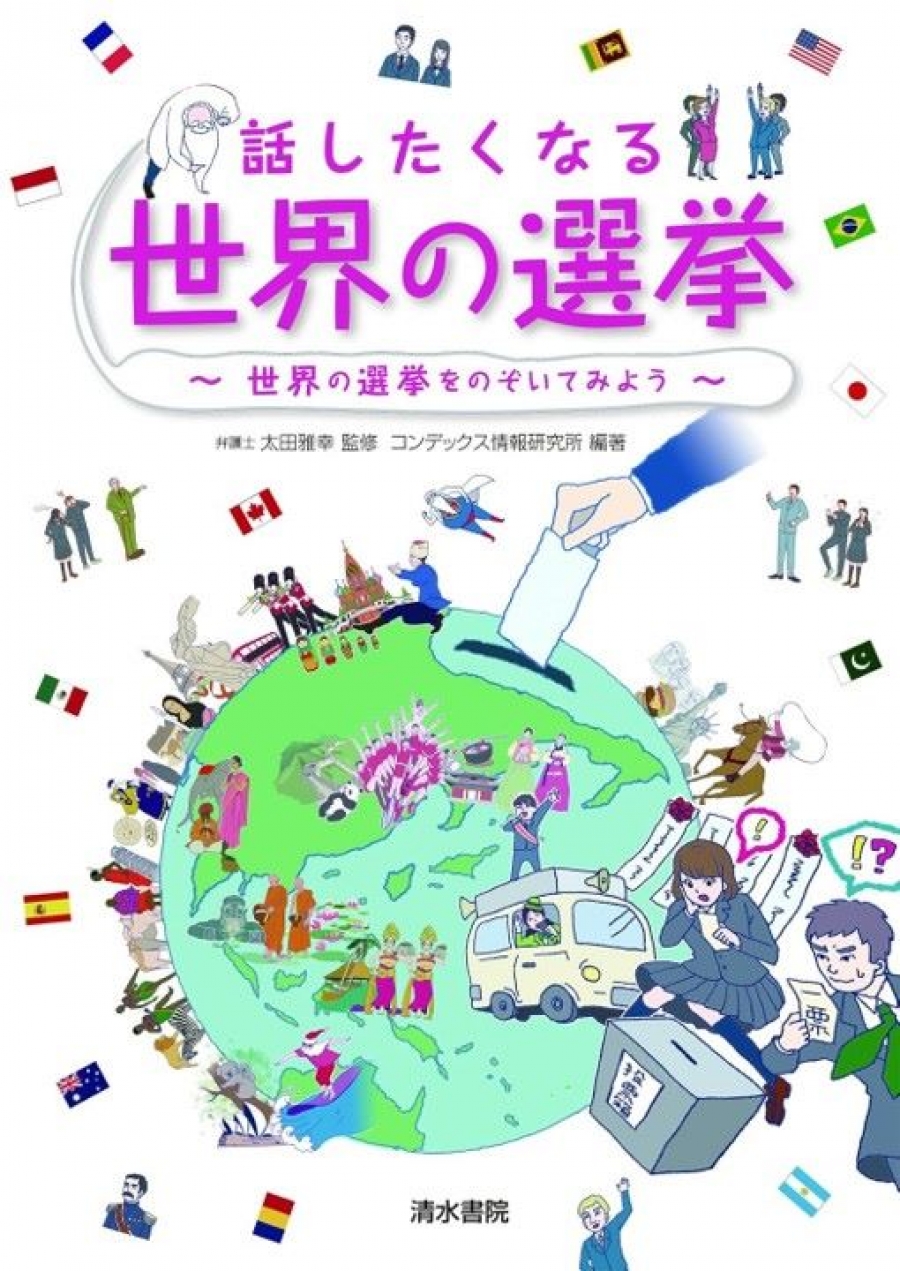
『話したくなる世界の選挙
~世界の選挙をのぞいてみよう~』
太田 雅幸/コンデックス情報研究所
清水書院 2016
ISBN 978-4-389-50051-1
今回生徒の関心が高かった課題が「選挙」だった。他の国ではどのような選挙制度なのかが、興味深く書かれた1冊。常に投票率が90%を超えているオーストラリアには、罰則規定が!低い投票率が続く日本の若者層への課題解決のヒントは? 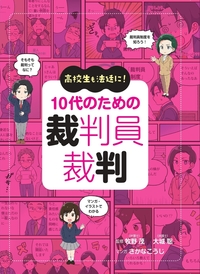
『高校生も法廷に! 10 代のための裁判員裁判』
牧野 茂 大城 聡 監修
さかなこうじ 絵
出版年月日 2023/08/29
ISBN 9784845118380
裁判員に選ばれた高校生ユウトが主人公。漫画とコラムで、裁判員制度が一から学べる。 
『政治分野におけるジェンダー平等の推進:フランスと日本の女性議員の実情と意識』
冨士谷あつ子(編著) 新川達郎(編著)
発行:明石書店 2024
ISBN978-4-7503-5800-0
中学生対象の本ではないので、公共図書館から借りた一冊。フランスは2000年に罰則規定を含むパリテ法を制定した。立候補者届け出には男女同数とし、違反する政党にペナルティを課した。ジェンダーギャップを縮めるフランスから日本は何を学べるのかを問う1冊 参考資料(含HP) 参考資料リンク https:// ブックリスト 76回生公民「よりよい日本の政治を目指して」関連資料ブックリスト(生徒配布用).xlsx
キーワード1 民主主義 キーワード2 政治 キーワード3 パネルディスカッション 授業計画・指導案等 公民日本の将来を考える.pdf 児童・生徒の作品 https:// 授業者 金城和秀 授業者コメント 一般的な政治単元の授業では、国会・内閣・裁判所・選挙・地方自治などを個別に仕組みやその課題などを学習すると思いますが、それぞれの課題は、「民主主義や民主政治の課題」ととらえることもできると思います。この授業では、マクロな視点で政治単元を捉え直し、よりよい社会の実現に向けて、民主主義や民主政治、国民主権や主権者としての在り方を考えることとしました。パネルディスカッション形式にして、それぞれの立場から主張や発表をしてもらい、その後それぞれのグループを解体して、それぞれのパネリストがいるような新たな班を作って振り返りを行いました。単元のまとめでは、民主主義や民主政治の発展についてミニレポートを書いてもらいました。「有権者になることが待ち遠しい」「両親や親せきに投票に行くように呼びかける」「一人の国民として自覚を持った」「民主主義として国民に主権がある以上、国民が主体的に国を動かす意識を持たなければ国家は腐っていってしまう」などの記述がみられました。恐らく、これらは座学による教師から生徒への一方通行の授業では、出てこなかった内容だと考えています。しかし、まだまだ改善の余地はあるので、これからも生徒の主権者意識が高められるような授業を実践していきたいと思います。 司書・司書教諭コメント 社会科の授業は、調べることがスタート地点であることが多い。今回も、6つのテーマで各グループがパネルディスカッションを行ったが、いずれもはたして日本が民主主義国家と言えるのかという問題をはらんでいる。用意した資料はいつもNDC順に並べて、自分達の課題を解決するためには、どの本が使えるのかは生徒に考えてもらっている。ピンポイントの情報を得るには、ネットの検索は便利だし時短にもなる。が、あえて、書籍を見ることで、書籍の特徴を理解したり、意識していなかった事柄に目が行くという利点がある。今回は信頼できる情報として、ジャパンナレッジスクールも1時間目は可とした。最終的に生徒がまとめた資料は、ネットからの情報が多かったがが、そこに行きつく手前で書籍が役立つのではないかと感じた。教室で行われたパネルディスカッションや、最終的にどの課題から解決すべきかなどの話し合いの様子も見学させてもらった。どのクラスも、3年後自分たちが当事者となる選挙への関心が最も高かったが、話し合いをしていたグループの生徒に「みんなは、18歳になったら選挙には行くの?」と尋ねると、「もちろん行きます!」と力強い返事が全員から返ってきた。彼らがそう思えるのは、やはりこのような授業を受けているからこそだと感じた。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2024.12.10 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3600644 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0452 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 社会 |
| 単元 | 民主政治と日本の政治:日本の将来を考える |
| 対象学年 | 中3 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供・ブックリスト提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 「よりよい民主主義・民主政治のために改善すべき問題は何か?」についてパネルディスカッション方式で学習するので、図書資料を用意してほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 全体で8時間の授業の3時間をリサーチ学習にあてたい。最初の1時間は図書と、「ジャパンナレッジスクール」のみ使用。後の2時間はネットも使って調べる。グループ学習を重視とのこと。 |
| 提示資料 | パネルディスカッションに役立った3冊を選んでみました。 |
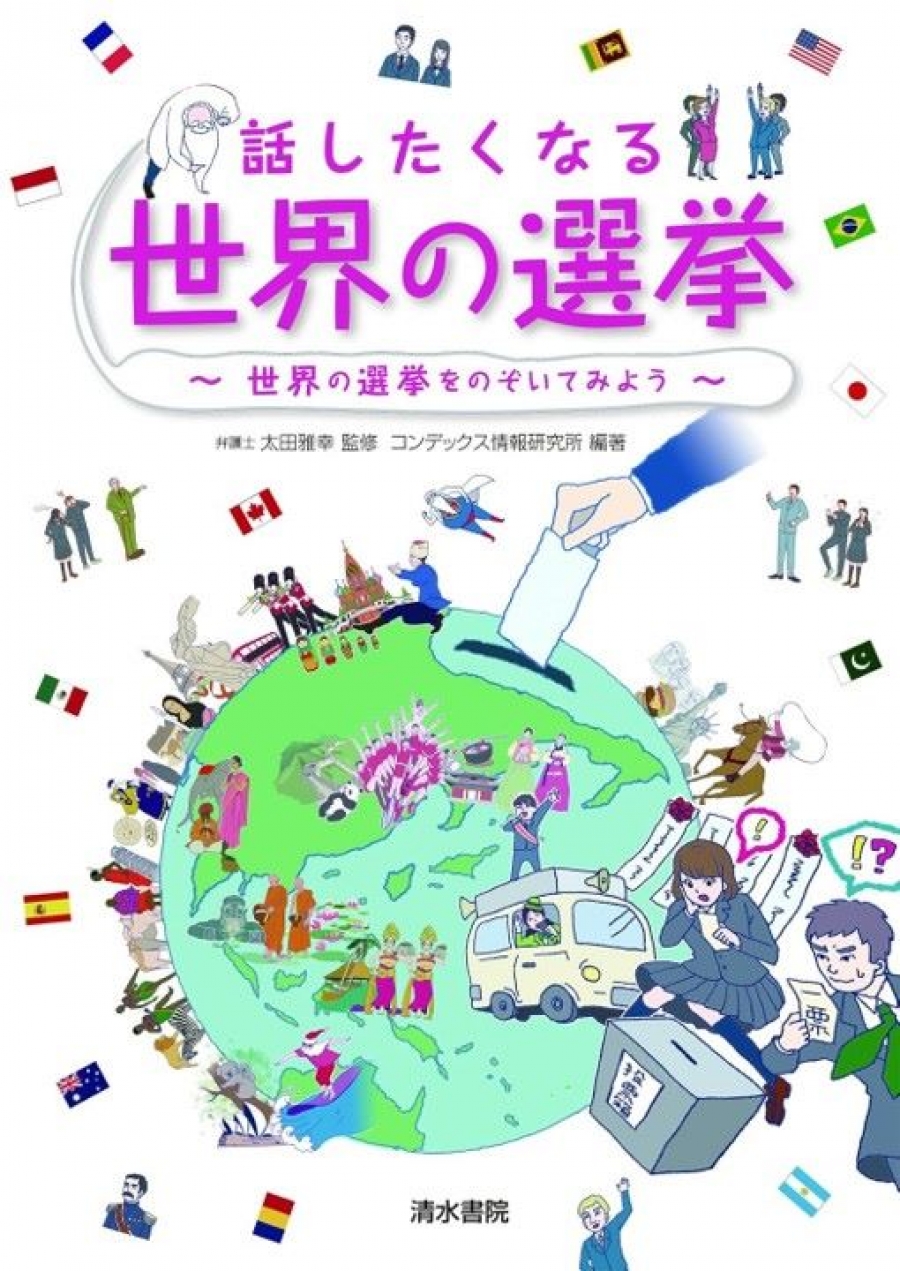 | 『話したくなる世界の選挙 ~世界の選挙をのぞいてみよう~』 太田 雅幸/コンデックス情報研究所 清水書院 2016 ISBN 978-4-389-50051-1 今回生徒の関心が高かった課題が「選挙」だった。他の国ではどのような選挙制度なのかが、興味深く書かれた1冊。常に投票率が90%を超えているオーストラリアには、罰則規定が!低い投票率が続く日本の若者層への課題解決のヒントは? |
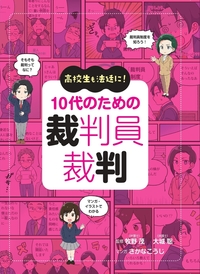 | 『高校生も法廷に! 10 代のための裁判員裁判』 牧野 茂 大城 聡 監修 さかなこうじ 絵 出版年月日 2023/08/29 ISBN 9784845118380 裁判員に選ばれた高校生ユウトが主人公。漫画とコラムで、裁判員制度が一から学べる。 |
 | 『政治分野におけるジェンダー平等の推進:フランスと日本の女性議員の実情と意識』 冨士谷あつ子(編著) 新川達郎(編著) 発行:明石書店 2024 ISBN978-4-7503-5800-0 中学生対象の本ではないので、公共図書館から借りた一冊。フランスは2000年に罰則規定を含むパリテ法を制定した。立候補者届け出には男女同数とし、違反する政党にペナルティを課した。ジェンダーギャップを縮めるフランスから日本は何を学べるのかを問う1冊 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | https:// |
| ブックリスト | 76回生公民「よりよい日本の政治を目指して」関連資料ブックリスト(生徒配布用).xlsx |
| キーワード1 | 民主主義 |
| キーワード2 | 政治 |
| キーワード3 | パネルディスカッション |
| 授業計画・指導案等 | 公民日本の将来を考える.pdf |
| 児童・生徒の作品 | https:// |
| 授業者 | 金城和秀 |
| 授業者コメント | 一般的な政治単元の授業では、国会・内閣・裁判所・選挙・地方自治などを個別に仕組みやその課題などを学習すると思いますが、それぞれの課題は、「民主主義や民主政治の課題」ととらえることもできると思います。この授業では、マクロな視点で政治単元を捉え直し、よりよい社会の実現に向けて、民主主義や民主政治、国民主権や主権者としての在り方を考えることとしました。パネルディスカッション形式にして、それぞれの立場から主張や発表をしてもらい、その後それぞれのグループを解体して、それぞれのパネリストがいるような新たな班を作って振り返りを行いました。単元のまとめでは、民主主義や民主政治の発展についてミニレポートを書いてもらいました。「有権者になることが待ち遠しい」「両親や親せきに投票に行くように呼びかける」「一人の国民として自覚を持った」「民主主義として国民に主権がある以上、国民が主体的に国を動かす意識を持たなければ国家は腐っていってしまう」などの記述がみられました。恐らく、これらは座学による教師から生徒への一方通行の授業では、出てこなかった内容だと考えています。しかし、まだまだ改善の余地はあるので、これからも生徒の主権者意識が高められるような授業を実践していきたいと思います。 |
| 司書・司書教諭コメント | 社会科の授業は、調べることがスタート地点であることが多い。今回も、6つのテーマで各グループがパネルディスカッションを行ったが、いずれもはたして日本が民主主義国家と言えるのかという問題をはらんでいる。用意した資料はいつもNDC順に並べて、自分達の課題を解決するためには、どの本が使えるのかは生徒に考えてもらっている。ピンポイントの情報を得るには、ネットの検索は便利だし時短にもなる。が、あえて、書籍を見ることで、書籍の特徴を理解したり、意識していなかった事柄に目が行くという利点がある。今回は信頼できる情報として、ジャパンナレッジスクールも1時間目は可とした。最終的に生徒がまとめた資料は、ネットからの情報が多かったがが、そこに行きつく手前で書籍が役立つのではないかと感じた。教室で行われたパネルディスカッションや、最終的にどの課題から解決すべきかなどの話し合いの様子も見学させてもらった。どのクラスも、3年後自分たちが当事者となる選挙への関心が最も高かったが、話し合いをしていたグループの生徒に「みんなは、18歳になったら選挙には行くの?」と尋ねると、「もちろん行きます!」と力強い返事が全員から返ってきた。彼らがそう思えるのは、やはりこのような授業を受けているからこそだと感じた。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
| 事例作成日 | 2024.12.10 |
| 事例作成者氏名 | 村上恭子 |
記入者:村上

























