お知らせ
今年度も、「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vo.17」をオンラインで開催します。日程は12月13日(土)、13:00〜17:00です。プログラムはこちらです。 後日録画配信も予定しています。ぜひ事前に申し込みください。申し込みフォーム
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は東京都立八丈高等学校です。
「授業と学校図書館」は、「はじまりは1冊の本から:光太郎と智恵子の愛のカタチ」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0470 校種 中学校 教科・領域等 外国語 単元 Sports for Everyone(他) 対象学年 中3 活用・支援の種類 資料提供 ブックトーク 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 教材のテーマや単元のゴールに興味関心をもったり深く考えたりできるような資料がほしい。
・各単元で扱っているストーリーの背景やその文化について考えるきっかけとなるような資料がほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ブックトークや資料を通して子供たちの身近な生活と単元の内容とのつながりを考えられるようにしたい。単元に関わることから子供達が新しいこと(文化や知識、生活など)に知り、図書館での活動の後、各自が考えを深められるような資料を紹介してほしい。
提示資料 いくつかの単元で紹介した本の中から3冊をピックアップしています。 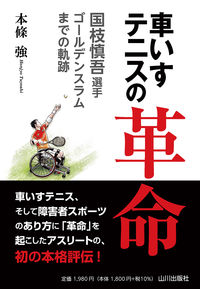
『車いすテニスの革命』本條強著 山川出版社 2023
パラスポーツのブックトークで紹介した本。国枝慎吾さんのことを取り上げた1冊で、ちょうど時期的に、3年生の部活動最後の大会が近いこともあり、紹介したら意欲的に聞いていた。この他にも「障害者ってだれのこと?」荒井裕樹(平凡社)、「わたしが障害者なくなる日」海老原宏美(旬報社)、「転んでも大丈夫 ぼくが義足を作る理由」臼井二美男(ポプラ社)など、障害のことや支える人についての本も紹介した。 
『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』庭田杏珠著 光文社 2020
マザーズララバイ」という広島の原爆を取り上げたUnitで紹介した本。戦争写真はモノクロのものがほとんどで、遠い昔のことのように感じがちなものが多いが、カラーになることで、とても身近に感じられるようになる1冊。エノラゲイや広島の様子がカラー写真で蘇っていて、とても惹きつけられていた。他にも様々な本を紹介した。 
『990円のジーンズがつくられるのはなぜ?』長田華子著 合同出版 2016
「Beyond Borders」というUnitでブックトークをした1冊。教科書では、日本のランドセルが海外に渡っていることを取り上げているが、ただ不要になったものを送れば、国際協力になるのか?自分の身近な生活から世界を考えてほしいと思い、ブックトークの1冊として選んだ。国際理解や国際協力は上記の障害者や戦争と同じく、自分の身近なこととして、いかに考えられるかが大切だと思うので、ブックトークでも、自分の普段の買い物はどうか、ということを本の内容とともに投げかけながら紹介をした。
参考資料(含HP) 参考資料リンク https://app.bookreach.org/curation?id=112 ブックリスト みんなのためのスポーツ ブックリスト.xlsx
キーワード1 パラスポーツ キーワード2 戦争と平和 キーワード3 国際理解 授業計画・指導案等 図書館を活用した英語科の授業実践.pdf 児童・生徒の作品 https:// 授業者 白山市立北星中学校 英語教諭 小松 美歩 授業者コメント それぞれのUnitの導入や終末で各テーマについて、ブックトークや資料提供をしていただいている。ブックトークや様々な資料を紹介してもらえることで、単元の内容やゴールに興味・関心を持つきっかけになっていると思う。ストーリー(Unit)を読んで終わりではなく、そこからその背景や文化を考えるきっかけになってほしい、授業で学んだことがより広い知識や世界とつながってほしいと期待して続けている。
実際に、ブックトークを入れた前後では、自分の意見を伝えたり書いたりする時に、自分の立場(考え・思い)を支えてくれる根拠や理由を示せるようになることも多い。ブックトークや資料の本を通して、互いの考えを話し合えることで、子どもたちの世界が広がっているように感じる。繰り返し続けていくと、英作文の内容が変わっていくこともあった。
司書・司書教諭コメント 授業者のコメントにあるように、各Unitを読んで終わりではなく、そこを起点に考えたり、もっと知りたいと思ってほしいと思い、イメージとして、自分の世界が広がっていくようなブックトークを心がけた。ブックトークだけでなく、内容に合った各分野の公式HPで紹介されている動画も視聴し、本と動画の両面から、自分と社会や世界を考えるヒントになる内容にした。動画はJICAの緒方貞子さんを取り上げたものや、ユニセフ、国連の動画を使用した。授業後の生徒の感想を読んでも、自分ができること、どうしていったらよいかということを真剣に考えている姿が見られた。現教科書にはないが、「Sports for Everyone」では、実際のパラスポーツのもの(ブラインドサッカーボール、ゴールボール)や、そこで使用する競技用のアイマスクも準備して、触ってみたり、アイマスクを付けて図書館内を歩行もしてみた。本・動画・体験を取り入れて行うことで、学んだことがより身近に感じられ、深く考えられたのではないかと思う。 情報提供校 石川県白山市立北星中学校 事例作成日 事例作成2025年7月1日 /授業実践2024年5月・9月・11月 事例作成者氏名 学校司書 平田奈美
記入者:村上
カウンタ
3599879 : 2010年9月14日より
今年度も、「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vo.17」をオンラインで開催します。日程は12月13日(土)、13:00〜17:00です。プログラムはこちらです。 後日録画配信も予定しています。ぜひ事前に申し込みください。申し込みフォーム
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は東京都立八丈高等学校です。
「授業と学校図書館」は、「はじまりは1冊の本から:光太郎と智恵子の愛のカタチ」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0470 校種 中学校 教科・領域等 外国語 単元 Sports for Everyone(他) 対象学年 中3 活用・支援の種類 資料提供 ブックトーク 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 教材のテーマや単元のゴールに興味関心をもったり深く考えたりできるような資料がほしい。
・各単元で扱っているストーリーの背景やその文化について考えるきっかけとなるような資料がほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ブックトークや資料を通して子供たちの身近な生活と単元の内容とのつながりを考えられるようにしたい。単元に関わることから子供達が新しいこと(文化や知識、生活など)に知り、図書館での活動の後、各自が考えを深められるような資料を紹介してほしい。
提示資料 いくつかの単元で紹介した本の中から3冊をピックアップしています。 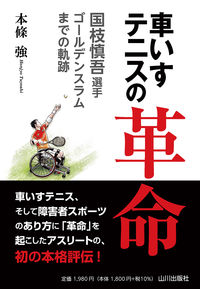
『車いすテニスの革命』本條強著 山川出版社 2023
パラスポーツのブックトークで紹介した本。国枝慎吾さんのことを取り上げた1冊で、ちょうど時期的に、3年生の部活動最後の大会が近いこともあり、紹介したら意欲的に聞いていた。この他にも「障害者ってだれのこと?」荒井裕樹(平凡社)、「わたしが障害者なくなる日」海老原宏美(旬報社)、「転んでも大丈夫 ぼくが義足を作る理由」臼井二美男(ポプラ社)など、障害のことや支える人についての本も紹介した。 
『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』庭田杏珠著 光文社 2020
マザーズララバイ」という広島の原爆を取り上げたUnitで紹介した本。戦争写真はモノクロのものがほとんどで、遠い昔のことのように感じがちなものが多いが、カラーになることで、とても身近に感じられるようになる1冊。エノラゲイや広島の様子がカラー写真で蘇っていて、とても惹きつけられていた。他にも様々な本を紹介した。 
『990円のジーンズがつくられるのはなぜ?』長田華子著 合同出版 2016
「Beyond Borders」というUnitでブックトークをした1冊。教科書では、日本のランドセルが海外に渡っていることを取り上げているが、ただ不要になったものを送れば、国際協力になるのか?自分の身近な生活から世界を考えてほしいと思い、ブックトークの1冊として選んだ。国際理解や国際協力は上記の障害者や戦争と同じく、自分の身近なこととして、いかに考えられるかが大切だと思うので、ブックトークでも、自分の普段の買い物はどうか、ということを本の内容とともに投げかけながら紹介をした。
参考資料(含HP) 参考資料リンク https://app.bookreach.org/curation?id=112 ブックリスト みんなのためのスポーツ ブックリスト.xlsx
キーワード1 パラスポーツ キーワード2 戦争と平和 キーワード3 国際理解 授業計画・指導案等 図書館を活用した英語科の授業実践.pdf 児童・生徒の作品 https:// 授業者 白山市立北星中学校 英語教諭 小松 美歩 授業者コメント それぞれのUnitの導入や終末で各テーマについて、ブックトークや資料提供をしていただいている。ブックトークや様々な資料を紹介してもらえることで、単元の内容やゴールに興味・関心を持つきっかけになっていると思う。ストーリー(Unit)を読んで終わりではなく、そこからその背景や文化を考えるきっかけになってほしい、授業で学んだことがより広い知識や世界とつながってほしいと期待して続けている。
実際に、ブックトークを入れた前後では、自分の意見を伝えたり書いたりする時に、自分の立場(考え・思い)を支えてくれる根拠や理由を示せるようになることも多い。ブックトークや資料の本を通して、互いの考えを話し合えることで、子どもたちの世界が広がっているように感じる。繰り返し続けていくと、英作文の内容が変わっていくこともあった。
司書・司書教諭コメント 授業者のコメントにあるように、各Unitを読んで終わりではなく、そこを起点に考えたり、もっと知りたいと思ってほしいと思い、イメージとして、自分の世界が広がっていくようなブックトークを心がけた。ブックトークだけでなく、内容に合った各分野の公式HPで紹介されている動画も視聴し、本と動画の両面から、自分と社会や世界を考えるヒントになる内容にした。動画はJICAの緒方貞子さんを取り上げたものや、ユニセフ、国連の動画を使用した。授業後の生徒の感想を読んでも、自分ができること、どうしていったらよいかということを真剣に考えている姿が見られた。現教科書にはないが、「Sports for Everyone」では、実際のパラスポーツのもの(ブラインドサッカーボール、ゴールボール)や、そこで使用する競技用のアイマスクも準備して、触ってみたり、アイマスクを付けて図書館内を歩行もしてみた。本・動画・体験を取り入れて行うことで、学んだことがより身近に感じられ、深く考えられたのではないかと思う。 情報提供校 石川県白山市立北星中学校 事例作成日 事例作成2025年7月1日 /授業実践2024年5月・9月・11月 事例作成者氏名 学校司書 平田奈美
記入者:村上
カウンタ
3599879 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0470 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 外国語 |
| 単元 | Sports for Everyone(他) |
| 対象学年 | 中3 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 ブックトーク |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 教材のテーマや単元のゴールに興味関心をもったり深く考えたりできるような資料がほしい。 ・各単元で扱っているストーリーの背景やその文化について考えるきっかけとなるような資料がほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | ブックトークや資料を通して子供たちの身近な生活と単元の内容とのつながりを考えられるようにしたい。単元に関わることから子供達が新しいこと(文化や知識、生活など)に知り、図書館での活動の後、各自が考えを深められるような資料を紹介してほしい。 |
| 提示資料 | いくつかの単元で紹介した本の中から3冊をピックアップしています。 |
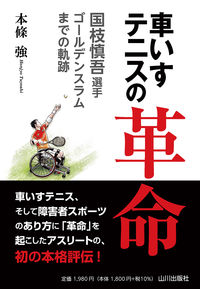 | 『車いすテニスの革命』本條強著 山川出版社 2023 パラスポーツのブックトークで紹介した本。国枝慎吾さんのことを取り上げた1冊で、ちょうど時期的に、3年生の部活動最後の大会が近いこともあり、紹介したら意欲的に聞いていた。この他にも「障害者ってだれのこと?」荒井裕樹(平凡社)、「わたしが障害者なくなる日」海老原宏美(旬報社)、「転んでも大丈夫 ぼくが義足を作る理由」臼井二美男(ポプラ社)など、障害のことや支える人についての本も紹介した。 |
 | 『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』庭田杏珠著 光文社 2020 マザーズララバイ」という広島の原爆を取り上げたUnitで紹介した本。戦争写真はモノクロのものがほとんどで、遠い昔のことのように感じがちなものが多いが、カラーになることで、とても身近に感じられるようになる1冊。エノラゲイや広島の様子がカラー写真で蘇っていて、とても惹きつけられていた。他にも様々な本を紹介した。 |
 | 『990円のジーンズがつくられるのはなぜ?』長田華子著 合同出版 2016 「Beyond Borders」というUnitでブックトークをした1冊。教科書では、日本のランドセルが海外に渡っていることを取り上げているが、ただ不要になったものを送れば、国際協力になるのか?自分の身近な生活から世界を考えてほしいと思い、ブックトークの1冊として選んだ。国際理解や国際協力は上記の障害者や戦争と同じく、自分の身近なこととして、いかに考えられるかが大切だと思うので、ブックトークでも、自分の普段の買い物はどうか、ということを本の内容とともに投げかけながら紹介をした。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | https://app.bookreach.org/curation?id=112 |
| ブックリスト | みんなのためのスポーツ ブックリスト.xlsx |
| キーワード1 | パラスポーツ |
| キーワード2 | 戦争と平和 |
| キーワード3 | 国際理解 |
| 授業計画・指導案等 | 図書館を活用した英語科の授業実践.pdf |
| 児童・生徒の作品 | https:// |
| 授業者 | 白山市立北星中学校 英語教諭 小松 美歩 |
| 授業者コメント | それぞれのUnitの導入や終末で各テーマについて、ブックトークや資料提供をしていただいている。ブックトークや様々な資料を紹介してもらえることで、単元の内容やゴールに興味・関心を持つきっかけになっていると思う。ストーリー(Unit)を読んで終わりではなく、そこからその背景や文化を考えるきっかけになってほしい、授業で学んだことがより広い知識や世界とつながってほしいと期待して続けている。 実際に、ブックトークを入れた前後では、自分の意見を伝えたり書いたりする時に、自分の立場(考え・思い)を支えてくれる根拠や理由を示せるようになることも多い。ブックトークや資料の本を通して、互いの考えを話し合えることで、子どもたちの世界が広がっているように感じる。繰り返し続けていくと、英作文の内容が変わっていくこともあった。 |
| 司書・司書教諭コメント | 授業者のコメントにあるように、各Unitを読んで終わりではなく、そこを起点に考えたり、もっと知りたいと思ってほしいと思い、イメージとして、自分の世界が広がっていくようなブックトークを心がけた。ブックトークだけでなく、内容に合った各分野の公式HPで紹介されている動画も視聴し、本と動画の両面から、自分と社会や世界を考えるヒントになる内容にした。動画はJICAの緒方貞子さんを取り上げたものや、ユニセフ、国連の動画を使用した。授業後の生徒の感想を読んでも、自分ができること、どうしていったらよいかということを真剣に考えている姿が見られた。現教科書にはないが、「Sports for Everyone」では、実際のパラスポーツのもの(ブラインドサッカーボール、ゴールボール)や、そこで使用する競技用のアイマスクも準備して、触ってみたり、アイマスクを付けて図書館内を歩行もしてみた。本・動画・体験を取り入れて行うことで、学んだことがより身近に感じられ、深く考えられたのではないかと思う。 |
| 情報提供校 | 石川県白山市立北星中学校 |
| 事例作成日 | 事例作成2025年7月1日 /授業実践2024年5月・9月・11月 |
| 事例作成者氏名 | 学校司書 平田奈美 |
記入者:村上

























