お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0136 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 世界地理の調べ学習 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供・ブックリスト・ワークシート作成・振り返りシートのまとめ 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 世界の国々について調べ学習をさせたい。
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 個人の興味・関心のあるテーマを考え、それを地理的な視点でとらえなおして自分のテーマを設定する。そのうえで必要な資料を探し、それらをまとめて、発表するという一連の流れのなかで、調べるスキルや発表するスキルを育てたい。
提示資料 様々な資料が使われた授業だったが、以下に挙げる資料は、「お好み焼き☆スペシャル☆」というテーマで調べた生徒の作品からの3冊を紹介。 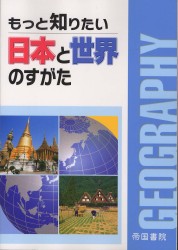
もっと知りたい 日本と世界のすがた(2012) 帝国書院 2012 帝国書院から出ているだけに、写真や図版も多く、きちんとしたデータが掲載されてしかも安価!調べ学習に役立つ1冊。 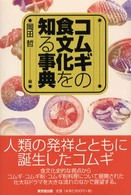
『コムギの食文化を知る事典』 岡田哲著 東京堂出版 2001
私たちにとってはあまりに身近すぎて普段考えないコムギの歴史や、その特徴、世界各地でどのように食べられているかなど、広範囲な視点からまとめられた事典。コムギ粉を使ったお菓子についても調べることができる。 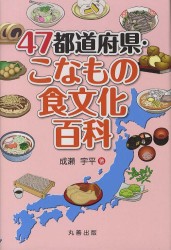
『47都道府県・こなもの食文化百科』成瀬宇平著 丸善出版 2012 日本の郷土料理的な視点で作られた本だが、コムギについての基本的な事項もあり、地方によって違うお好み焼きについての記述もある。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://okonomiyaki.sblo.jp/article/45089840.html ブックリスト 1年地理資料.xls
キーワード1 調べ学習 キーワード2 世界地理 キーワード3 お好み焼き 授業計画・指導案等 地理調べ学習資料.pdf 児童・生徒の作品 授業者 深澤貴宏 授業者コメント 子どもたちが、好きな事、好きなものを地理な見方・考え方で捉えなおすことによって、好きなことをより好きになり、それについて語れるようになることを目指した。やはり、多く生徒が「地理になるのかな?」と頭を抱えながらの調べ学習となったが、ウェビングマップ、教科書、仮テーマを頼りに探して頂いた図書資料を頼りに知識を増やし、問題意識となるテーマを絞っていった。
紹介した生徒の作品「お好み焼き☆スペシャル」は、特に好きな食べ物である「お好み焼き」を題材に、「なぜ類似料理ができたのか?」という具体的な課題を設定してまとめている。お好み焼きの起源の「麩の焼き」から「穀物」「ソース」「野菜」を使った料理と類似料理を絞り、世界各国の料理を調べていった。そして、小麦やトウモロコシ等の穀物と土地環境の関連を表や図で可視化し、様々な類似料理がある地域の気候環境による共通性と多様性をまとめることができた。また、発表では、「似た料理!何か知っているものはありますか?」と発問し、タコスやピザなどの写真を提示しながら、他生徒を引き込んでいく構成であり、改めて気候環境と食べ物の関連を強く認識できるものとなった。
今回、子どもの好きな事からスタートした調べ学習であった分、多くの支援が必要であった。好きなアニメから少年兵をテーマにした生徒もいた。また、図書館司書の先生には仮テーマの段階で、それに近い図書を探して頂いたり、生徒のテーマ設定や進行状況の把握に関わり、多くの支援をしていただいた。単なる好きな事調べで終始しないように、まずは好きなことに関わる様々な資料を読み込むことで知識を広げ、テーマ設定と地理の発表を見据えたストーリーを考える事で知識を深めるという過程が大切だと感じた。
司書・司書教諭コメント 調べ学習を始める前の段階から、先生といろいろ相談ができたのは良かったことだと感じた。調べる段階から、発表までの一連の過程を一緒に見ることで、こちらも勉強になった。今回はグループ活動ではなく、自分が興味・関心のあるテーマを見つけ、それを地理的なことに結びつけて発表するということにしたが、結びつけるのに苦労をし、先生と相談する姿が多く見られた。それでも、自分のテーマなので、与えられたテーマではない分、意欲的に調べる生徒も多かったように思う。また、グループ内での最初の発表は、調べたことを伝えるためには、どのような工夫が必要かを気づくいい機会になった。最後に友達から選ばれた4人が、クラス全員の前で発表をした。また提出したレポートは、クラス毎にファイルに入れて図書館に展示をした。調べ学習振り返りシートを見せてもらい、図書館として必要な項目をデータ化してみたので、今後の調べ学習に活かしたいと思う。
情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2013.3.15 事例作成者氏名 村上恭子(学校司書)
記入者:村上
カウンタ
3863375 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0136 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 世界地理の調べ学習 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供・ブックリスト・ワークシート作成・振り返りシートのまとめ 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 世界の国々について調べ学習をさせたい。
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 個人の興味・関心のあるテーマを考え、それを地理的な視点でとらえなおして自分のテーマを設定する。そのうえで必要な資料を探し、それらをまとめて、発表するという一連の流れのなかで、調べるスキルや発表するスキルを育てたい。
提示資料 様々な資料が使われた授業だったが、以下に挙げる資料は、「お好み焼き☆スペシャル☆」というテーマで調べた生徒の作品からの3冊を紹介。 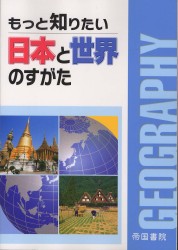
もっと知りたい 日本と世界のすがた(2012) 帝国書院 2012 帝国書院から出ているだけに、写真や図版も多く、きちんとしたデータが掲載されてしかも安価!調べ学習に役立つ1冊。 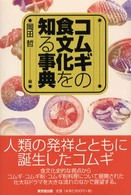
『コムギの食文化を知る事典』 岡田哲著 東京堂出版 2001
私たちにとってはあまりに身近すぎて普段考えないコムギの歴史や、その特徴、世界各地でどのように食べられているかなど、広範囲な視点からまとめられた事典。コムギ粉を使ったお菓子についても調べることができる。 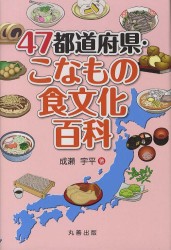
『47都道府県・こなもの食文化百科』成瀬宇平著 丸善出版 2012 日本の郷土料理的な視点で作られた本だが、コムギについての基本的な事項もあり、地方によって違うお好み焼きについての記述もある。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://okonomiyaki.sblo.jp/article/45089840.html ブックリスト 1年地理資料.xls
キーワード1 調べ学習 キーワード2 世界地理 キーワード3 お好み焼き 授業計画・指導案等 地理調べ学習資料.pdf 児童・生徒の作品 授業者 深澤貴宏 授業者コメント 子どもたちが、好きな事、好きなものを地理な見方・考え方で捉えなおすことによって、好きなことをより好きになり、それについて語れるようになることを目指した。やはり、多く生徒が「地理になるのかな?」と頭を抱えながらの調べ学習となったが、ウェビングマップ、教科書、仮テーマを頼りに探して頂いた図書資料を頼りに知識を増やし、問題意識となるテーマを絞っていった。
紹介した生徒の作品「お好み焼き☆スペシャル」は、特に好きな食べ物である「お好み焼き」を題材に、「なぜ類似料理ができたのか?」という具体的な課題を設定してまとめている。お好み焼きの起源の「麩の焼き」から「穀物」「ソース」「野菜」を使った料理と類似料理を絞り、世界各国の料理を調べていった。そして、小麦やトウモロコシ等の穀物と土地環境の関連を表や図で可視化し、様々な類似料理がある地域の気候環境による共通性と多様性をまとめることができた。また、発表では、「似た料理!何か知っているものはありますか?」と発問し、タコスやピザなどの写真を提示しながら、他生徒を引き込んでいく構成であり、改めて気候環境と食べ物の関連を強く認識できるものとなった。
今回、子どもの好きな事からスタートした調べ学習であった分、多くの支援が必要であった。好きなアニメから少年兵をテーマにした生徒もいた。また、図書館司書の先生には仮テーマの段階で、それに近い図書を探して頂いたり、生徒のテーマ設定や進行状況の把握に関わり、多くの支援をしていただいた。単なる好きな事調べで終始しないように、まずは好きなことに関わる様々な資料を読み込むことで知識を広げ、テーマ設定と地理の発表を見据えたストーリーを考える事で知識を深めるという過程が大切だと感じた。
司書・司書教諭コメント 調べ学習を始める前の段階から、先生といろいろ相談ができたのは良かったことだと感じた。調べる段階から、発表までの一連の過程を一緒に見ることで、こちらも勉強になった。今回はグループ活動ではなく、自分が興味・関心のあるテーマを見つけ、それを地理的なことに結びつけて発表するということにしたが、結びつけるのに苦労をし、先生と相談する姿が多く見られた。それでも、自分のテーマなので、与えられたテーマではない分、意欲的に調べる生徒も多かったように思う。また、グループ内での最初の発表は、調べたことを伝えるためには、どのような工夫が必要かを気づくいい機会になった。最後に友達から選ばれた4人が、クラス全員の前で発表をした。また提出したレポートは、クラス毎にファイルに入れて図書館に展示をした。調べ学習振り返りシートを見せてもらい、図書館として必要な項目をデータ化してみたので、今後の調べ学習に活かしたいと思う。
情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2013.3.15 事例作成者氏名 村上恭子(学校司書)
記入者:村上
カウンタ
3863375 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0136 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 社会 |
| 単元 | 世界地理の調べ学習 |
| 対象学年 | 中1 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供・ブックリスト・ワークシート作成・振り返りシートのまとめ |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 世界の国々について調べ学習をさせたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 個人の興味・関心のあるテーマを考え、それを地理的な視点でとらえなおして自分のテーマを設定する。そのうえで必要な資料を探し、それらをまとめて、発表するという一連の流れのなかで、調べるスキルや発表するスキルを育てたい。 |
| 提示資料 | 様々な資料が使われた授業だったが、以下に挙げる資料は、「お好み焼き☆スペシャル☆」というテーマで調べた生徒の作品からの3冊を紹介。 |
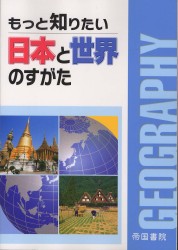 | もっと知りたい 日本と世界のすがた(2012) 帝国書院 2012 帝国書院から出ているだけに、写真や図版も多く、きちんとしたデータが掲載されてしかも安価!調べ学習に役立つ1冊。 |
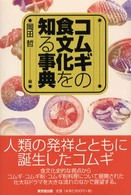 | 『コムギの食文化を知る事典』 岡田哲著 東京堂出版 2001 私たちにとってはあまりに身近すぎて普段考えないコムギの歴史や、その特徴、世界各地でどのように食べられているかなど、広範囲な視点からまとめられた事典。コムギ粉を使ったお菓子についても調べることができる。 |
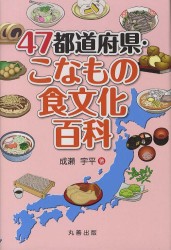 | 『47都道府県・こなもの食文化百科』成瀬宇平著 丸善出版 2012 日本の郷土料理的な視点で作られた本だが、コムギについての基本的な事項もあり、地方によって違うお好み焼きについての記述もある。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http://okonomiyaki.sblo.jp/article/45089840.html |
| ブックリスト | 1年地理資料.xls |
| キーワード1 | 調べ学習 |
| キーワード2 | 世界地理 |
| キーワード3 | お好み焼き |
| 授業計画・指導案等 | 地理調べ学習資料.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 深澤貴宏 |
| 授業者コメント | 子どもたちが、好きな事、好きなものを地理な見方・考え方で捉えなおすことによって、好きなことをより好きになり、それについて語れるようになることを目指した。やはり、多く生徒が「地理になるのかな?」と頭を抱えながらの調べ学習となったが、ウェビングマップ、教科書、仮テーマを頼りに探して頂いた図書資料を頼りに知識を増やし、問題意識となるテーマを絞っていった。 紹介した生徒の作品「お好み焼き☆スペシャル」は、特に好きな食べ物である「お好み焼き」を題材に、「なぜ類似料理ができたのか?」という具体的な課題を設定してまとめている。お好み焼きの起源の「麩の焼き」から「穀物」「ソース」「野菜」を使った料理と類似料理を絞り、世界各国の料理を調べていった。そして、小麦やトウモロコシ等の穀物と土地環境の関連を表や図で可視化し、様々な類似料理がある地域の気候環境による共通性と多様性をまとめることができた。また、発表では、「似た料理!何か知っているものはありますか?」と発問し、タコスやピザなどの写真を提示しながら、他生徒を引き込んでいく構成であり、改めて気候環境と食べ物の関連を強く認識できるものとなった。 今回、子どもの好きな事からスタートした調べ学習であった分、多くの支援が必要であった。好きなアニメから少年兵をテーマにした生徒もいた。また、図書館司書の先生には仮テーマの段階で、それに近い図書を探して頂いたり、生徒のテーマ設定や進行状況の把握に関わり、多くの支援をしていただいた。単なる好きな事調べで終始しないように、まずは好きなことに関わる様々な資料を読み込むことで知識を広げ、テーマ設定と地理の発表を見据えたストーリーを考える事で知識を深めるという過程が大切だと感じた。 |
| 司書・司書教諭コメント | 調べ学習を始める前の段階から、先生といろいろ相談ができたのは良かったことだと感じた。調べる段階から、発表までの一連の過程を一緒に見ることで、こちらも勉強になった。今回はグループ活動ではなく、自分が興味・関心のあるテーマを見つけ、それを地理的なことに結びつけて発表するということにしたが、結びつけるのに苦労をし、先生と相談する姿が多く見られた。それでも、自分のテーマなので、与えられたテーマではない分、意欲的に調べる生徒も多かったように思う。また、グループ内での最初の発表は、調べたことを伝えるためには、どのような工夫が必要かを気づくいい機会になった。最後に友達から選ばれた4人が、クラス全員の前で発表をした。また提出したレポートは、クラス毎にファイルに入れて図書館に展示をした。調べ学習振り返りシートを見せてもらい、図書館として必要な項目をデータ化してみたので、今後の調べ学習に活かしたいと思う。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
| 事例作成日 | 2013.3.15 |
| 事例作成者氏名 | 村上恭子(学校司書) |
記入者:村上

























