お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0163 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 読むとはどういう営みか(字のない絵本から考える) 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 絵本『たまご』(ガブリエル・バンサン著)の現物を生徒に提供しながら授業を展開したい
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 絵本は生徒2人に1冊となるよう、同一の絵本(1クラス41人なので21冊)を用意したい。資料の借り出し日、返却計画を立てるために、授業期間・資料の使用期間を確認した。
提示資料 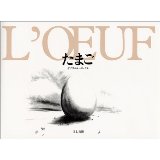
『たまご』ガブリエル・バンサン著 BL出版 1986年
ボローニャ国際児童図書展グラフィック賞、産経児童出版文化賞美術賞受賞。
「たまご」はガブリエル・バンサンによって描かれた、文字のない絵本です。大きな卵、それに反応する人間たち、そして突如やってきた大きな鳥が描かれていますが、この絵本をどんな物語として読み取るのかは読者に委ねられています。今回の授業では、読解行為を考えるためのケーススタディとしてこの絵本を使いました。それは、上記のようなこの絵本の特徴自体が生徒の関心を惹くだろうと予想されたことと、単語の意味調べなどにとらわれることがないので、普通の小説よりもかえって絵にも文字の本にも共通する「テクストを読む」という行為の意味を考えやすくなると思ったからです。


参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 絵本 キーワード2 読解 キーワード3 メタ認知 授業計画・指導案等 「たまご」資料.pdf 児童・生徒の作品 授業者 澤田英輔 授業者コメント 「読む」という行為がどういう行為なのか、自分たちで何らかのテキストを読解しつつ、その行為を振り返ることから考え、さらにそこから読みの適切な方略を考える授業の教材として、ガブリエル・バンサンの文字のない絵本『たまご』を使いました。「面白いし、深い」と言う生徒はけっこういましたし、解釈については、想像通り「自然と人間についての寓話」として読み取る生徒が多くいました。しかし、授業としては読み取りそれ自体よりも、「なぜ自分たちはそう読み取るのか、読むという行為はどういうことが」をメインにしました。
木炭のタッチが繊細な絵本なので、ぜひ実物の絵本を使って授業をしたいと思い、司書に依頼して、20冊以上を公共図書館などから借りて集めてもらいました。『たまご』という絵本自体に生徒を惹き付ける魅力があるのはもちろんですが、実際の絵本を使うことで、生徒の関心も非常に高まり、積極的に授業に取り組んでくれたと思います。
同じ絵本を20冊、しかも一定期間にわたって借り出してもらうこととなり、さらに休講などもあって予定より貸出期間が延びてしまったのですが、そういった点も司書がフォローしてくれ、非常に心強く、司書がいることのありがたみを感じました。
授業自体の手応えも一定以上感じられ、授業としての改善点もはっきりしたため、来年度以降もまた司書の助力を借りて、この教材に取り組んでみたいと思いました。 司書・司書教諭コメント 授業の趣旨から、絵本現物の重要性を理解しました。
所在地の世田谷区図書館においては団体登録できたものの、世田谷区には目的の資料「たまご」が所蔵1冊のため、他区からの取寄せなどに、世田谷区図書館にて協力を得られないかあたってみましたが、できませんでした。他の区においては学校所在地が別であるため、団体登録できませんでした。そこで、近接区の所蔵状況を調べ、司書2名であることの強みを生かし、手分けして、各館をまわって借り出し作業を行いました。
個人貸出では、同一タイトルの本を複数予約できないため、ひとつの館でその区で所蔵している複数冊を借り出すことができず、結果、本の所蔵館すべてをまわって借りることとしました。
今回の試みで、下記のようなことがあきらかになりました。
・教員の授業成果より、現物資料以外では代替の効かない授業と学びがある。
・公立学校を支える窓口として所在地の公立図書館サービスは、区によって異なり、かつ、国立附属学校図書館はそのサービス対象としてではなく、一団体(サークル等含む)としてみなされる。
・授業計画の授業構成を考えると、貸出⇒返却には一定の貸出期間を必要とする。今回は一度の延長貸出によりぎりぎりなんとかクリアできたが、もう少しゆとりある期間が欲しかった。
以上、公立図書館の学校図書館支援の状況を知ったり、区・都に属さない国立大学附属校として受けられる支援を知る機会としても有効でした。今後、所在地の公立図書館と関係性を深め、具体的に協力、支援を求めたい内容が明確になりました。
また、ごく一部の成果ではありますが、国立大学附属学校図書館のネットワークへ呼びかけたことで、1冊を提供いただくことができました。それら、独自のネットワークや体制づくりも同時に進めることで、いっそう豊かな授業に資する学校図書館の役割を果たしていけると感じました。 情報提供校 筑波大学附属駒場中学校 事例作成日 2013年10月(全7回、50分授業) 事例作成者氏名 筑波大学附属駒場中学校・高等学校教諭 澤田英輔 司書 加藤志保
記入者:井谷
カウンタ
3863523 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0163 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 読むとはどういう営みか(字のない絵本から考える) 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 絵本『たまご』(ガブリエル・バンサン著)の現物を生徒に提供しながら授業を展開したい
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 絵本は生徒2人に1冊となるよう、同一の絵本(1クラス41人なので21冊)を用意したい。資料の借り出し日、返却計画を立てるために、授業期間・資料の使用期間を確認した。
提示資料 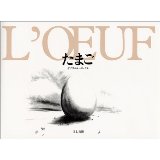
『たまご』ガブリエル・バンサン著 BL出版 1986年
ボローニャ国際児童図書展グラフィック賞、産経児童出版文化賞美術賞受賞。
「たまご」はガブリエル・バンサンによって描かれた、文字のない絵本です。大きな卵、それに反応する人間たち、そして突如やってきた大きな鳥が描かれていますが、この絵本をどんな物語として読み取るのかは読者に委ねられています。今回の授業では、読解行為を考えるためのケーススタディとしてこの絵本を使いました。それは、上記のようなこの絵本の特徴自体が生徒の関心を惹くだろうと予想されたことと、単語の意味調べなどにとらわれることがないので、普通の小説よりもかえって絵にも文字の本にも共通する「テクストを読む」という行為の意味を考えやすくなると思ったからです。


参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 絵本 キーワード2 読解 キーワード3 メタ認知 授業計画・指導案等 「たまご」資料.pdf 児童・生徒の作品 授業者 澤田英輔 授業者コメント 「読む」という行為がどういう行為なのか、自分たちで何らかのテキストを読解しつつ、その行為を振り返ることから考え、さらにそこから読みの適切な方略を考える授業の教材として、ガブリエル・バンサンの文字のない絵本『たまご』を使いました。「面白いし、深い」と言う生徒はけっこういましたし、解釈については、想像通り「自然と人間についての寓話」として読み取る生徒が多くいました。しかし、授業としては読み取りそれ自体よりも、「なぜ自分たちはそう読み取るのか、読むという行為はどういうことが」をメインにしました。
木炭のタッチが繊細な絵本なので、ぜひ実物の絵本を使って授業をしたいと思い、司書に依頼して、20冊以上を公共図書館などから借りて集めてもらいました。『たまご』という絵本自体に生徒を惹き付ける魅力があるのはもちろんですが、実際の絵本を使うことで、生徒の関心も非常に高まり、積極的に授業に取り組んでくれたと思います。
同じ絵本を20冊、しかも一定期間にわたって借り出してもらうこととなり、さらに休講などもあって予定より貸出期間が延びてしまったのですが、そういった点も司書がフォローしてくれ、非常に心強く、司書がいることのありがたみを感じました。
授業自体の手応えも一定以上感じられ、授業としての改善点もはっきりしたため、来年度以降もまた司書の助力を借りて、この教材に取り組んでみたいと思いました。 司書・司書教諭コメント 授業の趣旨から、絵本現物の重要性を理解しました。
所在地の世田谷区図書館においては団体登録できたものの、世田谷区には目的の資料「たまご」が所蔵1冊のため、他区からの取寄せなどに、世田谷区図書館にて協力を得られないかあたってみましたが、できませんでした。他の区においては学校所在地が別であるため、団体登録できませんでした。そこで、近接区の所蔵状況を調べ、司書2名であることの強みを生かし、手分けして、各館をまわって借り出し作業を行いました。
個人貸出では、同一タイトルの本を複数予約できないため、ひとつの館でその区で所蔵している複数冊を借り出すことができず、結果、本の所蔵館すべてをまわって借りることとしました。
今回の試みで、下記のようなことがあきらかになりました。
・教員の授業成果より、現物資料以外では代替の効かない授業と学びがある。
・公立学校を支える窓口として所在地の公立図書館サービスは、区によって異なり、かつ、国立附属学校図書館はそのサービス対象としてではなく、一団体(サークル等含む)としてみなされる。
・授業計画の授業構成を考えると、貸出⇒返却には一定の貸出期間を必要とする。今回は一度の延長貸出によりぎりぎりなんとかクリアできたが、もう少しゆとりある期間が欲しかった。
以上、公立図書館の学校図書館支援の状況を知ったり、区・都に属さない国立大学附属校として受けられる支援を知る機会としても有効でした。今後、所在地の公立図書館と関係性を深め、具体的に協力、支援を求めたい内容が明確になりました。
また、ごく一部の成果ではありますが、国立大学附属学校図書館のネットワークへ呼びかけたことで、1冊を提供いただくことができました。それら、独自のネットワークや体制づくりも同時に進めることで、いっそう豊かな授業に資する学校図書館の役割を果たしていけると感じました。 情報提供校 筑波大学附属駒場中学校 事例作成日 2013年10月(全7回、50分授業) 事例作成者氏名 筑波大学附属駒場中学校・高等学校教諭 澤田英輔 司書 加藤志保
記入者:井谷
カウンタ
3863523 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0163 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 読むとはどういう営みか(字のない絵本から考える) |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 絵本『たまご』(ガブリエル・バンサン著)の現物を生徒に提供しながら授業を展開したい |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 絵本は生徒2人に1冊となるよう、同一の絵本(1クラス41人なので21冊)を用意したい。資料の借り出し日、返却計画を立てるために、授業期間・資料の使用期間を確認した。 |
| 提示資料 | |
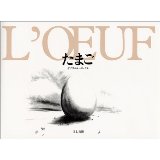 | 『たまご』ガブリエル・バンサン著 BL出版 1986年 ボローニャ国際児童図書展グラフィック賞、産経児童出版文化賞美術賞受賞。 「たまご」はガブリエル・バンサンによって描かれた、文字のない絵本です。大きな卵、それに反応する人間たち、そして突如やってきた大きな鳥が描かれていますが、この絵本をどんな物語として読み取るのかは読者に委ねられています。今回の授業では、読解行為を考えるためのケーススタディとしてこの絵本を使いました。それは、上記のようなこの絵本の特徴自体が生徒の関心を惹くだろうと予想されたことと、単語の意味調べなどにとらわれることがないので、普通の小説よりもかえって絵にも文字の本にも共通する「テクストを読む」という行為の意味を考えやすくなると思ったからです。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 絵本 |
| キーワード2 | 読解 |
| キーワード3 | メタ認知 |
| 授業計画・指導案等 | 「たまご」資料.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 澤田英輔 |
| 授業者コメント | 「読む」という行為がどういう行為なのか、自分たちで何らかのテキストを読解しつつ、その行為を振り返ることから考え、さらにそこから読みの適切な方略を考える授業の教材として、ガブリエル・バンサンの文字のない絵本『たまご』を使いました。「面白いし、深い」と言う生徒はけっこういましたし、解釈については、想像通り「自然と人間についての寓話」として読み取る生徒が多くいました。しかし、授業としては読み取りそれ自体よりも、「なぜ自分たちはそう読み取るのか、読むという行為はどういうことが」をメインにしました。 木炭のタッチが繊細な絵本なので、ぜひ実物の絵本を使って授業をしたいと思い、司書に依頼して、20冊以上を公共図書館などから借りて集めてもらいました。『たまご』という絵本自体に生徒を惹き付ける魅力があるのはもちろんですが、実際の絵本を使うことで、生徒の関心も非常に高まり、積極的に授業に取り組んでくれたと思います。 同じ絵本を20冊、しかも一定期間にわたって借り出してもらうこととなり、さらに休講などもあって予定より貸出期間が延びてしまったのですが、そういった点も司書がフォローしてくれ、非常に心強く、司書がいることのありがたみを感じました。 授業自体の手応えも一定以上感じられ、授業としての改善点もはっきりしたため、来年度以降もまた司書の助力を借りて、この教材に取り組んでみたいと思いました。 |
| 司書・司書教諭コメント | 授業の趣旨から、絵本現物の重要性を理解しました。 所在地の世田谷区図書館においては団体登録できたものの、世田谷区には目的の資料「たまご」が所蔵1冊のため、他区からの取寄せなどに、世田谷区図書館にて協力を得られないかあたってみましたが、できませんでした。他の区においては学校所在地が別であるため、団体登録できませんでした。そこで、近接区の所蔵状況を調べ、司書2名であることの強みを生かし、手分けして、各館をまわって借り出し作業を行いました。 個人貸出では、同一タイトルの本を複数予約できないため、ひとつの館でその区で所蔵している複数冊を借り出すことができず、結果、本の所蔵館すべてをまわって借りることとしました。 今回の試みで、下記のようなことがあきらかになりました。 ・教員の授業成果より、現物資料以外では代替の効かない授業と学びがある。 ・公立学校を支える窓口として所在地の公立図書館サービスは、区によって異なり、かつ、国立附属学校図書館はそのサービス対象としてではなく、一団体(サークル等含む)としてみなされる。 ・授業計画の授業構成を考えると、貸出⇒返却には一定の貸出期間を必要とする。今回は一度の延長貸出によりぎりぎりなんとかクリアできたが、もう少しゆとりある期間が欲しかった。 以上、公立図書館の学校図書館支援の状況を知ったり、区・都に属さない国立大学附属校として受けられる支援を知る機会としても有効でした。今後、所在地の公立図書館と関係性を深め、具体的に協力、支援を求めたい内容が明確になりました。 また、ごく一部の成果ではありますが、国立大学附属学校図書館のネットワークへ呼びかけたことで、1冊を提供いただくことができました。それら、独自のネットワークや体制づくりも同時に進めることで、いっそう豊かな授業に資する学校図書館の役割を果たしていけると感じました。 |
| 情報提供校 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 事例作成日 | 2013年10月(全7回、50分授業) |
| 事例作成者氏名 | 筑波大学附属駒場中学校・高等学校教諭 澤田英輔 司書 加藤志保 |
記入者:井谷

























