お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0180 校種 小学校 教科・領域等 特別活動 単元 お話給食 対象学年 中学年 活用・支援の種類 教材提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 秋の読書週間に合わせて「お話給食」にするので、「読みきかせした本」を教えてほしい。それをもとに、献立を考えたい。(全校対象) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 これから読む予定の本でもよいということなのでそれらを提示した。
提示資料 低学年、中学年、高学年とそれぞれに読むもののなかから、選んでもらいました。 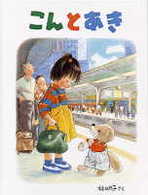
『こんとあき』林明子 福音館書店 1989年 生まれた時から一緒だったキツネのぬいぐるみの こん が、ほころびてきたので、あき はさきゅう町のおばあちゃんのところに、こん と一緒にでんしゃででかけました。途中でお弁当を買った時、こん はしっぽをドアに挟んでしまいます。 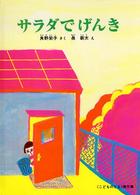
『サラダでげんき』角野栄子
長新太 2005年
りっちゃんはお母さんが病気になったので、なにかしてあげたいとサラダを作りました。そこに次々とあらわれる動物たちが○○をいれるといいですよと、アドバイスをくれるので、おいしいサラダができました。食べて、お母さんは元気になります。
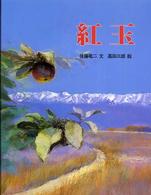
『紅玉』後藤竜二 高田三郎 新日本出版社 2005年
父は毎年リンゴの収穫の季節になると口にします。「あの人たち どうしてるべな」と。戦争が終わった年、まもなく収穫という紅玉のリンゴを、中国や朝鮮から無理やり連れて来られて炭鉱で過酷な労働をさせられたいた人々が襲います。父は必死に語りかけました。北海道美唄市出身の作者の体験に基づく物語です。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://kodomobook.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_f10c.html ブックリスト
キーワード1 給食 キーワード2 お話給食 キーワード3 読書週間 授業計画・指導案等 お話給食2013.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 東京学芸大学附属小金井小学校 栄養教諭 横山英吏子 授業者コメント 本を給食とともに味わってほしいなと思っています。お話給食当日の給食時間には、児童同士で、物語や献立について話している姿が見られたり、食堂入り口に展示した当日テーマの本をじっくりと見たりする様子が見られました。
また、「レシピを教えて欲しい」、「このお話しの本を持っています。大好きな本です。」、「夕日ハンバーグは、プチトマトが入っているかと思ったよ。でも丸形で赤いソースだった!」、「ドラゴンスープ、お母さんとどんなスープなのか前の日に考えて話していたよ。」など、お話と給食の話をしにくる児童も大勢いました。
司書・司書教諭コメント 『赤い目のドラゴン』では、ドラゴンの緑をスープにして赤い目が…、クライマックスの夕日をハンバーグに表現してくださいました。『こんとあき』ではふたりが食べたであろうお弁当に砂丘のある鳥取県の産物を使ってくださいました。『サラダでげんき』のりっちゃんが作ったサラダが本当に出ました。病気になった人にはおうどんがいいんだよと栄養もとれて消化の良いメニュー。『紅玉』では、紅玉の焼きリンゴと北海道の郷土料理にしてくださいました。物語の世界を料理―給食で表現。料理って、つくづく創造的な活動なんだと思わされます。食堂入り口の本の展示もよく見られたし、館内では休み時間も図書の時間も話題になていました。反省はその日のメニューになった本は、図書館ネットワークをつかって複本で用意して、あちこちで見られるように手配しておくべきだったという点でした。次年度はそのようにします。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2014年2月21日 実践日2013年11月 事例作成者氏名 東京学芸大学附属小金井小学校司書 中山美由紀
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863515 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0180 校種 小学校 教科・領域等 特別活動 単元 お話給食 対象学年 中学年 活用・支援の種類 教材提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 秋の読書週間に合わせて「お話給食」にするので、「読みきかせした本」を教えてほしい。それをもとに、献立を考えたい。(全校対象) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 これから読む予定の本でもよいということなのでそれらを提示した。
提示資料 低学年、中学年、高学年とそれぞれに読むもののなかから、選んでもらいました。 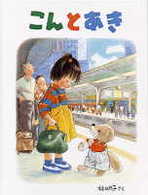
『こんとあき』林明子 福音館書店 1989年 生まれた時から一緒だったキツネのぬいぐるみの こん が、ほころびてきたので、あき はさきゅう町のおばあちゃんのところに、こん と一緒にでんしゃででかけました。途中でお弁当を買った時、こん はしっぽをドアに挟んでしまいます。 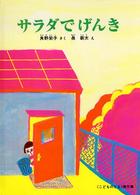
『サラダでげんき』角野栄子
長新太 2005年
りっちゃんはお母さんが病気になったので、なにかしてあげたいとサラダを作りました。そこに次々とあらわれる動物たちが○○をいれるといいですよと、アドバイスをくれるので、おいしいサラダができました。食べて、お母さんは元気になります。
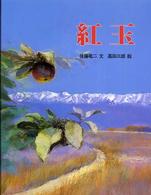
『紅玉』後藤竜二 高田三郎 新日本出版社 2005年
父は毎年リンゴの収穫の季節になると口にします。「あの人たち どうしてるべな」と。戦争が終わった年、まもなく収穫という紅玉のリンゴを、中国や朝鮮から無理やり連れて来られて炭鉱で過酷な労働をさせられたいた人々が襲います。父は必死に語りかけました。北海道美唄市出身の作者の体験に基づく物語です。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://kodomobook.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_f10c.html ブックリスト
キーワード1 給食 キーワード2 お話給食 キーワード3 読書週間 授業計画・指導案等 お話給食2013.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 東京学芸大学附属小金井小学校 栄養教諭 横山英吏子 授業者コメント 本を給食とともに味わってほしいなと思っています。お話給食当日の給食時間には、児童同士で、物語や献立について話している姿が見られたり、食堂入り口に展示した当日テーマの本をじっくりと見たりする様子が見られました。
また、「レシピを教えて欲しい」、「このお話しの本を持っています。大好きな本です。」、「夕日ハンバーグは、プチトマトが入っているかと思ったよ。でも丸形で赤いソースだった!」、「ドラゴンスープ、お母さんとどんなスープなのか前の日に考えて話していたよ。」など、お話と給食の話をしにくる児童も大勢いました。
司書・司書教諭コメント 『赤い目のドラゴン』では、ドラゴンの緑をスープにして赤い目が…、クライマックスの夕日をハンバーグに表現してくださいました。『こんとあき』ではふたりが食べたであろうお弁当に砂丘のある鳥取県の産物を使ってくださいました。『サラダでげんき』のりっちゃんが作ったサラダが本当に出ました。病気になった人にはおうどんがいいんだよと栄養もとれて消化の良いメニュー。『紅玉』では、紅玉の焼きリンゴと北海道の郷土料理にしてくださいました。物語の世界を料理―給食で表現。料理って、つくづく創造的な活動なんだと思わされます。食堂入り口の本の展示もよく見られたし、館内では休み時間も図書の時間も話題になていました。反省はその日のメニューになった本は、図書館ネットワークをつかって複本で用意して、あちこちで見られるように手配しておくべきだったという点でした。次年度はそのようにします。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2014年2月21日 実践日2013年11月 事例作成者氏名 東京学芸大学附属小金井小学校司書 中山美由紀
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863515 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0180 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 特別活動 |
| 単元 | お話給食 |
| 対象学年 | 中学年 |
| 活用・支援の種類 | 教材提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 秋の読書週間に合わせて「お話給食」にするので、「読みきかせした本」を教えてほしい。それをもとに、献立を考えたい。(全校対象) |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | これから読む予定の本でもよいということなのでそれらを提示した。 |
| 提示資料 | 低学年、中学年、高学年とそれぞれに読むもののなかから、選んでもらいました。 |
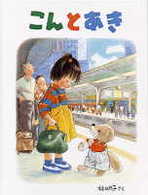 | 『こんとあき』林明子 福音館書店 1989年 生まれた時から一緒だったキツネのぬいぐるみの こん が、ほころびてきたので、あき はさきゅう町のおばあちゃんのところに、こん と一緒にでんしゃででかけました。途中でお弁当を買った時、こん はしっぽをドアに挟んでしまいます。 |
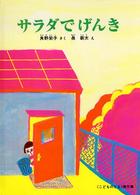 | 『サラダでげんき』角野栄子 長新太 2005年 りっちゃんはお母さんが病気になったので、なにかしてあげたいとサラダを作りました。そこに次々とあらわれる動物たちが○○をいれるといいですよと、アドバイスをくれるので、おいしいサラダができました。食べて、お母さんは元気になります。 |
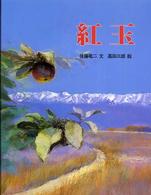 | 『紅玉』後藤竜二 高田三郎 新日本出版社 2005年 父は毎年リンゴの収穫の季節になると口にします。「あの人たち どうしてるべな」と。戦争が終わった年、まもなく収穫という紅玉のリンゴを、中国や朝鮮から無理やり連れて来られて炭鉱で過酷な労働をさせられたいた人々が襲います。父は必死に語りかけました。北海道美唄市出身の作者の体験に基づく物語です。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http://kodomobook.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_f10c.html |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 給食 |
| キーワード2 | お話給食 |
| キーワード3 | 読書週間 |
| 授業計画・指導案等 | お話給食2013.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 東京学芸大学附属小金井小学校 栄養教諭 横山英吏子 |
| 授業者コメント | 本を給食とともに味わってほしいなと思っています。お話給食当日の給食時間には、児童同士で、物語や献立について話している姿が見られたり、食堂入り口に展示した当日テーマの本をじっくりと見たりする様子が見られました。 また、「レシピを教えて欲しい」、「このお話しの本を持っています。大好きな本です。」、「夕日ハンバーグは、プチトマトが入っているかと思ったよ。でも丸形で赤いソースだった!」、「ドラゴンスープ、お母さんとどんなスープなのか前の日に考えて話していたよ。」など、お話と給食の話をしにくる児童も大勢いました。 |
| 司書・司書教諭コメント | 『赤い目のドラゴン』では、ドラゴンの緑をスープにして赤い目が…、クライマックスの夕日をハンバーグに表現してくださいました。『こんとあき』ではふたりが食べたであろうお弁当に砂丘のある鳥取県の産物を使ってくださいました。『サラダでげんき』のりっちゃんが作ったサラダが本当に出ました。病気になった人にはおうどんがいいんだよと栄養もとれて消化の良いメニュー。『紅玉』では、紅玉の焼きリンゴと北海道の郷土料理にしてくださいました。物語の世界を料理―給食で表現。料理って、つくづく創造的な活動なんだと思わされます。食堂入り口の本の展示もよく見られたし、館内では休み時間も図書の時間も話題になていました。反省はその日のメニューになった本は、図書館ネットワークをつかって複本で用意して、あちこちで見られるように手配しておくべきだったという点でした。次年度はそのようにします。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |
| 事例作成日 | 2014年2月21日 実践日2013年11月 |
| 事例作成者氏名 | 東京学芸大学附属小金井小学校司書 中山美由紀 |
記入者:中山(主担)

























