お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」は終了いたしました。当日参加してくださった皆様、配信をご覧になった皆様、こちらの参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。また、2月になりましたら、改めて視聴をご希望の皆さまには、申し込めるように整えます。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は埼玉県立松伏高等学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0280 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 うみのかくれんぼ 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料提供、読み聞かせ、学習支援 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 「海の生き物図鑑」づくりの学習を行うので、参考となる図書資料を紹介し、教室に貸してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 担任から単元終末のまとめの学習内容として行いたいとの要望があった。資料から魚を探し出すこと、さらに魚が隠れている場所、隠れるための特徴、隠れ方等の説明文を書かせたいとのことであった。最低でもグループに1冊資料となる図書がほしいとのこと。
提示資料 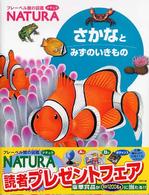
978-4-577-02842-1 フレーベルの図鑑ナチュラ『さかなとみずのいきもの』 / フレーベル館 「海の岩場にすむ魚」「海のすなぞこにすむ魚」「さんごしょうの魚」「たこ・いかのからだ」各々の項目において、平易な表現で、魚の特徴を説明してある。 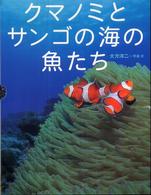
978-4-265-04355-2 『クマノミとサンゴの海の魚たち』 / 大方洋二:写真・文 / 岩崎書店 / 2008年 
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 海の生き物図鑑 キーワード2 説明文 キーワード3 しおり 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 上野美紀教諭 授業者コメント 単元の終末に、「海の生きもの図鑑」づくりとして、教科書には載っていない海の生き物を図書資料から見付け、カードにまとめる学習を設定した。しかし、自分で調べてカードにまとめる学習を経験したことのない子供たちにとって、図書資料を選び、そこから大事な事柄を見付けることは大変難しい活動である。「海の生き物をもっと知りたい」という子供たちの思いと、図鑑をつくる活動をうまくつなげるためには、学校司書との連携が必要であると考えた。
学校司書に、体の特徴を生かして隠れる海の生き物をピックアップしてもらい、「本のどこを見るとよいのか」「特徴はどこに書いてあるのか」など、図鑑の見方を分かりやすく子供たちに助言してもらった。子供たちはしおりの挟んであるページを読み比べながら、自分の興味をもった海の生きものを選んでカードにまとめることができた。子供たちは分からないことを、学校司書に質問したり、友達同士で教え合ったりして、自分でカードにまとめることができた。見付けた生き物を紹介する活動では、どの子供も興味をもって友達の話を聞き、海の生き物への関心を高めることができた。 これまで、図鑑を手にすることが少なかった子供も、進んで手に取るようになった。また、写真を見るだけではなく、説明の文章も一緒に読むなど、図鑑を活用する力が付いてきた。 司書・司書教諭コメント 担任からの依頼は「授業に使う本を揃えてほしい」ということだった。しかし、ただ本を揃えて資料を提供するだけでは、1年生が生き物を探し出すことは難しいと考え、学校司書が以下の①、②を授業支援として行うことを担任に提案した。
①かくれんぼしている生き物が載っている図鑑等のページにしおりをはさんでおく。
②子供たちが図鑑等の資料を使って調べるときの着眼点を話して理解させる。
子供たちに図書資料を手渡すと勝手に好きなページを見始め収集がつかななる恐れがあったが、しおりを挟んだことで、学習の目的が明確になりスムーズに学習が進んだ。読み聞かせで使用したフレーベル館の図鑑『NATURA』は表現が易しく、1年生への読み聞かせに最適だった。 読み聞かせで得た情報を元に、子供たちは的確に魚の特徴を見つけ出していた。 学校司書が資料提供するだけでなく、授業の支援も行ったことで、提供した資料を子供たちがどのように使ったのか、知ることが出来た。 情報提供校 富山市立神明小学校 事例作成日 事例作成 2016年10月17日 /授業実践 2016年9月27日 事例作成者氏名 学校司書 佐藤千雅子
記入者:村上
カウンタ
3800290 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」は終了いたしました。当日参加してくださった皆様、配信をご覧になった皆様、こちらの参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。また、2月になりましたら、改めて視聴をご希望の皆さまには、申し込めるように整えます。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は埼玉県立松伏高等学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0280 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 うみのかくれんぼ 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料提供、読み聞かせ、学習支援 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 「海の生き物図鑑」づくりの学習を行うので、参考となる図書資料を紹介し、教室に貸してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 担任から単元終末のまとめの学習内容として行いたいとの要望があった。資料から魚を探し出すこと、さらに魚が隠れている場所、隠れるための特徴、隠れ方等の説明文を書かせたいとのことであった。最低でもグループに1冊資料となる図書がほしいとのこと。
提示資料 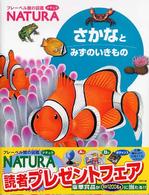
978-4-577-02842-1 フレーベルの図鑑ナチュラ『さかなとみずのいきもの』 / フレーベル館 「海の岩場にすむ魚」「海のすなぞこにすむ魚」「さんごしょうの魚」「たこ・いかのからだ」各々の項目において、平易な表現で、魚の特徴を説明してある。 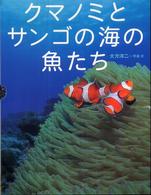
978-4-265-04355-2 『クマノミとサンゴの海の魚たち』 / 大方洋二:写真・文 / 岩崎書店 / 2008年 
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 海の生き物図鑑 キーワード2 説明文 キーワード3 しおり 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 上野美紀教諭 授業者コメント 単元の終末に、「海の生きもの図鑑」づくりとして、教科書には載っていない海の生き物を図書資料から見付け、カードにまとめる学習を設定した。しかし、自分で調べてカードにまとめる学習を経験したことのない子供たちにとって、図書資料を選び、そこから大事な事柄を見付けることは大変難しい活動である。「海の生き物をもっと知りたい」という子供たちの思いと、図鑑をつくる活動をうまくつなげるためには、学校司書との連携が必要であると考えた。
学校司書に、体の特徴を生かして隠れる海の生き物をピックアップしてもらい、「本のどこを見るとよいのか」「特徴はどこに書いてあるのか」など、図鑑の見方を分かりやすく子供たちに助言してもらった。子供たちはしおりの挟んであるページを読み比べながら、自分の興味をもった海の生きものを選んでカードにまとめることができた。子供たちは分からないことを、学校司書に質問したり、友達同士で教え合ったりして、自分でカードにまとめることができた。見付けた生き物を紹介する活動では、どの子供も興味をもって友達の話を聞き、海の生き物への関心を高めることができた。 これまで、図鑑を手にすることが少なかった子供も、進んで手に取るようになった。また、写真を見るだけではなく、説明の文章も一緒に読むなど、図鑑を活用する力が付いてきた。 司書・司書教諭コメント 担任からの依頼は「授業に使う本を揃えてほしい」ということだった。しかし、ただ本を揃えて資料を提供するだけでは、1年生が生き物を探し出すことは難しいと考え、学校司書が以下の①、②を授業支援として行うことを担任に提案した。
①かくれんぼしている生き物が載っている図鑑等のページにしおりをはさんでおく。
②子供たちが図鑑等の資料を使って調べるときの着眼点を話して理解させる。
子供たちに図書資料を手渡すと勝手に好きなページを見始め収集がつかななる恐れがあったが、しおりを挟んだことで、学習の目的が明確になりスムーズに学習が進んだ。読み聞かせで使用したフレーベル館の図鑑『NATURA』は表現が易しく、1年生への読み聞かせに最適だった。 読み聞かせで得た情報を元に、子供たちは的確に魚の特徴を見つけ出していた。 学校司書が資料提供するだけでなく、授業の支援も行ったことで、提供した資料を子供たちがどのように使ったのか、知ることが出来た。 情報提供校 富山市立神明小学校 事例作成日 事例作成 2016年10月17日 /授業実践 2016年9月27日 事例作成者氏名 学校司書 佐藤千雅子
記入者:村上
カウンタ
3800290 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0280 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | うみのかくれんぼ |
| 対象学年 | 低学年 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供、読み聞かせ、学習支援 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 「海の生き物図鑑」づくりの学習を行うので、参考となる図書資料を紹介し、教室に貸してほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 担任から単元終末のまとめの学習内容として行いたいとの要望があった。資料から魚を探し出すこと、さらに魚が隠れている場所、隠れるための特徴、隠れ方等の説明文を書かせたいとのことであった。最低でもグループに1冊資料となる図書がほしいとのこと。 |
| 提示資料 | |
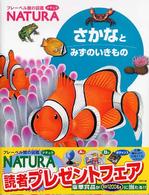 | 978-4-577-02842-1 フレーベルの図鑑ナチュラ『さかなとみずのいきもの』 / フレーベル館 「海の岩場にすむ魚」「海のすなぞこにすむ魚」「さんごしょうの魚」「たこ・いかのからだ」各々の項目において、平易な表現で、魚の特徴を説明してある。 |
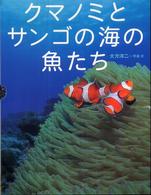 | 978-4-265-04355-2 『クマノミとサンゴの海の魚たち』 / 大方洋二:写真・文 / 岩崎書店 / 2008年 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 海の生き物図鑑 |
| キーワード2 | 説明文 |
| キーワード3 | しおり |
| 授業計画・指導案等 | |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 上野美紀教諭 |
| 授業者コメント | 単元の終末に、「海の生きもの図鑑」づくりとして、教科書には載っていない海の生き物を図書資料から見付け、カードにまとめる学習を設定した。しかし、自分で調べてカードにまとめる学習を経験したことのない子供たちにとって、図書資料を選び、そこから大事な事柄を見付けることは大変難しい活動である。「海の生き物をもっと知りたい」という子供たちの思いと、図鑑をつくる活動をうまくつなげるためには、学校司書との連携が必要であると考えた。 学校司書に、体の特徴を生かして隠れる海の生き物をピックアップしてもらい、「本のどこを見るとよいのか」「特徴はどこに書いてあるのか」など、図鑑の見方を分かりやすく子供たちに助言してもらった。子供たちはしおりの挟んであるページを読み比べながら、自分の興味をもった海の生きものを選んでカードにまとめることができた。子供たちは分からないことを、学校司書に質問したり、友達同士で教え合ったりして、自分でカードにまとめることができた。見付けた生き物を紹介する活動では、どの子供も興味をもって友達の話を聞き、海の生き物への関心を高めることができた。 これまで、図鑑を手にすることが少なかった子供も、進んで手に取るようになった。また、写真を見るだけではなく、説明の文章も一緒に読むなど、図鑑を活用する力が付いてきた。 |
| 司書・司書教諭コメント | 担任からの依頼は「授業に使う本を揃えてほしい」ということだった。しかし、ただ本を揃えて資料を提供するだけでは、1年生が生き物を探し出すことは難しいと考え、学校司書が以下の①、②を授業支援として行うことを担任に提案した。 ①かくれんぼしている生き物が載っている図鑑等のページにしおりをはさんでおく。 ②子供たちが図鑑等の資料を使って調べるときの着眼点を話して理解させる。 子供たちに図書資料を手渡すと勝手に好きなページを見始め収集がつかななる恐れがあったが、しおりを挟んだことで、学習の目的が明確になりスムーズに学習が進んだ。読み聞かせで使用したフレーベル館の図鑑『NATURA』は表現が易しく、1年生への読み聞かせに最適だった。 読み聞かせで得た情報を元に、子供たちは的確に魚の特徴を見つけ出していた。 学校司書が資料提供するだけでなく、授業の支援も行ったことで、提供した資料を子供たちがどのように使ったのか、知ることが出来た。 |
| 情報提供校 | 富山市立神明小学校 |
| 事例作成日 | 事例作成 2016年10月17日 /授業実践 2016年9月27日 |
| 事例作成者氏名 | 学校司書 佐藤千雅子 |
記入者:村上

























