お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0024 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 人権を考える 対象学年 中3 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 人権についてのグループ学習を予定しているので資料の準備をお願いします。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 あらかじめ設定したテーマは以下のもの。死刑制度の是非・靖国神社参拝問題・君が代問題・外国人の選挙権・女性の仕事と子育て・夫婦別姓・知的障害者の統合教育・犯罪事件における実名報道について・安楽死、尊厳死について・空港の騒音問題。事前に設定したテーマについて、簡単に自分の考えを書き、どちらの立場に現在あるかを記入してもらったうえで、自分が調べてもいいテーマをいくつかあげさせて、先生がそれをもとにグループを決定。生徒は自分達が選んだテーマについて本とインターネットを使って調べて、発表する予定とのこと。
提示資料 自館にあるものと、公共図書館から借りてきて、資料は提供した。グループごとに調べるので、資料はテーマごとにかごに入れ、かごに資料一覧を掲示。騒音に関する資料はなかったので、インターネットで資料を探してもらった。 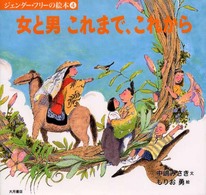
『男と女これまで、これから;ジェンダーフリーの絵本4』
中嶋みさき文 もりお勇絵 大月書店 2001
全6巻のジェンダー・フリー絵本の中の1一冊。この巻では特に歴史を遡り、女性と男性がどのような役割分担をしてきたのかを振り返ります。その時々にいろいろな生き方をしてきた男と女。歴史のなかでつくられてきた姿は、また作り替えることも可能だと示唆している絵本です。 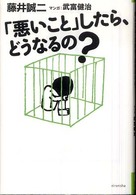
『「悪いこと」したらどうなるの?』
藤井誠二(著) マンガ:武富健治 理論社 2008
子どもが万一「犯罪」を犯したらどうなるのかを子どもたちだってきちんと知るべきなのでは…という視点できちんと書かれた本です。大人達には知らせる義務が、そして子どもには知る権利がある。「少年犯罪」の当事者としてではない私たちも知るべきこと、考えなくてはいけないことがある。死刑制度もしかり。

『世界を信じるためのメソッド;ぼくらの時代のリテラシー』
森達也(著) 理論社 2006
私たちの世界観は、実はメディアによって作られている。だからこそ、メディアはとても大切だが、同時にメディアは誤った情報を流すこともある。時にはそれが意図的であることも。そんなメディアとどうつきおあっていけばいいのか、中学生にわかることばで語る好著。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 人権に関する本リスト.xls
キーワード1 人権学習 キーワード2 キーワード3 授業計画・指導案等 3年社会科グループ発表学習(参考資料).pdf 児童・生徒の作品 授業者 荒井正剛 授業者コメント 今回は、比較的議論がしやすいテーマということで設定したため、テーマによっては中学生が読めるような資料が少ないものもあった。次回は適切な資料があるかも考慮しながらテーマを絞る必要があると感じた。このようなグループ学習をする利点は、普段つきあっている友達が、そんなふうに考えていたのかという驚きや、自分と違う意見の存在に気づくこと、また調べたり、発表を聞きあうなかで、自分の考えを改めたり、さらに強固なものになったりという経験を持つことだといえる。 司書・司書教諭コメント 用意した資料は、必ずしも読みやすいものばかりではなかったので、使われ方にかなり差があった。今後もこのような学習があることを想定して、必要な資料をもう少し精査して集めたい。授業終了後、担当教諭に用意した資料の評価をお願いした。あくまでこの授業のなかで生徒にとってという視点だが、このような評価の積み重ねは大切だと感じた。
情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2009.12.21 事例作成者氏名
記入者:村上
カウンタ
3863377 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0024 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 人権を考える 対象学年 中3 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 人権についてのグループ学習を予定しているので資料の準備をお願いします。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 あらかじめ設定したテーマは以下のもの。死刑制度の是非・靖国神社参拝問題・君が代問題・外国人の選挙権・女性の仕事と子育て・夫婦別姓・知的障害者の統合教育・犯罪事件における実名報道について・安楽死、尊厳死について・空港の騒音問題。事前に設定したテーマについて、簡単に自分の考えを書き、どちらの立場に現在あるかを記入してもらったうえで、自分が調べてもいいテーマをいくつかあげさせて、先生がそれをもとにグループを決定。生徒は自分達が選んだテーマについて本とインターネットを使って調べて、発表する予定とのこと。
提示資料 自館にあるものと、公共図書館から借りてきて、資料は提供した。グループごとに調べるので、資料はテーマごとにかごに入れ、かごに資料一覧を掲示。騒音に関する資料はなかったので、インターネットで資料を探してもらった。 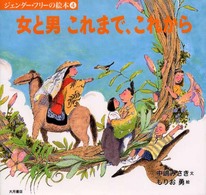
『男と女これまで、これから;ジェンダーフリーの絵本4』
中嶋みさき文 もりお勇絵 大月書店 2001
全6巻のジェンダー・フリー絵本の中の1一冊。この巻では特に歴史を遡り、女性と男性がどのような役割分担をしてきたのかを振り返ります。その時々にいろいろな生き方をしてきた男と女。歴史のなかでつくられてきた姿は、また作り替えることも可能だと示唆している絵本です。 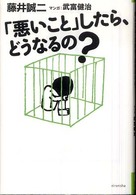
『「悪いこと」したらどうなるの?』
藤井誠二(著) マンガ:武富健治 理論社 2008
子どもが万一「犯罪」を犯したらどうなるのかを子どもたちだってきちんと知るべきなのでは…という視点できちんと書かれた本です。大人達には知らせる義務が、そして子どもには知る権利がある。「少年犯罪」の当事者としてではない私たちも知るべきこと、考えなくてはいけないことがある。死刑制度もしかり。

『世界を信じるためのメソッド;ぼくらの時代のリテラシー』
森達也(著) 理論社 2006
私たちの世界観は、実はメディアによって作られている。だからこそ、メディアはとても大切だが、同時にメディアは誤った情報を流すこともある。時にはそれが意図的であることも。そんなメディアとどうつきおあっていけばいいのか、中学生にわかることばで語る好著。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 人権に関する本リスト.xls
キーワード1 人権学習 キーワード2 キーワード3 授業計画・指導案等 3年社会科グループ発表学習(参考資料).pdf 児童・生徒の作品 授業者 荒井正剛 授業者コメント 今回は、比較的議論がしやすいテーマということで設定したため、テーマによっては中学生が読めるような資料が少ないものもあった。次回は適切な資料があるかも考慮しながらテーマを絞る必要があると感じた。このようなグループ学習をする利点は、普段つきあっている友達が、そんなふうに考えていたのかという驚きや、自分と違う意見の存在に気づくこと、また調べたり、発表を聞きあうなかで、自分の考えを改めたり、さらに強固なものになったりという経験を持つことだといえる。 司書・司書教諭コメント 用意した資料は、必ずしも読みやすいものばかりではなかったので、使われ方にかなり差があった。今後もこのような学習があることを想定して、必要な資料をもう少し精査して集めたい。授業終了後、担当教諭に用意した資料の評価をお願いした。あくまでこの授業のなかで生徒にとってという視点だが、このような評価の積み重ねは大切だと感じた。
情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2009.12.21 事例作成者氏名
記入者:村上
カウンタ
3863377 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0024 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 社会 |
| 単元 | 人権を考える |
| 対象学年 | 中3 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 人権についてのグループ学習を予定しているので資料の準備をお願いします。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | あらかじめ設定したテーマは以下のもの。死刑制度の是非・靖国神社参拝問題・君が代問題・外国人の選挙権・女性の仕事と子育て・夫婦別姓・知的障害者の統合教育・犯罪事件における実名報道について・安楽死、尊厳死について・空港の騒音問題。事前に設定したテーマについて、簡単に自分の考えを書き、どちらの立場に現在あるかを記入してもらったうえで、自分が調べてもいいテーマをいくつかあげさせて、先生がそれをもとにグループを決定。生徒は自分達が選んだテーマについて本とインターネットを使って調べて、発表する予定とのこと。 |
| 提示資料 | 自館にあるものと、公共図書館から借りてきて、資料は提供した。グループごとに調べるので、資料はテーマごとにかごに入れ、かごに資料一覧を掲示。騒音に関する資料はなかったので、インターネットで資料を探してもらった。 |
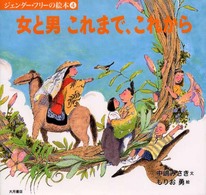 | 『男と女これまで、これから;ジェンダーフリーの絵本4』 中嶋みさき文 もりお勇絵 大月書店 2001 全6巻のジェンダー・フリー絵本の中の1一冊。この巻では特に歴史を遡り、女性と男性がどのような役割分担をしてきたのかを振り返ります。その時々にいろいろな生き方をしてきた男と女。歴史のなかでつくられてきた姿は、また作り替えることも可能だと示唆している絵本です。 |
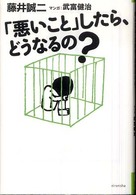 | 『「悪いこと」したらどうなるの?』 藤井誠二(著) マンガ:武富健治 理論社 2008 子どもが万一「犯罪」を犯したらどうなるのかを子どもたちだってきちんと知るべきなのでは…という視点できちんと書かれた本です。大人達には知らせる義務が、そして子どもには知る権利がある。「少年犯罪」の当事者としてではない私たちも知るべきこと、考えなくてはいけないことがある。死刑制度もしかり。 |
 | 『世界を信じるためのメソッド;ぼくらの時代のリテラシー』 森達也(著) 理論社 2006 私たちの世界観は、実はメディアによって作られている。だからこそ、メディアはとても大切だが、同時にメディアは誤った情報を流すこともある。時にはそれが意図的であることも。そんなメディアとどうつきおあっていけばいいのか、中学生にわかることばで語る好著。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 人権に関する本リスト.xls |
| キーワード1 | 人権学習 |
| キーワード2 | |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | 3年社会科グループ発表学習(参考資料).pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 荒井正剛 |
| 授業者コメント | 今回は、比較的議論がしやすいテーマということで設定したため、テーマによっては中学生が読めるような資料が少ないものもあった。次回は適切な資料があるかも考慮しながらテーマを絞る必要があると感じた。このようなグループ学習をする利点は、普段つきあっている友達が、そんなふうに考えていたのかという驚きや、自分と違う意見の存在に気づくこと、また調べたり、発表を聞きあうなかで、自分の考えを改めたり、さらに強固なものになったりという経験を持つことだといえる。 |
| 司書・司書教諭コメント | 用意した資料は、必ずしも読みやすいものばかりではなかったので、使われ方にかなり差があった。今後もこのような学習があることを想定して、必要な資料をもう少し精査して集めたい。授業終了後、担当教諭に用意した資料の評価をお願いした。あくまでこの授業のなかで生徒にとってという視点だが、このような評価の積み重ねは大切だと感じた。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
| 事例作成日 | 2009.12.21 |
| 事例作成者氏名 |
記入者:村上

























