お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0026 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 読書ポスター 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供 他 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 夏休み中に、近代文学作品を読み、普段読んでいる現代作家の作品と比較したレポート(ポスター)を作成させたい。2学期には、そのための作家・作品について調べる時間もとりたい。
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 先生が選んだ近代文学作家は、次の10名。夏目漱石・太宰治・芥川龍之介・森鴎外・梶井基次郎・川端康成・井伏鱒二・中嶋篤・堀辰雄・横光利一。生徒の要望もあり、江戸川乱歩・三島由紀夫を追加。夏休み前に、これらの作家の作品を並べたコーナーを設置。2学期に自分が選んだ作家について、あるいはその作品について書かれた資料を読み、ワークシートに書き込む。さらに、現代文学作品との比較をし、レポートを作成させたいとのこと。図書館での授業時には、公共図書館からも資料を借りて、作家に関する本や近代文学案内などを用意した。
提示資料 少年少女に近代文学の魅力を伝えてくれる本の中から、特にお薦めの三冊。
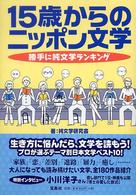
『15歳からのニッポン文学;勝手に純文学ランキング」
著:純文学研究会 宝島社 2005
作家や文芸評論家、大学・高校の先生など、“文学のプロ”が10代後半~20代の若者に読んでほしい、あるいは自分が若い頃に読んで感動した本をランキングにして紹介。切り口も面白く、読みやすい本の構成。何を読んだらいいかわからない中学生向け。
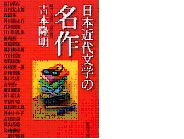
『日本近代文学の名作』
吉本隆明著 構成/大井浩一・重里徹也 新潮社 2008年
近代文学の名作について吉本隆明が語り、毎日新聞学芸部の記者が話を要約し、構成したもの。簡単な作家紹介、作品紹介のページもあり、そのあとに作品について語られたことが要約されている。
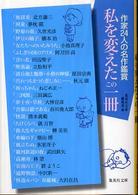
『作家24人の名作鑑賞;私を変えたこの一冊』
集英社文庫編集部 編 集英社 2007
著名な作家たちが、“名作”にどう出会い、どう読み、自分がどう変わったのかが綴られた本。中学生が自分の読みと、作家の読みとを比較するうえでも、読みやすい一冊。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 近代文学 キーワード2 キーワード3 授業計画・指導案等 読書ポスター.pdf 児童・生徒の作品 授業者 渡邉裕 授業者コメント 近代文学に親しんでもらうという、この単元のいちばんの目的は達成することができた。普段なかなか自分では手にしない作家の作品を読み、現代作家の作品と比較することで、それぞれの良さに気づけた生徒も多かった。また、特定の視点を持って文学を読むという試みも新鮮であったと感じた生徒もいた。レポートを書くことで、引用や参考文献の扱いに関する意識付けができるようになった。
司書・司書教諭コメント 日常的に読書に親しんでいる生徒は、近代文学作品であっても、読むことは苦ではなく、むしろ今まで読まなかったジャンルの本の面白さに気づいた生徒も少なくない。ただ、日頃からあまり本を読まない生徒には、まして近代文学ということで、敷居が高く、そのうえ、近代と現代を比較するにいたっては、かなり高度なことを要求されていると感じているように見受けられた。(本が苦手タイプの男子生徒は江戸川乱歩が人気!)また、比較という視点で、現代作家の作品を何にしたらいいかという相談を受けたりもした。参考文献や引用に関しては、このような授業のなかで必要なこととして学ぶ機会を持ってもらえるとたいへんありがたい。
情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2010.1.22 事例作成者氏名
記入者:村上
カウンタ
3863398 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0026 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 読書ポスター 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供 他 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 夏休み中に、近代文学作品を読み、普段読んでいる現代作家の作品と比較したレポート(ポスター)を作成させたい。2学期には、そのための作家・作品について調べる時間もとりたい。
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 先生が選んだ近代文学作家は、次の10名。夏目漱石・太宰治・芥川龍之介・森鴎外・梶井基次郎・川端康成・井伏鱒二・中嶋篤・堀辰雄・横光利一。生徒の要望もあり、江戸川乱歩・三島由紀夫を追加。夏休み前に、これらの作家の作品を並べたコーナーを設置。2学期に自分が選んだ作家について、あるいはその作品について書かれた資料を読み、ワークシートに書き込む。さらに、現代文学作品との比較をし、レポートを作成させたいとのこと。図書館での授業時には、公共図書館からも資料を借りて、作家に関する本や近代文学案内などを用意した。
提示資料 少年少女に近代文学の魅力を伝えてくれる本の中から、特にお薦めの三冊。
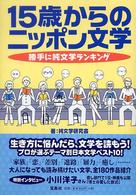
『15歳からのニッポン文学;勝手に純文学ランキング」
著:純文学研究会 宝島社 2005
作家や文芸評論家、大学・高校の先生など、“文学のプロ”が10代後半~20代の若者に読んでほしい、あるいは自分が若い頃に読んで感動した本をランキングにして紹介。切り口も面白く、読みやすい本の構成。何を読んだらいいかわからない中学生向け。
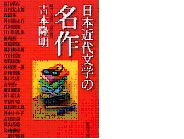
『日本近代文学の名作』
吉本隆明著 構成/大井浩一・重里徹也 新潮社 2008年
近代文学の名作について吉本隆明が語り、毎日新聞学芸部の記者が話を要約し、構成したもの。簡単な作家紹介、作品紹介のページもあり、そのあとに作品について語られたことが要約されている。
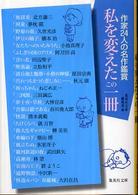
『作家24人の名作鑑賞;私を変えたこの一冊』
集英社文庫編集部 編 集英社 2007
著名な作家たちが、“名作”にどう出会い、どう読み、自分がどう変わったのかが綴られた本。中学生が自分の読みと、作家の読みとを比較するうえでも、読みやすい一冊。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 近代文学 キーワード2 キーワード3 授業計画・指導案等 読書ポスター.pdf 児童・生徒の作品 授業者 渡邉裕 授業者コメント 近代文学に親しんでもらうという、この単元のいちばんの目的は達成することができた。普段なかなか自分では手にしない作家の作品を読み、現代作家の作品と比較することで、それぞれの良さに気づけた生徒も多かった。また、特定の視点を持って文学を読むという試みも新鮮であったと感じた生徒もいた。レポートを書くことで、引用や参考文献の扱いに関する意識付けができるようになった。
司書・司書教諭コメント 日常的に読書に親しんでいる生徒は、近代文学作品であっても、読むことは苦ではなく、むしろ今まで読まなかったジャンルの本の面白さに気づいた生徒も少なくない。ただ、日頃からあまり本を読まない生徒には、まして近代文学ということで、敷居が高く、そのうえ、近代と現代を比較するにいたっては、かなり高度なことを要求されていると感じているように見受けられた。(本が苦手タイプの男子生徒は江戸川乱歩が人気!)また、比較という視点で、現代作家の作品を何にしたらいいかという相談を受けたりもした。参考文献や引用に関しては、このような授業のなかで必要なこととして学ぶ機会を持ってもらえるとたいへんありがたい。
情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2010.1.22 事例作成者氏名
記入者:村上
カウンタ
3863398 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0026 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 読書ポスター |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 他 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 夏休み中に、近代文学作品を読み、普段読んでいる現代作家の作品と比較したレポート(ポスター)を作成させたい。2学期には、そのための作家・作品について調べる時間もとりたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 先生が選んだ近代文学作家は、次の10名。夏目漱石・太宰治・芥川龍之介・森鴎外・梶井基次郎・川端康成・井伏鱒二・中嶋篤・堀辰雄・横光利一。生徒の要望もあり、江戸川乱歩・三島由紀夫を追加。夏休み前に、これらの作家の作品を並べたコーナーを設置。2学期に自分が選んだ作家について、あるいはその作品について書かれた資料を読み、ワークシートに書き込む。さらに、現代文学作品との比較をし、レポートを作成させたいとのこと。図書館での授業時には、公共図書館からも資料を借りて、作家に関する本や近代文学案内などを用意した。 |
| 提示資料 | 少年少女に近代文学の魅力を伝えてくれる本の中から、特にお薦めの三冊。 |
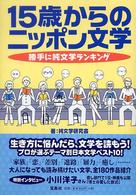 | 『15歳からのニッポン文学;勝手に純文学ランキング」 著:純文学研究会 宝島社 2005 作家や文芸評論家、大学・高校の先生など、“文学のプロ”が10代後半~20代の若者に読んでほしい、あるいは自分が若い頃に読んで感動した本をランキングにして紹介。切り口も面白く、読みやすい本の構成。何を読んだらいいかわからない中学生向け。 |
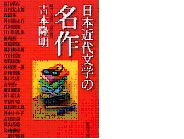 | 『日本近代文学の名作』 吉本隆明著 構成/大井浩一・重里徹也 新潮社 2008年 近代文学の名作について吉本隆明が語り、毎日新聞学芸部の記者が話を要約し、構成したもの。簡単な作家紹介、作品紹介のページもあり、そのあとに作品について語られたことが要約されている。 |
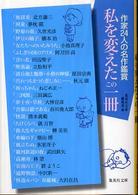 | 『作家24人の名作鑑賞;私を変えたこの一冊』 集英社文庫編集部 編 集英社 2007 著名な作家たちが、“名作”にどう出会い、どう読み、自分がどう変わったのかが綴られた本。中学生が自分の読みと、作家の読みとを比較するうえでも、読みやすい一冊。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 近代文学 |
| キーワード2 | |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | 読書ポスター.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 渡邉裕 |
| 授業者コメント | 近代文学に親しんでもらうという、この単元のいちばんの目的は達成することができた。普段なかなか自分では手にしない作家の作品を読み、現代作家の作品と比較することで、それぞれの良さに気づけた生徒も多かった。また、特定の視点を持って文学を読むという試みも新鮮であったと感じた生徒もいた。レポートを書くことで、引用や参考文献の扱いに関する意識付けができるようになった。 |
| 司書・司書教諭コメント | 日常的に読書に親しんでいる生徒は、近代文学作品であっても、読むことは苦ではなく、むしろ今まで読まなかったジャンルの本の面白さに気づいた生徒も少なくない。ただ、日頃からあまり本を読まない生徒には、まして近代文学ということで、敷居が高く、そのうえ、近代と現代を比較するにいたっては、かなり高度なことを要求されていると感じているように見受けられた。(本が苦手タイプの男子生徒は江戸川乱歩が人気!)また、比較という視点で、現代作家の作品を何にしたらいいかという相談を受けたりもした。参考文献や引用に関しては、このような授業のなかで必要なこととして学ぶ機会を持ってもらえるとたいへんありがたい。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
| 事例作成日 | 2010.1.22 |
| 事例作成者氏名 |
記入者:村上

























