お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0430 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 世界の諸地域「ヨーロッパ州」 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供・レファレンス 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 3学期に生徒による授業を計画しているので、ヨーロッパに関する資料を集めてほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 生徒は3~4人グループで、「なぜヨーロッパの国々は一つにまとまろうとしているのか、果たしてまとまることはできるのか。」という単元の学習課題を設定し、3~4人のグループで自分たちの作った学習指導案をもとに授業を行う。まずは図書資料を調べるところからスタートしたい。
提示資料 提示資料の1と2、中学生の学習に適した資料なので、附属学校から借りて副本を用意した。 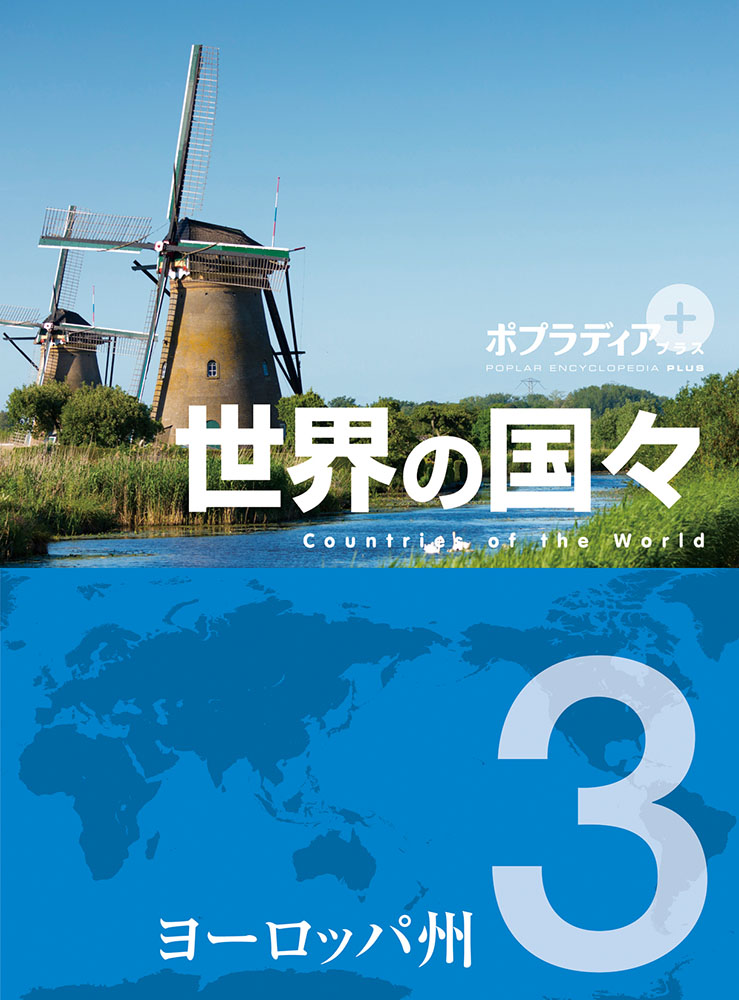
『ポプラディアプラス3 世界の国々 ヨーロッパ州3 ポプラ社 2019
児童生徒を対象とした学習用事典。最初にヨーロッパ全体の自然・歴史・文化・産業について書かれていて、そのあとは、ヨーロッパ各国について、コンパクトにまとまっている。中学生が調べるには、最適な一冊。 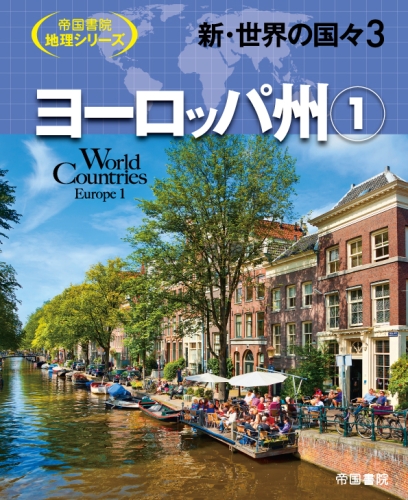
『帝国書院地理シリーズ 新・世界の国々3ヨーロッパ州⓵』兼子純監修 帝国書院 2020
地理の教科書も出している帝国書院のシリーズだけに、教科書に沿った学習には最適。2012年版も蔵書にあるので、あわせて提供したが、どこが変わっているかまで注目してくれたのかは、わからない。地理資料は、できるだけ新しいものが必要になるので悩ましい。 
『国境で読み解くヨーロッパ:境界の地理紀行』加賀美雅弘著 朝倉書店 2022
今回の学習にあたって、使えるかなと思って新たに買い足した資料の1冊。ヨーロッパで地理学の調査をし続けてきた著者が、国境をキーワードに、歴史、民族問題、観光、多様性、鉄道などのテーマを掘り下げた1冊。ヨーロッパは国境だらけで、国境は見どころが多いという。この本で仕入れた豆知識を、生徒授業で披露してくれたら嬉しいが…。ただし、読むには時間がかかる資料かもしれない。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト ヨーロッパに関するブックリスト生徒用2022.12.15.xlsx
キーワード1 ヨーロッパ キーワード2 EU キーワード3 生徒授業 授業計画・指導案等 チャレンジ!生徒授業.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 篠塚昭司 授業者コメント この生徒授業は単なる調べ・発表学習ではなく、自ら担当国の課題を見つけ解決をめざす問題解決型学習として実施しました。そのため、生徒たちの学習過程は、「情報収集」(担当国の調べ学習)→「学習問題を設定」(授業で伝えたい担当国の特色を発見)→「学習指導案作成」(担当国の特色をどのように伝えていくか)→「生徒授業実践」の流れで進めていきました。
学習過程の中で、特に学校図書館との連携が有効だったのは、「情報収集」の場面です。本当に興味を持った「学習問題を設定」するためには、できるだけ多くの「情報取集」をすることが必要になります。そこで、図書館司書の先生にお願いし、他の附属学校の図書館からもヨーロッパ州の国々に関する様々な本を集めていただきました。とかく、現代の中学生たちは「情報収集」の際に、インターネットを活用しがちですが、まずは情報源が明確で信頼性が高い本の情報を重要視する生徒になってほしいという思いからでした。その後、図書館司書の先生に、情報のファクトチェック方法やインターネットサイトや新聞データベースの検索方法といった多様な収集手段についてもお話していただいた上で、タブレットPCの活用を始めました。このように、生徒たちが多角的・多面的な「情報収集」を行ったことが、今回の生徒授業成功のカギとなった気がしています。 司書・司書教諭コメント この授業の時は、他教科でも図書館を使う授業があったため、用意した資料は、通しナンバーをつけてさらには国別の見出しをつけて社会科教室に持ち込みんだ。リストに載せ忘れた資料が、あとからいくつか見つかったので追加コーナーも作った。
授業の冒頭のみ顔を出したが、実際の様子や生徒授業の様子を見学できず、残念だったが、充実した授業が行われたようで嬉しく思う。生徒授業から半年も過ぎてしまったが、図書館に来ていた現2年生に、生徒授業をやってみての感想を聞いてみた。「生徒授業は、自分で調べるのでその国に対する興味が凄く沸いた。他のグループの授業も、中学生ならではの視点があってとても面白かった。」とのこと。
早い時期から、授業内容を伝えていただき、資料の準備を依頼されていたので、余裕をもって他附属の図書館から借りて提供することができた。一人一台端末になり、ネットの情報も使うことが増えたので、必ずその際に注意してほしいことは図書館からも伝えるように心がけている。ブックリストも、今回はTeams上から提供したので、使えるサイトはリンクを貼れるのは、ICT活用の利点と言える。今年の生徒授業はぜひ見学に行きたいと思う。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2023.9.29 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3863490 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0430 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 世界の諸地域「ヨーロッパ州」 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供・レファレンス 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 3学期に生徒による授業を計画しているので、ヨーロッパに関する資料を集めてほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 生徒は3~4人グループで、「なぜヨーロッパの国々は一つにまとまろうとしているのか、果たしてまとまることはできるのか。」という単元の学習課題を設定し、3~4人のグループで自分たちの作った学習指導案をもとに授業を行う。まずは図書資料を調べるところからスタートしたい。
提示資料 提示資料の1と2、中学生の学習に適した資料なので、附属学校から借りて副本を用意した。 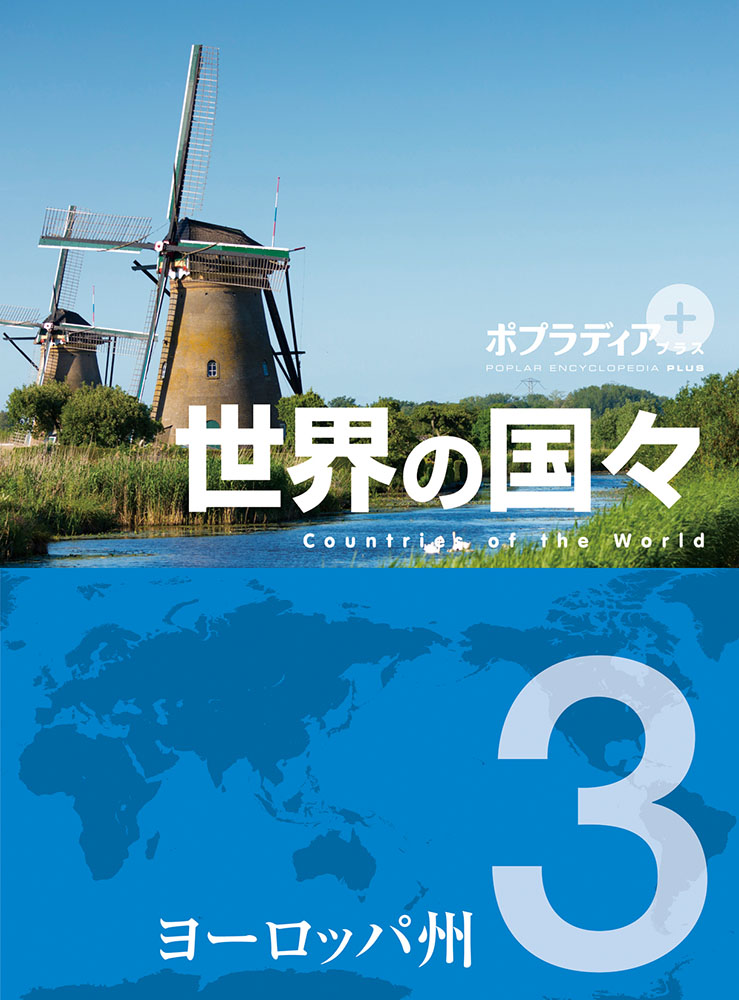
『ポプラディアプラス3 世界の国々 ヨーロッパ州3 ポプラ社 2019
児童生徒を対象とした学習用事典。最初にヨーロッパ全体の自然・歴史・文化・産業について書かれていて、そのあとは、ヨーロッパ各国について、コンパクトにまとまっている。中学生が調べるには、最適な一冊。 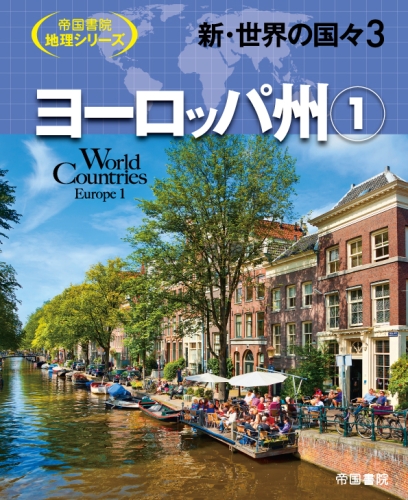
『帝国書院地理シリーズ 新・世界の国々3ヨーロッパ州⓵』兼子純監修 帝国書院 2020
地理の教科書も出している帝国書院のシリーズだけに、教科書に沿った学習には最適。2012年版も蔵書にあるので、あわせて提供したが、どこが変わっているかまで注目してくれたのかは、わからない。地理資料は、できるだけ新しいものが必要になるので悩ましい。 
『国境で読み解くヨーロッパ:境界の地理紀行』加賀美雅弘著 朝倉書店 2022
今回の学習にあたって、使えるかなと思って新たに買い足した資料の1冊。ヨーロッパで地理学の調査をし続けてきた著者が、国境をキーワードに、歴史、民族問題、観光、多様性、鉄道などのテーマを掘り下げた1冊。ヨーロッパは国境だらけで、国境は見どころが多いという。この本で仕入れた豆知識を、生徒授業で披露してくれたら嬉しいが…。ただし、読むには時間がかかる資料かもしれない。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト ヨーロッパに関するブックリスト生徒用2022.12.15.xlsx
キーワード1 ヨーロッパ キーワード2 EU キーワード3 生徒授業 授業計画・指導案等 チャレンジ!生徒授業.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 篠塚昭司 授業者コメント この生徒授業は単なる調べ・発表学習ではなく、自ら担当国の課題を見つけ解決をめざす問題解決型学習として実施しました。そのため、生徒たちの学習過程は、「情報収集」(担当国の調べ学習)→「学習問題を設定」(授業で伝えたい担当国の特色を発見)→「学習指導案作成」(担当国の特色をどのように伝えていくか)→「生徒授業実践」の流れで進めていきました。
学習過程の中で、特に学校図書館との連携が有効だったのは、「情報収集」の場面です。本当に興味を持った「学習問題を設定」するためには、できるだけ多くの「情報取集」をすることが必要になります。そこで、図書館司書の先生にお願いし、他の附属学校の図書館からもヨーロッパ州の国々に関する様々な本を集めていただきました。とかく、現代の中学生たちは「情報収集」の際に、インターネットを活用しがちですが、まずは情報源が明確で信頼性が高い本の情報を重要視する生徒になってほしいという思いからでした。その後、図書館司書の先生に、情報のファクトチェック方法やインターネットサイトや新聞データベースの検索方法といった多様な収集手段についてもお話していただいた上で、タブレットPCの活用を始めました。このように、生徒たちが多角的・多面的な「情報収集」を行ったことが、今回の生徒授業成功のカギとなった気がしています。 司書・司書教諭コメント この授業の時は、他教科でも図書館を使う授業があったため、用意した資料は、通しナンバーをつけてさらには国別の見出しをつけて社会科教室に持ち込みんだ。リストに載せ忘れた資料が、あとからいくつか見つかったので追加コーナーも作った。
授業の冒頭のみ顔を出したが、実際の様子や生徒授業の様子を見学できず、残念だったが、充実した授業が行われたようで嬉しく思う。生徒授業から半年も過ぎてしまったが、図書館に来ていた現2年生に、生徒授業をやってみての感想を聞いてみた。「生徒授業は、自分で調べるのでその国に対する興味が凄く沸いた。他のグループの授業も、中学生ならではの視点があってとても面白かった。」とのこと。
早い時期から、授業内容を伝えていただき、資料の準備を依頼されていたので、余裕をもって他附属の図書館から借りて提供することができた。一人一台端末になり、ネットの情報も使うことが増えたので、必ずその際に注意してほしいことは図書館からも伝えるように心がけている。ブックリストも、今回はTeams上から提供したので、使えるサイトはリンクを貼れるのは、ICT活用の利点と言える。今年の生徒授業はぜひ見学に行きたいと思う。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2023.9.29 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3863490 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0430 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 社会 |
| 単元 | 世界の諸地域「ヨーロッパ州」 |
| 対象学年 | 中1 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供・レファレンス |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 3学期に生徒による授業を計画しているので、ヨーロッパに関する資料を集めてほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 生徒は3~4人グループで、「なぜヨーロッパの国々は一つにまとまろうとしているのか、果たしてまとまることはできるのか。」という単元の学習課題を設定し、3~4人のグループで自分たちの作った学習指導案をもとに授業を行う。まずは図書資料を調べるところからスタートしたい。 |
| 提示資料 | 提示資料の1と2、中学生の学習に適した資料なので、附属学校から借りて副本を用意した。 |
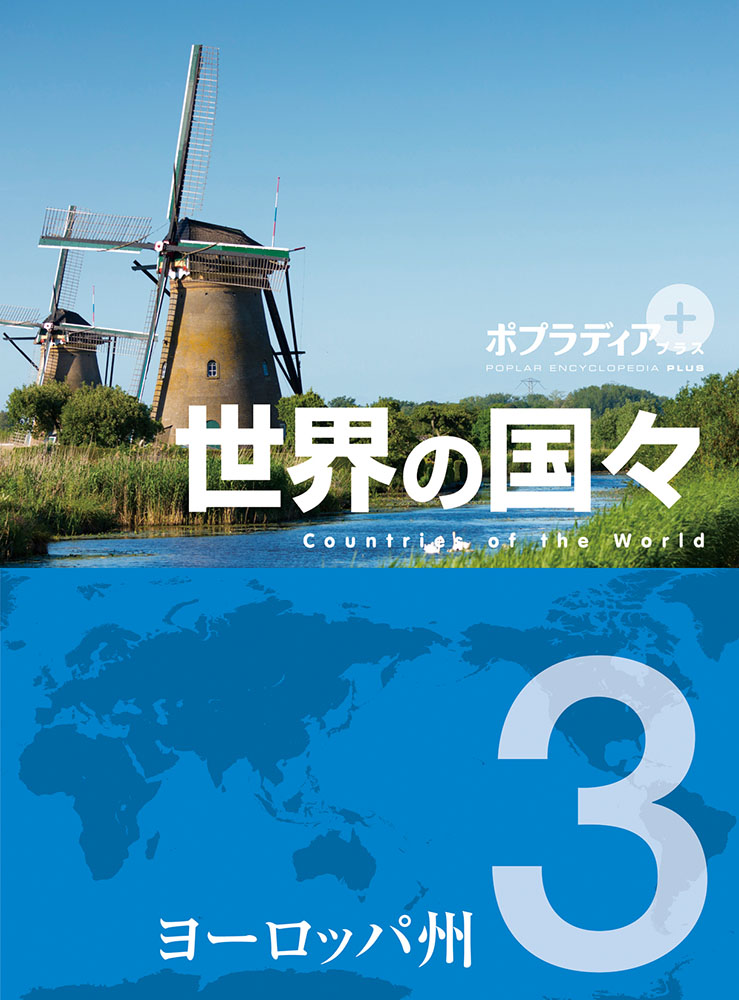 | 『ポプラディアプラス3 世界の国々 ヨーロッパ州3 ポプラ社 2019 児童生徒を対象とした学習用事典。最初にヨーロッパ全体の自然・歴史・文化・産業について書かれていて、そのあとは、ヨーロッパ各国について、コンパクトにまとまっている。中学生が調べるには、最適な一冊。 |
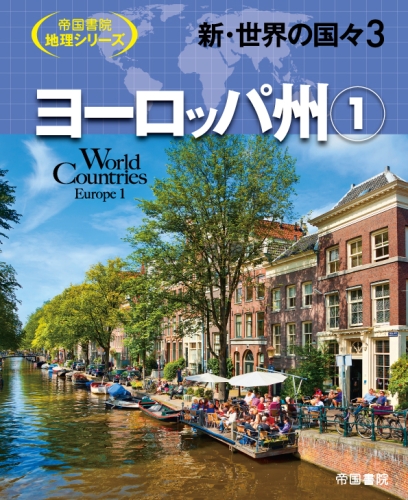 | 『帝国書院地理シリーズ 新・世界の国々3ヨーロッパ州⓵』兼子純監修 帝国書院 2020 地理の教科書も出している帝国書院のシリーズだけに、教科書に沿った学習には最適。2012年版も蔵書にあるので、あわせて提供したが、どこが変わっているかまで注目してくれたのかは、わからない。地理資料は、できるだけ新しいものが必要になるので悩ましい。 |
 | 『国境で読み解くヨーロッパ:境界の地理紀行』加賀美雅弘著 朝倉書店 2022 今回の学習にあたって、使えるかなと思って新たに買い足した資料の1冊。ヨーロッパで地理学の調査をし続けてきた著者が、国境をキーワードに、歴史、民族問題、観光、多様性、鉄道などのテーマを掘り下げた1冊。ヨーロッパは国境だらけで、国境は見どころが多いという。この本で仕入れた豆知識を、生徒授業で披露してくれたら嬉しいが…。ただし、読むには時間がかかる資料かもしれない。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | ヨーロッパに関するブックリスト生徒用2022.12.15.xlsx |
| キーワード1 | ヨーロッパ |
| キーワード2 | EU |
| キーワード3 | 生徒授業 |
| 授業計画・指導案等 | チャレンジ!生徒授業.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 篠塚昭司 |
| 授業者コメント | この生徒授業は単なる調べ・発表学習ではなく、自ら担当国の課題を見つけ解決をめざす問題解決型学習として実施しました。そのため、生徒たちの学習過程は、「情報収集」(担当国の調べ学習)→「学習問題を設定」(授業で伝えたい担当国の特色を発見)→「学習指導案作成」(担当国の特色をどのように伝えていくか)→「生徒授業実践」の流れで進めていきました。 学習過程の中で、特に学校図書館との連携が有効だったのは、「情報収集」の場面です。本当に興味を持った「学習問題を設定」するためには、できるだけ多くの「情報取集」をすることが必要になります。そこで、図書館司書の先生にお願いし、他の附属学校の図書館からもヨーロッパ州の国々に関する様々な本を集めていただきました。とかく、現代の中学生たちは「情報収集」の際に、インターネットを活用しがちですが、まずは情報源が明確で信頼性が高い本の情報を重要視する生徒になってほしいという思いからでした。その後、図書館司書の先生に、情報のファクトチェック方法やインターネットサイトや新聞データベースの検索方法といった多様な収集手段についてもお話していただいた上で、タブレットPCの活用を始めました。このように、生徒たちが多角的・多面的な「情報収集」を行ったことが、今回の生徒授業成功のカギとなった気がしています。 |
| 司書・司書教諭コメント | この授業の時は、他教科でも図書館を使う授業があったため、用意した資料は、通しナンバーをつけてさらには国別の見出しをつけて社会科教室に持ち込みんだ。リストに載せ忘れた資料が、あとからいくつか見つかったので追加コーナーも作った。 授業の冒頭のみ顔を出したが、実際の様子や生徒授業の様子を見学できず、残念だったが、充実した授業が行われたようで嬉しく思う。生徒授業から半年も過ぎてしまったが、図書館に来ていた現2年生に、生徒授業をやってみての感想を聞いてみた。「生徒授業は、自分で調べるのでその国に対する興味が凄く沸いた。他のグループの授業も、中学生ならではの視点があってとても面白かった。」とのこと。 早い時期から、授業内容を伝えていただき、資料の準備を依頼されていたので、余裕をもって他附属の図書館から借りて提供することができた。一人一台端末になり、ネットの情報も使うことが増えたので、必ずその際に注意してほしいことは図書館からも伝えるように心がけている。ブックリストも、今回はTeams上から提供したので、使えるサイトはリンクを貼れるのは、ICT活用の利点と言える。今年の生徒授業はぜひ見学に行きたいと思う。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
| 事例作成日 | 2023.9.29 |
| 事例作成者氏名 | 村上恭子 |
記入者:村上

























