お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0464 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 読む・・・物語を読んで考えたことを、伝え合おう 対象学年 高学年 活用・支援の種類 リテラチャーサークルの進行・・・ リテラチャーサークルとはアメリカの学校現場で開発された読書会である。日本には足立幸子氏によって紹介された。授業時間1時間の中で、読み、書き、話し合いをする。4,5名のグループで、役割を決め、その時間読むところまで読み、、5時間ほどかけて完読する。そして最後に自分たちが読んだ本の魅力を紹介する。自分では気づかなかったことを友だちの感想から気づかされるなど話し合いが楽しい。司書は本を選び、ブックトークをして、読みたい本を選ばせる。 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) リテラチャーサークルの説明と本の紹介 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 読書指導 「リテラチャーサークル」
提示資料 易しいものもとりまぜて、100ページから200ページ前後の本を選んだ。 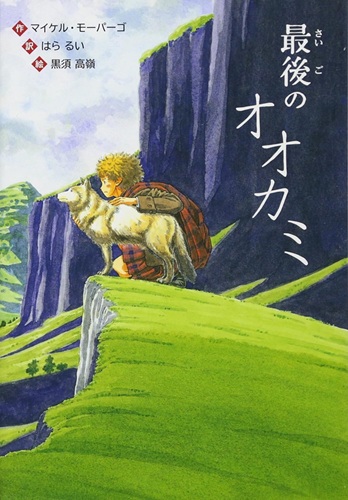
『最後のオオカミ』マイケル・モーパーゴ/作 文研出版 978-4-580-82337-2 2017年
マイケルは自分の家系を調べるうちに先祖のロビーが遺した遺言書にであう。それは「最後のオオカミ」という回想録だった。戦争にまきこまれ、親を亡くしたロビーが一匹のオオカミと心を通わせ生きていく。 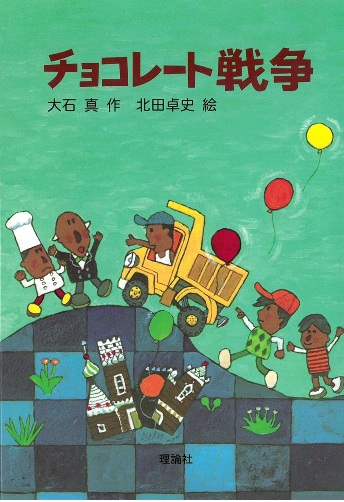
『チョコレート戦争』 大石 真/作 理論社 4-652-00502-4 1999年
洋菓子店のショーウインドウを割った犯人にされた子どもたち。子どもたちは作戦を練り抗議の戦いを挑む。 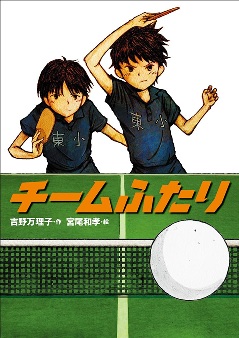
『チームふたり』吉野 万里子/作 学習研究社 978-4-05-202895-3 2007年
卓球部キャプテンの大地は小学校最後の試合で最強のダブルスを組みたかったのに、5年の純と組むことになりがっかり。家に帰るとそれどころでない問題が起こっていた。 参考資料(含HP) 参考資料リンク https:// ブックリスト リテラチャーサークル リスト.pdf
キーワード1 リテラチャーサークル キーワード2 読書 キーワード3 授業計画・指導案等 ブッククラブ 役割シート 2023-結合済み.pdf 児童・生徒の作品 https:// 授業者 吉田一博 授業者コメント リテラチャーサークルを終えて
私は読書が大好きな子どもだった。本の世界に入り込むのが好きで、登場人物の真似をしてトイレで本を読む時期もあった。LCを知ったのは恥ずかしながら大人になって…つい先日のことである。実際にやってみて真っ先に思ったことは、「子どものころにしたかった。」であった。
好きなマンガやアニメ、テレビ番組の話で盛り上がったことは何度もあったが、好きな本、読んだ本の話で盛り上がったことはほとんどないからである。
私にとって、目の前で本を読んだ感想を語り合える関係がうらやましいと思った。本は一人で読むものという考えがひっくり返った瞬間だった。
同じ本を読んでも、考え方や感じ方の違いがあることがとてもよく分かった。一つの場面を二つ以上の視点から見られる。他の意見を聞いて、もう一度本を読みたくなるだろうと感じた。
本を読んで感じたことを、自分の思うように友達に発することができる喜び、同じ本を読んだ仲間の感じたことを聞いて、共感したり新しい発見をしたりできる喜びを味わうことができる良さをLCは持っていると感じた。(以上、自分の感想)
本を読むことが好きな子が考えたり感じたりしたことを言葉に発したとき、本を読むのは少し苦手な子や、読むのは好きだけど話をするのが得意ではない子が「それ、すごくよく分かる」とか、「そうそう」など納得、共感している様子が見られてうれしくなった。
あまり普段の授業で発表をしない子が、周囲とは異なる視点で内容を捉えて意見を述べたとき、「そういう考えもあるのか」「ということは、○○かもしれないね」などの会話が盛り上がっている様子が見られ、大変興味深かった。
一度本を読むだけで、話合いを行った人数分だけの回数本を読んだ経験になりそうだと感じられた。そして、もう一度本を読みたくなる効果があるように感じられた。(以上、教師目線で感じたこと)
司書・司書教諭コメント 読解力はただ本を読めばつくものではないと思う。読みの視点、ヒントをもとに主体的に読むこの読書法はもっと広がっていいと考える。また、児童がお互いの考えを述べていくことで尊重しあう態度も見受けられた。読書の苦手な児童も友だちの話に助けられて、完読し、自信をつけることができた。 情報提供校 新居浜市立中萩小学校 事例作成日 事例作成 2025年3月/授業実践 2024年5月 事例作成者氏名 清水 広美 学校司書
記入者:金澤
カウンタ
3863504 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0464 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 読む・・・物語を読んで考えたことを、伝え合おう 対象学年 高学年 活用・支援の種類 リテラチャーサークルの進行・・・ リテラチャーサークルとはアメリカの学校現場で開発された読書会である。日本には足立幸子氏によって紹介された。授業時間1時間の中で、読み、書き、話し合いをする。4,5名のグループで、役割を決め、その時間読むところまで読み、、5時間ほどかけて完読する。そして最後に自分たちが読んだ本の魅力を紹介する。自分では気づかなかったことを友だちの感想から気づかされるなど話し合いが楽しい。司書は本を選び、ブックトークをして、読みたい本を選ばせる。 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) リテラチャーサークルの説明と本の紹介 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 読書指導 「リテラチャーサークル」
提示資料 易しいものもとりまぜて、100ページから200ページ前後の本を選んだ。 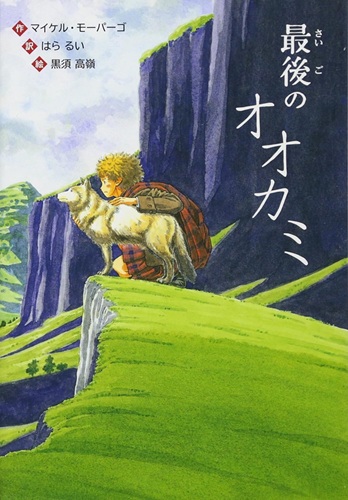
『最後のオオカミ』マイケル・モーパーゴ/作 文研出版 978-4-580-82337-2 2017年
マイケルは自分の家系を調べるうちに先祖のロビーが遺した遺言書にであう。それは「最後のオオカミ」という回想録だった。戦争にまきこまれ、親を亡くしたロビーが一匹のオオカミと心を通わせ生きていく。 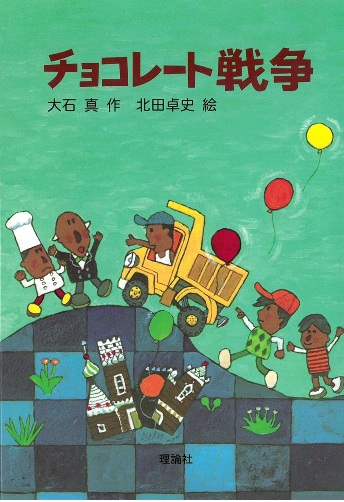
『チョコレート戦争』 大石 真/作 理論社 4-652-00502-4 1999年
洋菓子店のショーウインドウを割った犯人にされた子どもたち。子どもたちは作戦を練り抗議の戦いを挑む。 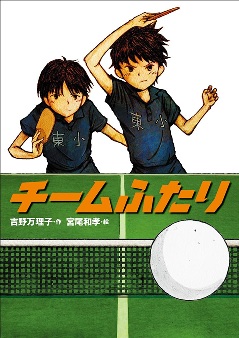
『チームふたり』吉野 万里子/作 学習研究社 978-4-05-202895-3 2007年
卓球部キャプテンの大地は小学校最後の試合で最強のダブルスを組みたかったのに、5年の純と組むことになりがっかり。家に帰るとそれどころでない問題が起こっていた。 参考資料(含HP) 参考資料リンク https:// ブックリスト リテラチャーサークル リスト.pdf
キーワード1 リテラチャーサークル キーワード2 読書 キーワード3 授業計画・指導案等 ブッククラブ 役割シート 2023-結合済み.pdf 児童・生徒の作品 https:// 授業者 吉田一博 授業者コメント リテラチャーサークルを終えて
私は読書が大好きな子どもだった。本の世界に入り込むのが好きで、登場人物の真似をしてトイレで本を読む時期もあった。LCを知ったのは恥ずかしながら大人になって…つい先日のことである。実際にやってみて真っ先に思ったことは、「子どものころにしたかった。」であった。
好きなマンガやアニメ、テレビ番組の話で盛り上がったことは何度もあったが、好きな本、読んだ本の話で盛り上がったことはほとんどないからである。
私にとって、目の前で本を読んだ感想を語り合える関係がうらやましいと思った。本は一人で読むものという考えがひっくり返った瞬間だった。
同じ本を読んでも、考え方や感じ方の違いがあることがとてもよく分かった。一つの場面を二つ以上の視点から見られる。他の意見を聞いて、もう一度本を読みたくなるだろうと感じた。
本を読んで感じたことを、自分の思うように友達に発することができる喜び、同じ本を読んだ仲間の感じたことを聞いて、共感したり新しい発見をしたりできる喜びを味わうことができる良さをLCは持っていると感じた。(以上、自分の感想)
本を読むことが好きな子が考えたり感じたりしたことを言葉に発したとき、本を読むのは少し苦手な子や、読むのは好きだけど話をするのが得意ではない子が「それ、すごくよく分かる」とか、「そうそう」など納得、共感している様子が見られてうれしくなった。
あまり普段の授業で発表をしない子が、周囲とは異なる視点で内容を捉えて意見を述べたとき、「そういう考えもあるのか」「ということは、○○かもしれないね」などの会話が盛り上がっている様子が見られ、大変興味深かった。
一度本を読むだけで、話合いを行った人数分だけの回数本を読んだ経験になりそうだと感じられた。そして、もう一度本を読みたくなる効果があるように感じられた。(以上、教師目線で感じたこと)
司書・司書教諭コメント 読解力はただ本を読めばつくものではないと思う。読みの視点、ヒントをもとに主体的に読むこの読書法はもっと広がっていいと考える。また、児童がお互いの考えを述べていくことで尊重しあう態度も見受けられた。読書の苦手な児童も友だちの話に助けられて、完読し、自信をつけることができた。 情報提供校 新居浜市立中萩小学校 事例作成日 事例作成 2025年3月/授業実践 2024年5月 事例作成者氏名 清水 広美 学校司書
記入者:金澤
カウンタ
3863504 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0464 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 読む・・・物語を読んで考えたことを、伝え合おう |
| 対象学年 | 高学年 |
| 活用・支援の種類 | リテラチャーサークルの進行・・・ リテラチャーサークルとはアメリカの学校現場で開発された読書会である。日本には足立幸子氏によって紹介された。授業時間1時間の中で、読み、書き、話し合いをする。4,5名のグループで、役割を決め、その時間読むところまで読み、、5時間ほどかけて完読する。そして最後に自分たちが読んだ本の魅力を紹介する。自分では気づかなかったことを友だちの感想から気づかされるなど話し合いが楽しい。司書は本を選び、ブックトークをして、読みたい本を選ばせる。 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | リテラチャーサークルの説明と本の紹介 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 読書指導 「リテラチャーサークル」 |
| 提示資料 | 易しいものもとりまぜて、100ページから200ページ前後の本を選んだ。 |
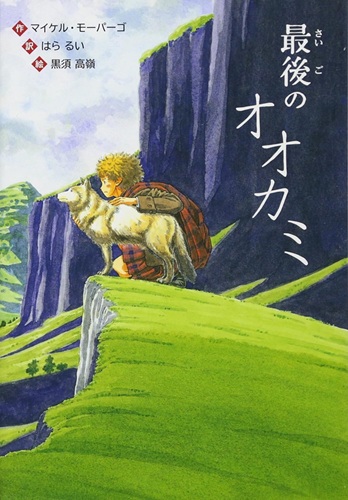 | 『最後のオオカミ』マイケル・モーパーゴ/作 文研出版 978-4-580-82337-2 2017年 マイケルは自分の家系を調べるうちに先祖のロビーが遺した遺言書にであう。それは「最後のオオカミ」という回想録だった。戦争にまきこまれ、親を亡くしたロビーが一匹のオオカミと心を通わせ生きていく。 |
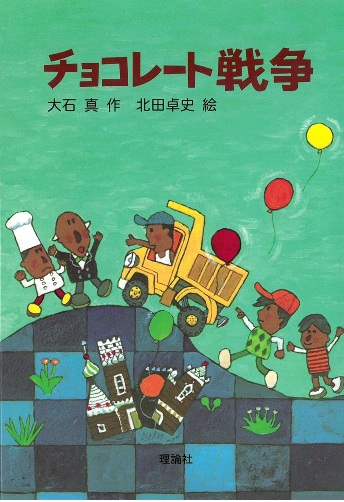 | 『チョコレート戦争』 大石 真/作 理論社 4-652-00502-4 1999年 洋菓子店のショーウインドウを割った犯人にされた子どもたち。子どもたちは作戦を練り抗議の戦いを挑む。 |
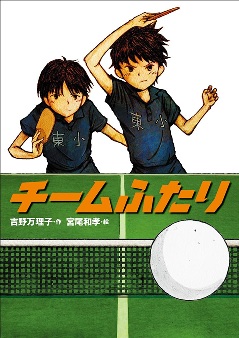 | 『チームふたり』吉野 万里子/作 学習研究社 978-4-05-202895-3 2007年 卓球部キャプテンの大地は小学校最後の試合で最強のダブルスを組みたかったのに、5年の純と組むことになりがっかり。家に帰るとそれどころでない問題が起こっていた。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | https:// |
| ブックリスト | リテラチャーサークル リスト.pdf |
| キーワード1 | リテラチャーサークル |
| キーワード2 | 読書 |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | ブッククラブ 役割シート 2023-結合済み.pdf |
| 児童・生徒の作品 | https:// |
| 授業者 | 吉田一博 |
| 授業者コメント | リテラチャーサークルを終えて 私は読書が大好きな子どもだった。本の世界に入り込むのが好きで、登場人物の真似をしてトイレで本を読む時期もあった。LCを知ったのは恥ずかしながら大人になって…つい先日のことである。実際にやってみて真っ先に思ったことは、「子どものころにしたかった。」であった。 好きなマンガやアニメ、テレビ番組の話で盛り上がったことは何度もあったが、好きな本、読んだ本の話で盛り上がったことはほとんどないからである。 私にとって、目の前で本を読んだ感想を語り合える関係がうらやましいと思った。本は一人で読むものという考えがひっくり返った瞬間だった。 同じ本を読んでも、考え方や感じ方の違いがあることがとてもよく分かった。一つの場面を二つ以上の視点から見られる。他の意見を聞いて、もう一度本を読みたくなるだろうと感じた。 本を読んで感じたことを、自分の思うように友達に発することができる喜び、同じ本を読んだ仲間の感じたことを聞いて、共感したり新しい発見をしたりできる喜びを味わうことができる良さをLCは持っていると感じた。(以上、自分の感想) 本を読むことが好きな子が考えたり感じたりしたことを言葉に発したとき、本を読むのは少し苦手な子や、読むのは好きだけど話をするのが得意ではない子が「それ、すごくよく分かる」とか、「そうそう」など納得、共感している様子が見られてうれしくなった。 あまり普段の授業で発表をしない子が、周囲とは異なる視点で内容を捉えて意見を述べたとき、「そういう考えもあるのか」「ということは、○○かもしれないね」などの会話が盛り上がっている様子が見られ、大変興味深かった。 一度本を読むだけで、話合いを行った人数分だけの回数本を読んだ経験になりそうだと感じられた。そして、もう一度本を読みたくなる効果があるように感じられた。(以上、教師目線で感じたこと) |
| 司書・司書教諭コメント | 読解力はただ本を読めばつくものではないと思う。読みの視点、ヒントをもとに主体的に読むこの読書法はもっと広がっていいと考える。また、児童がお互いの考えを述べていくことで尊重しあう態度も見受けられた。読書の苦手な児童も友だちの話に助けられて、完読し、自信をつけることができた。 |
| 情報提供校 | 新居浜市立中萩小学校 |
| 事例作成日 | 事例作成 2025年3月/授業実践 2024年5月 |
| 事例作成者氏名 | 清水 広美 学校司書 |
記入者:金澤

























