お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0466 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 クマゼミの増加の原因を探る(光村) 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供 授業相談 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 表やグラフの見方や、データリテラシーについて書かれた資料を見せてほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 表やグラフが多用されている「クマゼミの増加の原因を探る」という説明文を学習したので、生徒に、実際に異なる立場からグラフを書いてみることで、データリテラシーについて学ぶ機会にしたい。
提示資料 
知っておきたい!統計のオモテとウラ
統計とうまくつき合うために
神林博史 カンバヤシヒロシ (著)
ISBN:978-4-469-27015-0
大修館書店 2023
数学が苦手だったという著者が、統計の基礎知識と、統計との付き合い方を楽しく解説した1冊。読み物のように読めるのも特徴。今回のねらいにぴったりの1冊だったそうだ。 
表とグラフを使おう3
自由研究・プレゼンにチャレンジ
渡辺 美智子 (監修)
ISBN:978-4-8113-2112-7
汐文社 2015
3巻シリーズ。いろいろな表やグラフの読み方についてわかりやすく解説している。 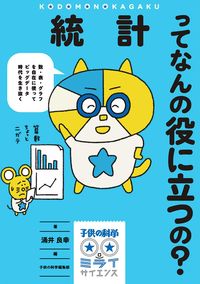
統計っとなんの役に立つの?:数・表・グラフを自在に使ってビッグデータ時代を生き抜く
涌井 良幸
子供の科学編集部 (編)
ISBN:978-4-416-51817-5
誠文堂新光社 2018年
子供の科学★ミライサイエンスシリーズ第3弾 ニュースや広告で使われるアンケート結果や、サイコロやカードゲームで日常よく目にする身近な例で、統計について基本的なことを学ぶ1冊。 参考資料(含HP) 参考資料リンク https://app.bookreach.org/curation?id=108 ブックリスト データリテラシーを学ぶブックリスト.xlsx
キーワード1 表 キーワード2 グラフ キーワード3 データリテラシー 授業計画・指導案等 図やグラフの役割ってなぁに.pdf 児童・生徒の作品 https:// 授業者 阿部由美(国語科教諭&司書教諭) 授業者コメント 表やグラフがどのような役割を果たすのか、なんとなく知っていて、使っていても、それを改めて問われると言葉で説明するのは難しいらしい。ということがわかりました。また、縦軸の特性を理解して取り組むと立場を変えてグラフを作る作業でおもしろい作品ができあがってきました。
図やグラフをレポートや発表に入れ込む機会が増えている子どもたちが授業の最後の感想で「3Dのグラフで意図せず人を騙していたかもしれない」 「印象操作をしていたかもしれない」と振り返ったり気づいたりしている様子が見られて授業者も楽しかったです。 司書・司書教諭コメント 授業の前日、資料を探しに来た先生に、どのような授業を考えているのかを聞き取りながら、関連書籍を3類と4類の本棚から抜いて手渡しました。100分授業の前半で、教科書教材を学習し、後半は表やグラフの特性を知り、実際にグラフを書くというワークをさせたいとのこと。
10数冊の本をパラパラ読み、比較した上で4冊の本を借りていきました。翌日の授業を1クラスだけ見学に行きました。普段何気なくみている統計データですが、このようにじっくり考える機会は意外と少ない気がします。
最後の15分ほどで、テストの点数を表の数値を使って、違う目的で2通りの折れ線グラフを書くという課題にグループで取り組み、その違いが腑に落ちたようです。この学年は数学で統計コンテストに参加していましたが、国語の授業でデータリテラシーについて学ぶことは大切だと感じました。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2025.5.31 事例作成者氏名 村上恭子(学校司書)
記入者:村上
カウンタ
3863457 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0466 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 クマゼミの増加の原因を探る(光村) 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供 授業相談 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 表やグラフの見方や、データリテラシーについて書かれた資料を見せてほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 表やグラフが多用されている「クマゼミの増加の原因を探る」という説明文を学習したので、生徒に、実際に異なる立場からグラフを書いてみることで、データリテラシーについて学ぶ機会にしたい。
提示資料 
知っておきたい!統計のオモテとウラ
統計とうまくつき合うために
神林博史 カンバヤシヒロシ (著)
ISBN:978-4-469-27015-0
大修館書店 2023
数学が苦手だったという著者が、統計の基礎知識と、統計との付き合い方を楽しく解説した1冊。読み物のように読めるのも特徴。今回のねらいにぴったりの1冊だったそうだ。 
表とグラフを使おう3
自由研究・プレゼンにチャレンジ
渡辺 美智子 (監修)
ISBN:978-4-8113-2112-7
汐文社 2015
3巻シリーズ。いろいろな表やグラフの読み方についてわかりやすく解説している。 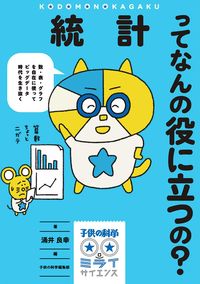
統計っとなんの役に立つの?:数・表・グラフを自在に使ってビッグデータ時代を生き抜く
涌井 良幸
子供の科学編集部 (編)
ISBN:978-4-416-51817-5
誠文堂新光社 2018年
子供の科学★ミライサイエンスシリーズ第3弾 ニュースや広告で使われるアンケート結果や、サイコロやカードゲームで日常よく目にする身近な例で、統計について基本的なことを学ぶ1冊。 参考資料(含HP) 参考資料リンク https://app.bookreach.org/curation?id=108 ブックリスト データリテラシーを学ぶブックリスト.xlsx
キーワード1 表 キーワード2 グラフ キーワード3 データリテラシー 授業計画・指導案等 図やグラフの役割ってなぁに.pdf 児童・生徒の作品 https:// 授業者 阿部由美(国語科教諭&司書教諭) 授業者コメント 表やグラフがどのような役割を果たすのか、なんとなく知っていて、使っていても、それを改めて問われると言葉で説明するのは難しいらしい。ということがわかりました。また、縦軸の特性を理解して取り組むと立場を変えてグラフを作る作業でおもしろい作品ができあがってきました。
図やグラフをレポートや発表に入れ込む機会が増えている子どもたちが授業の最後の感想で「3Dのグラフで意図せず人を騙していたかもしれない」 「印象操作をしていたかもしれない」と振り返ったり気づいたりしている様子が見られて授業者も楽しかったです。 司書・司書教諭コメント 授業の前日、資料を探しに来た先生に、どのような授業を考えているのかを聞き取りながら、関連書籍を3類と4類の本棚から抜いて手渡しました。100分授業の前半で、教科書教材を学習し、後半は表やグラフの特性を知り、実際にグラフを書くというワークをさせたいとのこと。
10数冊の本をパラパラ読み、比較した上で4冊の本を借りていきました。翌日の授業を1クラスだけ見学に行きました。普段何気なくみている統計データですが、このようにじっくり考える機会は意外と少ない気がします。
最後の15分ほどで、テストの点数を表の数値を使って、違う目的で2通りの折れ線グラフを書くという課題にグループで取り組み、その違いが腑に落ちたようです。この学年は数学で統計コンテストに参加していましたが、国語の授業でデータリテラシーについて学ぶことは大切だと感じました。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2025.5.31 事例作成者氏名 村上恭子(学校司書)
記入者:村上
カウンタ
3863457 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0466 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | クマゼミの増加の原因を探る(光村) |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 授業相談 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 表やグラフの見方や、データリテラシーについて書かれた資料を見せてほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 表やグラフが多用されている「クマゼミの増加の原因を探る」という説明文を学習したので、生徒に、実際に異なる立場からグラフを書いてみることで、データリテラシーについて学ぶ機会にしたい。 |
| 提示資料 | |
 | 知っておきたい!統計のオモテとウラ 統計とうまくつき合うために 神林博史 カンバヤシヒロシ (著) ISBN:978-4-469-27015-0 大修館書店 2023 数学が苦手だったという著者が、統計の基礎知識と、統計との付き合い方を楽しく解説した1冊。読み物のように読めるのも特徴。今回のねらいにぴったりの1冊だったそうだ。 |
 | 表とグラフを使おう3 自由研究・プレゼンにチャレンジ 渡辺 美智子 (監修) ISBN:978-4-8113-2112-7 汐文社 2015 3巻シリーズ。いろいろな表やグラフの読み方についてわかりやすく解説している。 |
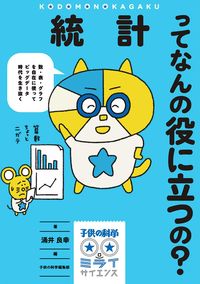 | 統計っとなんの役に立つの?:数・表・グラフを自在に使ってビッグデータ時代を生き抜く 涌井 良幸 子供の科学編集部 (編) ISBN:978-4-416-51817-5 誠文堂新光社 2018年 子供の科学★ミライサイエンスシリーズ第3弾 ニュースや広告で使われるアンケート結果や、サイコロやカードゲームで日常よく目にする身近な例で、統計について基本的なことを学ぶ1冊。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | https://app.bookreach.org/curation?id=108 |
| ブックリスト | データリテラシーを学ぶブックリスト.xlsx |
| キーワード1 | 表 |
| キーワード2 | グラフ |
| キーワード3 | データリテラシー |
| 授業計画・指導案等 | 図やグラフの役割ってなぁに.pdf |
| 児童・生徒の作品 | https:// |
| 授業者 | 阿部由美(国語科教諭&司書教諭) |
| 授業者コメント | 表やグラフがどのような役割を果たすのか、なんとなく知っていて、使っていても、それを改めて問われると言葉で説明するのは難しいらしい。ということがわかりました。また、縦軸の特性を理解して取り組むと立場を変えてグラフを作る作業でおもしろい作品ができあがってきました。 図やグラフをレポートや発表に入れ込む機会が増えている子どもたちが授業の最後の感想で「3Dのグラフで意図せず人を騙していたかもしれない」 「印象操作をしていたかもしれない」と振り返ったり気づいたりしている様子が見られて授業者も楽しかったです。 |
| 司書・司書教諭コメント | 授業の前日、資料を探しに来た先生に、どのような授業を考えているのかを聞き取りながら、関連書籍を3類と4類の本棚から抜いて手渡しました。100分授業の前半で、教科書教材を学習し、後半は表やグラフの特性を知り、実際にグラフを書くというワークをさせたいとのこと。 10数冊の本をパラパラ読み、比較した上で4冊の本を借りていきました。翌日の授業を1クラスだけ見学に行きました。普段何気なくみている統計データですが、このようにじっくり考える機会は意外と少ない気がします。 最後の15分ほどで、テストの点数を表の数値を使って、違う目的で2通りの折れ線グラフを書くという課題にグループで取り組み、その違いが腑に落ちたようです。この学年は数学で統計コンテストに参加していましたが、国語の授業でデータリテラシーについて学ぶことは大切だと感じました。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
| 事例作成日 | 2025.5.31 |
| 事例作成者氏名 | 村上恭子(学校司書) |
記入者:村上

























