お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」は終了いたしました。当日参加してくださった皆様、配信をご覧になった皆様、こちらの参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。また、2月になりましたら、改めて視聴をご希望の皆さまには、申し込めるように整えます。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は埼玉県立松伏高等学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0045 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 「つながる/ つなげる読書~図書館との協働」 対象学年 中1 活用・支援の種類 図書館からは、分類のしくみ・科学の本の選び方・等の指導 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 「動物の睡眠」を学習したあとなので、物語や小説ではなく、説明文を読ませたいのですが・・・。
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 具体的には、科学の本を読んで、自分が一番驚いたことを、200文字にまとめるという作業(リライト)をし、それをもとに、2学期に1分間スピーチをさせたいとのこと。そこで、学校司書からは、「科学の本」を読むことの意味と面白さを伝えたうえで、4類の分類のしくみ、科学の本の選び方などを話し、自由に本を選んでもらうことに。また、選んだ本をワークシートを書き込んでもらったあとで、次の一冊をどうやって探すかまでを宿題としたので、そのさがし方も簡単に説明することにした。
提示資料 理科読を薦める本、スピーチに役立つ本、分類のしくみを理解する上で役立つ本の3冊。 
『理科読をはじめよう』 滝川洋二編 岩波書店 2010年・・子どもたちの科学離れを憂う人たちの思いが詰まった一冊。子どもの「なぜ」を大切にすることは、探求心を育み世界を広げること。だからこそ科学の本の面白さを伝えたい。様々な現場で実際に子どもたちに科学の本を手渡している人たちの日々の実践も書かれた好著。
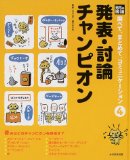
『発表・討論チャンピオン;調べて、まとめて、コミュニケーション4』 中川一史・高木まさき 監修 光村教育図書 2003・・・この巻ではいろいろな発表の方法や討論のしかたを、具体的な例をあげて紹介している。今回はスピーチ、ショー・アンド・テルを参考にして、生徒にスピーチ原稿のつくりかたや話し方を指導。

『調べ学習の基礎の基礎;だれでもできる赤木かん子の魔法の図書館学』 赤木かん子 著ポプラ社 2006・・・小学生向けに、調べるための基本をやさしく解説した一冊。左ページに解説、右ページにワークシートという構成で、見開きをコピーすればそのまま授業で使えるという親切なつくりの本。今回直接使用したわけではないが、分類の仕組みを話すうえで参考にした本の1冊。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 生徒が選んだ科学本リスト.xls
キーワード1 科学読み物 キーワード2 分類 キーワード3 スピーチ 授業計画・指導案等 「つなげる読書」授業.pdf 児童・生徒の作品 授業者 渡邊裕 授業者コメント 近日中にアップします。 司書・司書教諭コメント 夏休み前からずっと手元に置いていた科学の本をもとに、1分間スピーチをするという日に見学させてもらった。日頃特定の生徒しか手にとらない4類の本が、このように広く読まれたことだけでも司書としては嬉しい。そしてやはり選んだ本が面白いと思えた生徒のスピーチは、内容が濃いように感じた。図書館というと、物語の本を読むというイメージしか持っていない生徒に、科学の本のおもしろさが多少なりとも伝わり、今後の読書の幅が広がるきっかけにはなったのでは。後日生徒に書いてもらったアンケートをみせてもらったところ、多くの生徒が科学の本の面白さに気づき、つながりを考えて本を選ぶという視点を持てたこと、また自分の思いをスピーチという形で表現することの難しさや楽しさを綴っていた。こういう形で図書館の資料が役立つ企画はとてもいいのではと感じた。
情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2010年12月 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3800287 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」は終了いたしました。当日参加してくださった皆様、配信をご覧になった皆様、こちらの参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。また、2月になりましたら、改めて視聴をご希望の皆さまには、申し込めるように整えます。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は埼玉県立松伏高等学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0045 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 「つながる/ つなげる読書~図書館との協働」 対象学年 中1 活用・支援の種類 図書館からは、分類のしくみ・科学の本の選び方・等の指導 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 「動物の睡眠」を学習したあとなので、物語や小説ではなく、説明文を読ませたいのですが・・・。
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 具体的には、科学の本を読んで、自分が一番驚いたことを、200文字にまとめるという作業(リライト)をし、それをもとに、2学期に1分間スピーチをさせたいとのこと。そこで、学校司書からは、「科学の本」を読むことの意味と面白さを伝えたうえで、4類の分類のしくみ、科学の本の選び方などを話し、自由に本を選んでもらうことに。また、選んだ本をワークシートを書き込んでもらったあとで、次の一冊をどうやって探すかまでを宿題としたので、そのさがし方も簡単に説明することにした。
提示資料 理科読を薦める本、スピーチに役立つ本、分類のしくみを理解する上で役立つ本の3冊。 
『理科読をはじめよう』 滝川洋二編 岩波書店 2010年・・子どもたちの科学離れを憂う人たちの思いが詰まった一冊。子どもの「なぜ」を大切にすることは、探求心を育み世界を広げること。だからこそ科学の本の面白さを伝えたい。様々な現場で実際に子どもたちに科学の本を手渡している人たちの日々の実践も書かれた好著。
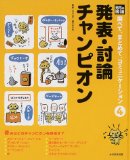
『発表・討論チャンピオン;調べて、まとめて、コミュニケーション4』 中川一史・高木まさき 監修 光村教育図書 2003・・・この巻ではいろいろな発表の方法や討論のしかたを、具体的な例をあげて紹介している。今回はスピーチ、ショー・アンド・テルを参考にして、生徒にスピーチ原稿のつくりかたや話し方を指導。

『調べ学習の基礎の基礎;だれでもできる赤木かん子の魔法の図書館学』 赤木かん子 著ポプラ社 2006・・・小学生向けに、調べるための基本をやさしく解説した一冊。左ページに解説、右ページにワークシートという構成で、見開きをコピーすればそのまま授業で使えるという親切なつくりの本。今回直接使用したわけではないが、分類の仕組みを話すうえで参考にした本の1冊。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 生徒が選んだ科学本リスト.xls
キーワード1 科学読み物 キーワード2 分類 キーワード3 スピーチ 授業計画・指導案等 「つなげる読書」授業.pdf 児童・生徒の作品 授業者 渡邊裕 授業者コメント 近日中にアップします。 司書・司書教諭コメント 夏休み前からずっと手元に置いていた科学の本をもとに、1分間スピーチをするという日に見学させてもらった。日頃特定の生徒しか手にとらない4類の本が、このように広く読まれたことだけでも司書としては嬉しい。そしてやはり選んだ本が面白いと思えた生徒のスピーチは、内容が濃いように感じた。図書館というと、物語の本を読むというイメージしか持っていない生徒に、科学の本のおもしろさが多少なりとも伝わり、今後の読書の幅が広がるきっかけにはなったのでは。後日生徒に書いてもらったアンケートをみせてもらったところ、多くの生徒が科学の本の面白さに気づき、つながりを考えて本を選ぶという視点を持てたこと、また自分の思いをスピーチという形で表現することの難しさや楽しさを綴っていた。こういう形で図書館の資料が役立つ企画はとてもいいのではと感じた。
情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2010年12月 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3800287 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0045 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 「つながる/ つなげる読書~図書館との協働」 |
| 対象学年 | 中1 |
| 活用・支援の種類 | 図書館からは、分類のしくみ・科学の本の選び方・等の指導 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 「動物の睡眠」を学習したあとなので、物語や小説ではなく、説明文を読ませたいのですが・・・。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 具体的には、科学の本を読んで、自分が一番驚いたことを、200文字にまとめるという作業(リライト)をし、それをもとに、2学期に1分間スピーチをさせたいとのこと。そこで、学校司書からは、「科学の本」を読むことの意味と面白さを伝えたうえで、4類の分類のしくみ、科学の本の選び方などを話し、自由に本を選んでもらうことに。また、選んだ本をワークシートを書き込んでもらったあとで、次の一冊をどうやって探すかまでを宿題としたので、そのさがし方も簡単に説明することにした。 |
| 提示資料 | 理科読を薦める本、スピーチに役立つ本、分類のしくみを理解する上で役立つ本の3冊。 |
 | 『理科読をはじめよう』 滝川洋二編 岩波書店 2010年・・子どもたちの科学離れを憂う人たちの思いが詰まった一冊。子どもの「なぜ」を大切にすることは、探求心を育み世界を広げること。だからこそ科学の本の面白さを伝えたい。様々な現場で実際に子どもたちに科学の本を手渡している人たちの日々の実践も書かれた好著。 |
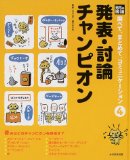 | 『発表・討論チャンピオン;調べて、まとめて、コミュニケーション4』 中川一史・高木まさき 監修 光村教育図書 2003・・・この巻ではいろいろな発表の方法や討論のしかたを、具体的な例をあげて紹介している。今回はスピーチ、ショー・アンド・テルを参考にして、生徒にスピーチ原稿のつくりかたや話し方を指導。 |
 | 『調べ学習の基礎の基礎;だれでもできる赤木かん子の魔法の図書館学』 赤木かん子 著ポプラ社 2006・・・小学生向けに、調べるための基本をやさしく解説した一冊。左ページに解説、右ページにワークシートという構成で、見開きをコピーすればそのまま授業で使えるという親切なつくりの本。今回直接使用したわけではないが、分類の仕組みを話すうえで参考にした本の1冊。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 生徒が選んだ科学本リスト.xls |
| キーワード1 | 科学読み物 |
| キーワード2 | 分類 |
| キーワード3 | スピーチ |
| 授業計画・指導案等 | 「つなげる読書」授業.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 渡邊裕 |
| 授業者コメント | 近日中にアップします。 |
| 司書・司書教諭コメント | 夏休み前からずっと手元に置いていた科学の本をもとに、1分間スピーチをするという日に見学させてもらった。日頃特定の生徒しか手にとらない4類の本が、このように広く読まれたことだけでも司書としては嬉しい。そしてやはり選んだ本が面白いと思えた生徒のスピーチは、内容が濃いように感じた。図書館というと、物語の本を読むというイメージしか持っていない生徒に、科学の本のおもしろさが多少なりとも伝わり、今後の読書の幅が広がるきっかけにはなったのでは。後日生徒に書いてもらったアンケートをみせてもらったところ、多くの生徒が科学の本の面白さに気づき、つながりを考えて本を選ぶという視点を持てたこと、また自分の思いをスピーチという形で表現することの難しさや楽しさを綴っていた。こういう形で図書館の資料が役立つ企画はとてもいいのではと感じた。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
| 事例作成日 | 2010年12月 |
| 事例作成者氏名 | 村上恭子 |
記入者:村上

























