お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0059 校種 小学校 教科・領域等 特別活動 単元 お話し給食(詩) 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 給食献立について、読書月間の特集を「詩」にしたいので、小学生になじみのある詩、食べ物が出てくる詩の載っている本を読みたい。(全校対象) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 絵本、アンソロジー、教科書、指導者用のものなんでもいいということだったので、詩のコーナーに案内し、教科書は図書館常備のものを貸した。
提示資料 食べ物が出てくる詩の本 
『子どもと読む詩 30選 小学校1・2年』 渡辺増治・長谷川峻編 桐書房 2000年 子どもと詩を教室で楽しもうという教師のための本。子どもと読むのに適した詩、教科書でなじみのある詩を春夏秋冬、人間、自然、言葉あそびやナンセンス・比喩の項目で選んでいる。各詩に鑑賞のポイントがつく。巻末に鑑賞の基本や授業のことが解説されている。3・4年、5・6年の3部作。子どもに身近な詩をまず知るにはいいアンソロジー。
『みんなで読む詩・ひとりで読む詩 全6巻』 小海永二編 ポプラ社 1996年 これも子どもに身近な様々な詩が入っている。 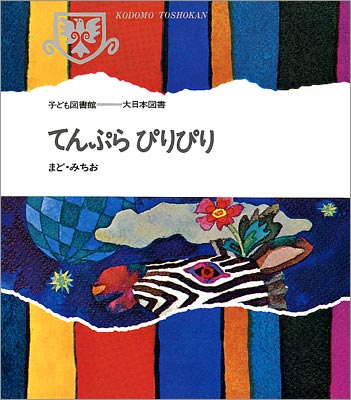
『てんぷらぴりぴり』 まどみちお 大日本図書 2010年(1982年の新版か) 「ほら おかあさんが ことしも また てんぷら ぴりぴり あげだした」という「てんぷらぴりぴり」ほか、「タマネギ」「スイカのたね」「カキ」「つけものの おもし」「音」にもたべものの詩がある。まどさんの日常の生活をキラリと切り取るやさしいまなざしを感じる。 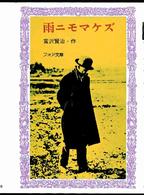
『雨ニモマケズ』 宮沢賢治 岩崎書店 1990年
賢治の詩や短歌、手紙などを年代順に載せる。後半は、兄清六により「賢治の一生」を紹介する。実際に貸し出した本は同じ岩崎書店の『新装宮沢賢治童話全集12 雨ニモマケズ』であるが、上記フォア文庫はこれをもとに編集しなおしたと思われる。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 給食 キーワード2 詩 キーワード3 読書月間 授業計画・指導案等 おはなし給食.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 横山英吏子 授業者コメント 11月の読書月間に合わせ、学校給食で「お話の中の献立」を特集しました。H19年から継続して行っている取り組みです。昨年までは、物語や教科書の中、人気のある図書館の本から献立を組み立てていました。今年度は、「詩」をテーマに取りあげ、詩の魅力を給食を通して感じて欲しいと思いました。
実施当日は、食堂前の展示コーナーに、給食のサンプルとともに、題材となった詩や、その作者の詩集を並べたところ、たくさんの子どもたちが、じっくりと展示コーナーに見入り、関心を寄せていました。いくつかの学級では、その日の献立の詩を音読の宿題にするなど、国語との関連も見られました。
実際に食べることで、子どもの中に「お話」と「お話の中の献立」が、すぅっと入っていったようで、「はたはた」や「しその実」など、食べたことのない食材と、詩が結びつき、「とても心に残りました。」「食べたことがなくて、どんな味かな?と思っていたけど、スーッとしていておいしかったです。」「もっと本が読みたくなりました。」などの声が聞けました。言葉は抽象の世界ですが、この献立を通して、食材を知っている詩人の気持ちに限りなく近づくことができたのではないでしょうか。実際に見て、味わう体験を通して、より作品の世界を具体的にイメージすることができ、理解が深まったのではと感じています。
司書・司書教諭コメント 相談されたのは、7月夏休みに入って間もなく。「てんぷらぴりぴり」は、ちょうど改めて読んでいたところだったので、食べ物が他にも出てくるからと真っ先に案内した。たくさんの詩人の詩が出ている本ということで『子どもと読む詩30選』などを紹介し、詩の棚に案内した。夏休みはアンソロジーが中心だったが、好きな詩人を発掘していたという熱心さにこちらもびっくりだった。教科書も館内保存用を貸出した。教科書にある「はたはたのうた」にあるはたはたが、から揚げになってでてきたので、文語詩がずいぶん身近になったようだった。人気だったのはやはり宮沢賢治。有名な「雨ニモマケズ」は、給食をきっかけにあっちこっちで話題になっていたようだった。お話し給食の1週間が終わった後、食堂の掲示をまとめて、館内でもしばらく行ったところ、子どもたちはよく話題にし、よく借りていってくれた。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2011.2.24 事例作成者氏名 中山美由紀
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863371 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0059 校種 小学校 教科・領域等 特別活動 単元 お話し給食(詩) 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 給食献立について、読書月間の特集を「詩」にしたいので、小学生になじみのある詩、食べ物が出てくる詩の載っている本を読みたい。(全校対象) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 絵本、アンソロジー、教科書、指導者用のものなんでもいいということだったので、詩のコーナーに案内し、教科書は図書館常備のものを貸した。
提示資料 食べ物が出てくる詩の本 
『子どもと読む詩 30選 小学校1・2年』 渡辺増治・長谷川峻編 桐書房 2000年 子どもと詩を教室で楽しもうという教師のための本。子どもと読むのに適した詩、教科書でなじみのある詩を春夏秋冬、人間、自然、言葉あそびやナンセンス・比喩の項目で選んでいる。各詩に鑑賞のポイントがつく。巻末に鑑賞の基本や授業のことが解説されている。3・4年、5・6年の3部作。子どもに身近な詩をまず知るにはいいアンソロジー。
『みんなで読む詩・ひとりで読む詩 全6巻』 小海永二編 ポプラ社 1996年 これも子どもに身近な様々な詩が入っている。 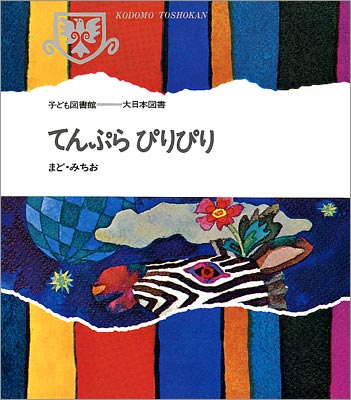
『てんぷらぴりぴり』 まどみちお 大日本図書 2010年(1982年の新版か) 「ほら おかあさんが ことしも また てんぷら ぴりぴり あげだした」という「てんぷらぴりぴり」ほか、「タマネギ」「スイカのたね」「カキ」「つけものの おもし」「音」にもたべものの詩がある。まどさんの日常の生活をキラリと切り取るやさしいまなざしを感じる。 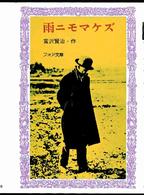
『雨ニモマケズ』 宮沢賢治 岩崎書店 1990年
賢治の詩や短歌、手紙などを年代順に載せる。後半は、兄清六により「賢治の一生」を紹介する。実際に貸し出した本は同じ岩崎書店の『新装宮沢賢治童話全集12 雨ニモマケズ』であるが、上記フォア文庫はこれをもとに編集しなおしたと思われる。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 給食 キーワード2 詩 キーワード3 読書月間 授業計画・指導案等 おはなし給食.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 横山英吏子 授業者コメント 11月の読書月間に合わせ、学校給食で「お話の中の献立」を特集しました。H19年から継続して行っている取り組みです。昨年までは、物語や教科書の中、人気のある図書館の本から献立を組み立てていました。今年度は、「詩」をテーマに取りあげ、詩の魅力を給食を通して感じて欲しいと思いました。
実施当日は、食堂前の展示コーナーに、給食のサンプルとともに、題材となった詩や、その作者の詩集を並べたところ、たくさんの子どもたちが、じっくりと展示コーナーに見入り、関心を寄せていました。いくつかの学級では、その日の献立の詩を音読の宿題にするなど、国語との関連も見られました。
実際に食べることで、子どもの中に「お話」と「お話の中の献立」が、すぅっと入っていったようで、「はたはた」や「しその実」など、食べたことのない食材と、詩が結びつき、「とても心に残りました。」「食べたことがなくて、どんな味かな?と思っていたけど、スーッとしていておいしかったです。」「もっと本が読みたくなりました。」などの声が聞けました。言葉は抽象の世界ですが、この献立を通して、食材を知っている詩人の気持ちに限りなく近づくことができたのではないでしょうか。実際に見て、味わう体験を通して、より作品の世界を具体的にイメージすることができ、理解が深まったのではと感じています。
司書・司書教諭コメント 相談されたのは、7月夏休みに入って間もなく。「てんぷらぴりぴり」は、ちょうど改めて読んでいたところだったので、食べ物が他にも出てくるからと真っ先に案内した。たくさんの詩人の詩が出ている本ということで『子どもと読む詩30選』などを紹介し、詩の棚に案内した。夏休みはアンソロジーが中心だったが、好きな詩人を発掘していたという熱心さにこちらもびっくりだった。教科書も館内保存用を貸出した。教科書にある「はたはたのうた」にあるはたはたが、から揚げになってでてきたので、文語詩がずいぶん身近になったようだった。人気だったのはやはり宮沢賢治。有名な「雨ニモマケズ」は、給食をきっかけにあっちこっちで話題になっていたようだった。お話し給食の1週間が終わった後、食堂の掲示をまとめて、館内でもしばらく行ったところ、子どもたちはよく話題にし、よく借りていってくれた。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2011.2.24 事例作成者氏名 中山美由紀
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863371 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0059 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 特別活動 |
| 単元 | お話し給食(詩) |
| 対象学年 | 高学年 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 給食献立について、読書月間の特集を「詩」にしたいので、小学生になじみのある詩、食べ物が出てくる詩の載っている本を読みたい。(全校対象) |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 絵本、アンソロジー、教科書、指導者用のものなんでもいいということだったので、詩のコーナーに案内し、教科書は図書館常備のものを貸した。 |
| 提示資料 | 食べ物が出てくる詩の本 |
 | 『子どもと読む詩 30選 小学校1・2年』 渡辺増治・長谷川峻編 桐書房 2000年 子どもと詩を教室で楽しもうという教師のための本。子どもと読むのに適した詩、教科書でなじみのある詩を春夏秋冬、人間、自然、言葉あそびやナンセンス・比喩の項目で選んでいる。各詩に鑑賞のポイントがつく。巻末に鑑賞の基本や授業のことが解説されている。3・4年、5・6年の3部作。子どもに身近な詩をまず知るにはいいアンソロジー。 『みんなで読む詩・ひとりで読む詩 全6巻』 小海永二編 ポプラ社 1996年 これも子どもに身近な様々な詩が入っている。 |
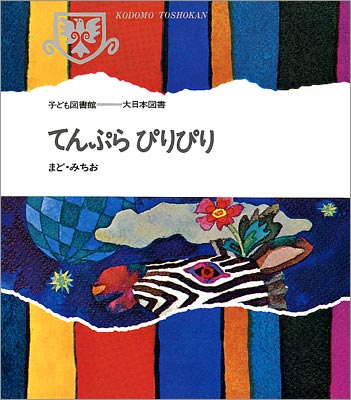 | 『てんぷらぴりぴり』 まどみちお 大日本図書 2010年(1982年の新版か) 「ほら おかあさんが ことしも また てんぷら ぴりぴり あげだした」という「てんぷらぴりぴり」ほか、「タマネギ」「スイカのたね」「カキ」「つけものの おもし」「音」にもたべものの詩がある。まどさんの日常の生活をキラリと切り取るやさしいまなざしを感じる。 |
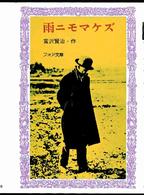 | 『雨ニモマケズ』 宮沢賢治 岩崎書店 1990年 賢治の詩や短歌、手紙などを年代順に載せる。後半は、兄清六により「賢治の一生」を紹介する。実際に貸し出した本は同じ岩崎書店の『新装宮沢賢治童話全集12 雨ニモマケズ』であるが、上記フォア文庫はこれをもとに編集しなおしたと思われる。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 給食 |
| キーワード2 | 詩 |
| キーワード3 | 読書月間 |
| 授業計画・指導案等 | おはなし給食.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 横山英吏子 |
| 授業者コメント | 11月の読書月間に合わせ、学校給食で「お話の中の献立」を特集しました。H19年から継続して行っている取り組みです。昨年までは、物語や教科書の中、人気のある図書館の本から献立を組み立てていました。今年度は、「詩」をテーマに取りあげ、詩の魅力を給食を通して感じて欲しいと思いました。 実施当日は、食堂前の展示コーナーに、給食のサンプルとともに、題材となった詩や、その作者の詩集を並べたところ、たくさんの子どもたちが、じっくりと展示コーナーに見入り、関心を寄せていました。いくつかの学級では、その日の献立の詩を音読の宿題にするなど、国語との関連も見られました。 実際に食べることで、子どもの中に「お話」と「お話の中の献立」が、すぅっと入っていったようで、「はたはた」や「しその実」など、食べたことのない食材と、詩が結びつき、「とても心に残りました。」「食べたことがなくて、どんな味かな?と思っていたけど、スーッとしていておいしかったです。」「もっと本が読みたくなりました。」などの声が聞けました。言葉は抽象の世界ですが、この献立を通して、食材を知っている詩人の気持ちに限りなく近づくことができたのではないでしょうか。実際に見て、味わう体験を通して、より作品の世界を具体的にイメージすることができ、理解が深まったのではと感じています。 |
| 司書・司書教諭コメント | 相談されたのは、7月夏休みに入って間もなく。「てんぷらぴりぴり」は、ちょうど改めて読んでいたところだったので、食べ物が他にも出てくるからと真っ先に案内した。たくさんの詩人の詩が出ている本ということで『子どもと読む詩30選』などを紹介し、詩の棚に案内した。夏休みはアンソロジーが中心だったが、好きな詩人を発掘していたという熱心さにこちらもびっくりだった。教科書も館内保存用を貸出した。教科書にある「はたはたのうた」にあるはたはたが、から揚げになってでてきたので、文語詩がずいぶん身近になったようだった。人気だったのはやはり宮沢賢治。有名な「雨ニモマケズ」は、給食をきっかけにあっちこっちで話題になっていたようだった。お話し給食の1週間が終わった後、食堂の掲示をまとめて、館内でもしばらく行ったところ、子どもたちはよく話題にし、よく借りていってくれた。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |
| 事例作成日 | 2011.2.24 |
| 事例作成者氏名 | 中山美由紀 |
記入者:中山(主担)

























