お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0064 校種 中学校 教科・領域等 音楽 単元 「ベートーヴェン・レポート」 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供、レポートとして課す内容の提案、レポートの基本形および具体的な書き方ガイダンス、レポート完成までの流れにそったワークブック作成 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 交響曲第5番「運命」の鑑賞文+レポート=「ベートーヴェン・レポート」としたい。
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ロマン派までの西洋音楽史の流れを理解させた上で、ベートーヴェンに関するレポート作成をさせたい。また、交響曲第5番「運命」を授業内で鑑賞し、第一楽章から第四楽章まで細かな解説も加える。さらにオーケストラの映像も見せる。
提示資料 ベートーヴェンの生涯と音楽が大まかに分かる本を4タイトル選び、それらは各8冊ずつ用意した。(基本資料) さらに詳細に調べられる本や専門的な本まで、できるだけ揃えるようにした。揃えた本は、およそ120冊。オンライン百科事典「ポプラディアネット」「ジャパンナレッジ」は、出力してファイルにした。
下記に提示できなかったもう1冊は、『世界の音楽家たち:楽聖ベートーヴェン』 汐文社 2005

『伝記 世界の作曲家(4)ベートーベン―古典派音楽を完成したドイツの作曲家 』 パム ブラウン著 橘高 弓枝訳 偕成社 1998
小学校高学年から読める音楽家の伝記。写真や図版も多く、読みやすい。
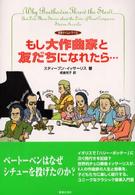
『もし大作曲家と友だちになれたら・・・』
スティーブン・イッサリース著 板倉克子訳 音楽之友社 2003
6人の大作曲家たちが、どんな人で、どんな人生を送ったかを、ユーモアを交えわかりやすく伝えてくれる。
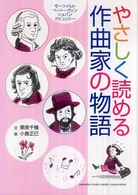
『やさしく読める作曲家の物語』
栗原千種著 ヤマハミュージックメディア 2010
作曲家の人生や作品について、タイトルどおりとてもやさしく書かれた本で、クラッシックに興味がない生徒も読み進めることができる。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 ベートーヴェン キーワード2 音楽鑑賞 キーワード3 レポート 授業計画・指導案等 中2音楽_ワークp20.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 山下彩 授業者コメント 生徒として「ベートーヴェン・レポート」に取り組んだ経験を持っている。その為、この調べ学習は教える側からみると、生徒たちに「ベートーヴェンについて図書館で調べてレポートを書きなさい」と伝えるだけの、楽なものだと考えていた。ところが、遊佐先生との事前打ち合わせにより単に調べてまとめるだけの課題ではないことがわかった。前年度のレポートを読むと、調べたことを元に「独自のトピック」を立て、そうなった理由を探し、結論を導いていた。中二がどうしてこのような手順を踏めるのか、頭の中は疑問で埋め尽くされた。疑問の答えは、遊佐先生作成の「ワークブック」にあった。生徒はワークブックの手順に従って進めていくことが出来る作りになっていた。当然、各クラス三時間の図書館での授業は、このワークブックに沿って実施した。
生徒にとって最も難しかったのは、第三章「独自のトピック」を立てることだった。「ベートーヴェンは何故ドイツで生まれたのか?」「ベートーヴェンの好きな食べ物はなにか?」など、珍トピック続出。一人ひとり興味を持つことが違うので、提出されたワークに何度もコメントを返し、それぞれに合ったトピックになるよう導いた。ここが生徒たちにとっても、私にとっても一番の難題だったように思う。しかし、この第三章こそが、この課題のねらいだった。
生徒の感想をご紹介する。「レポートを一人で全部作るのは初めてで、出来るわけがないと思っていたが、調べるうちにどんどん新しい知識が増えていくのが面白かった。ベートーヴェンは無愛想な顔だから性格が悪いのかと思っていたが、そうではなかった。イメージが変わった。物事は、知っていると知らないでは、全く違うのだと思った」。苦労が報われた気がした。この課題を通して、私自身も本当の意味での「調べる」とはどういうことなのかを学んだ。 司書・司書教諭コメント 中学2年・音楽でレポートを書くという課題は、およそ10年前から行われている。図書館の支援は、3期に分かれる。第1期:資料提供。 第2期:「資料提供」に加えてレポート指導。レポートの基本形をはじめ、参考文献の書き方など、どちらかといえば形式を指導。 第3期(現在):「資料提供」と「レポートの形式指導」に加えて、情報のまとめ方、問い→理由(根拠)→結論(意見)の方法、序論の書き方など、レポートの中身に言及する指導に重点を置いている。レポートが情報の「切り貼り」や「羅列」と言った不毛な作業にならないように、章立てを予めこちらで作り、レポート完成までの流れに沿ったワークブック作成した。子どもたちは、立てた問いの答えを事実やデータに求めなければならないことに苦戦していた。この課題は、中3での公民「時事問題スピーチ」に向けた準備という位置づけを図書館側はしている。
情報提供校 東京純心女子中学校 事例作成日 2011年5月11日 事例作成者氏名 遊佐幸枝
記入者:村上
カウンタ
3863386 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0064 校種 中学校 教科・領域等 音楽 単元 「ベートーヴェン・レポート」 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供、レポートとして課す内容の提案、レポートの基本形および具体的な書き方ガイダンス、レポート完成までの流れにそったワークブック作成 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 交響曲第5番「運命」の鑑賞文+レポート=「ベートーヴェン・レポート」としたい。
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ロマン派までの西洋音楽史の流れを理解させた上で、ベートーヴェンに関するレポート作成をさせたい。また、交響曲第5番「運命」を授業内で鑑賞し、第一楽章から第四楽章まで細かな解説も加える。さらにオーケストラの映像も見せる。
提示資料 ベートーヴェンの生涯と音楽が大まかに分かる本を4タイトル選び、それらは各8冊ずつ用意した。(基本資料) さらに詳細に調べられる本や専門的な本まで、できるだけ揃えるようにした。揃えた本は、およそ120冊。オンライン百科事典「ポプラディアネット」「ジャパンナレッジ」は、出力してファイルにした。
下記に提示できなかったもう1冊は、『世界の音楽家たち:楽聖ベートーヴェン』 汐文社 2005

『伝記 世界の作曲家(4)ベートーベン―古典派音楽を完成したドイツの作曲家 』 パム ブラウン著 橘高 弓枝訳 偕成社 1998
小学校高学年から読める音楽家の伝記。写真や図版も多く、読みやすい。
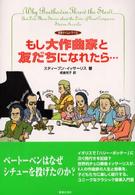
『もし大作曲家と友だちになれたら・・・』
スティーブン・イッサリース著 板倉克子訳 音楽之友社 2003
6人の大作曲家たちが、どんな人で、どんな人生を送ったかを、ユーモアを交えわかりやすく伝えてくれる。
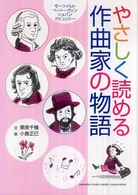
『やさしく読める作曲家の物語』
栗原千種著 ヤマハミュージックメディア 2010
作曲家の人生や作品について、タイトルどおりとてもやさしく書かれた本で、クラッシックに興味がない生徒も読み進めることができる。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 ベートーヴェン キーワード2 音楽鑑賞 キーワード3 レポート 授業計画・指導案等 中2音楽_ワークp20.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 山下彩 授業者コメント 生徒として「ベートーヴェン・レポート」に取り組んだ経験を持っている。その為、この調べ学習は教える側からみると、生徒たちに「ベートーヴェンについて図書館で調べてレポートを書きなさい」と伝えるだけの、楽なものだと考えていた。ところが、遊佐先生との事前打ち合わせにより単に調べてまとめるだけの課題ではないことがわかった。前年度のレポートを読むと、調べたことを元に「独自のトピック」を立て、そうなった理由を探し、結論を導いていた。中二がどうしてこのような手順を踏めるのか、頭の中は疑問で埋め尽くされた。疑問の答えは、遊佐先生作成の「ワークブック」にあった。生徒はワークブックの手順に従って進めていくことが出来る作りになっていた。当然、各クラス三時間の図書館での授業は、このワークブックに沿って実施した。
生徒にとって最も難しかったのは、第三章「独自のトピック」を立てることだった。「ベートーヴェンは何故ドイツで生まれたのか?」「ベートーヴェンの好きな食べ物はなにか?」など、珍トピック続出。一人ひとり興味を持つことが違うので、提出されたワークに何度もコメントを返し、それぞれに合ったトピックになるよう導いた。ここが生徒たちにとっても、私にとっても一番の難題だったように思う。しかし、この第三章こそが、この課題のねらいだった。
生徒の感想をご紹介する。「レポートを一人で全部作るのは初めてで、出来るわけがないと思っていたが、調べるうちにどんどん新しい知識が増えていくのが面白かった。ベートーヴェンは無愛想な顔だから性格が悪いのかと思っていたが、そうではなかった。イメージが変わった。物事は、知っていると知らないでは、全く違うのだと思った」。苦労が報われた気がした。この課題を通して、私自身も本当の意味での「調べる」とはどういうことなのかを学んだ。 司書・司書教諭コメント 中学2年・音楽でレポートを書くという課題は、およそ10年前から行われている。図書館の支援は、3期に分かれる。第1期:資料提供。 第2期:「資料提供」に加えてレポート指導。レポートの基本形をはじめ、参考文献の書き方など、どちらかといえば形式を指導。 第3期(現在):「資料提供」と「レポートの形式指導」に加えて、情報のまとめ方、問い→理由(根拠)→結論(意見)の方法、序論の書き方など、レポートの中身に言及する指導に重点を置いている。レポートが情報の「切り貼り」や「羅列」と言った不毛な作業にならないように、章立てを予めこちらで作り、レポート完成までの流れに沿ったワークブック作成した。子どもたちは、立てた問いの答えを事実やデータに求めなければならないことに苦戦していた。この課題は、中3での公民「時事問題スピーチ」に向けた準備という位置づけを図書館側はしている。
情報提供校 東京純心女子中学校 事例作成日 2011年5月11日 事例作成者氏名 遊佐幸枝
記入者:村上
カウンタ
3863386 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0064 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 音楽 |
| 単元 | 「ベートーヴェン・レポート」 |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供、レポートとして課す内容の提案、レポートの基本形および具体的な書き方ガイダンス、レポート完成までの流れにそったワークブック作成 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 交響曲第5番「運命」の鑑賞文+レポート=「ベートーヴェン・レポート」としたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | ロマン派までの西洋音楽史の流れを理解させた上で、ベートーヴェンに関するレポート作成をさせたい。また、交響曲第5番「運命」を授業内で鑑賞し、第一楽章から第四楽章まで細かな解説も加える。さらにオーケストラの映像も見せる。 |
| 提示資料 | ベートーヴェンの生涯と音楽が大まかに分かる本を4タイトル選び、それらは各8冊ずつ用意した。(基本資料) さらに詳細に調べられる本や専門的な本まで、できるだけ揃えるようにした。揃えた本は、およそ120冊。オンライン百科事典「ポプラディアネット」「ジャパンナレッジ」は、出力してファイルにした。 下記に提示できなかったもう1冊は、『世界の音楽家たち:楽聖ベートーヴェン』 汐文社 2005 |
 | 『伝記 世界の作曲家(4)ベートーベン―古典派音楽を完成したドイツの作曲家 』 パム ブラウン著 橘高 弓枝訳 偕成社 1998 小学校高学年から読める音楽家の伝記。写真や図版も多く、読みやすい。 |
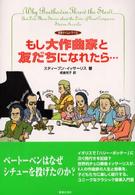 | 『もし大作曲家と友だちになれたら・・・』 スティーブン・イッサリース著 板倉克子訳 音楽之友社 2003 6人の大作曲家たちが、どんな人で、どんな人生を送ったかを、ユーモアを交えわかりやすく伝えてくれる。 |
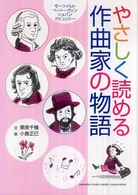 | 『やさしく読める作曲家の物語』 栗原千種著 ヤマハミュージックメディア 2010 作曲家の人生や作品について、タイトルどおりとてもやさしく書かれた本で、クラッシックに興味がない生徒も読み進めることができる。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | ベートーヴェン |
| キーワード2 | 音楽鑑賞 |
| キーワード3 | レポート |
| 授業計画・指導案等 | 中2音楽_ワークp20.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 山下彩 |
| 授業者コメント | 生徒として「ベートーヴェン・レポート」に取り組んだ経験を持っている。その為、この調べ学習は教える側からみると、生徒たちに「ベートーヴェンについて図書館で調べてレポートを書きなさい」と伝えるだけの、楽なものだと考えていた。ところが、遊佐先生との事前打ち合わせにより単に調べてまとめるだけの課題ではないことがわかった。前年度のレポートを読むと、調べたことを元に「独自のトピック」を立て、そうなった理由を探し、結論を導いていた。中二がどうしてこのような手順を踏めるのか、頭の中は疑問で埋め尽くされた。疑問の答えは、遊佐先生作成の「ワークブック」にあった。生徒はワークブックの手順に従って進めていくことが出来る作りになっていた。当然、各クラス三時間の図書館での授業は、このワークブックに沿って実施した。 生徒にとって最も難しかったのは、第三章「独自のトピック」を立てることだった。「ベートーヴェンは何故ドイツで生まれたのか?」「ベートーヴェンの好きな食べ物はなにか?」など、珍トピック続出。一人ひとり興味を持つことが違うので、提出されたワークに何度もコメントを返し、それぞれに合ったトピックになるよう導いた。ここが生徒たちにとっても、私にとっても一番の難題だったように思う。しかし、この第三章こそが、この課題のねらいだった。 生徒の感想をご紹介する。「レポートを一人で全部作るのは初めてで、出来るわけがないと思っていたが、調べるうちにどんどん新しい知識が増えていくのが面白かった。ベートーヴェンは無愛想な顔だから性格が悪いのかと思っていたが、そうではなかった。イメージが変わった。物事は、知っていると知らないでは、全く違うのだと思った」。苦労が報われた気がした。この課題を通して、私自身も本当の意味での「調べる」とはどういうことなのかを学んだ。 |
| 司書・司書教諭コメント | 中学2年・音楽でレポートを書くという課題は、およそ10年前から行われている。図書館の支援は、3期に分かれる。第1期:資料提供。 第2期:「資料提供」に加えてレポート指導。レポートの基本形をはじめ、参考文献の書き方など、どちらかといえば形式を指導。 第3期(現在):「資料提供」と「レポートの形式指導」に加えて、情報のまとめ方、問い→理由(根拠)→結論(意見)の方法、序論の書き方など、レポートの中身に言及する指導に重点を置いている。レポートが情報の「切り貼り」や「羅列」と言った不毛な作業にならないように、章立てを予めこちらで作り、レポート完成までの流れに沿ったワークブック作成した。子どもたちは、立てた問いの答えを事実やデータに求めなければならないことに苦戦していた。この課題は、中3での公民「時事問題スピーチ」に向けた準備という位置づけを図書館側はしている。 |
| 情報提供校 | 東京純心女子中学校 |
| 事例作成日 | 2011年5月11日 |
| 事例作成者氏名 | 遊佐幸枝 |
記入者:村上

























